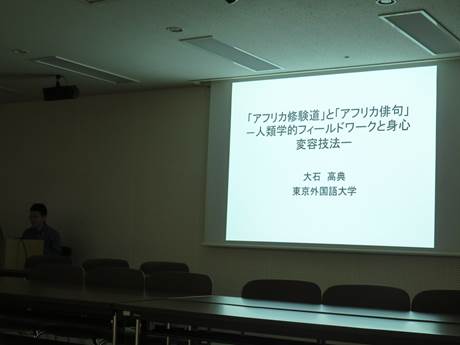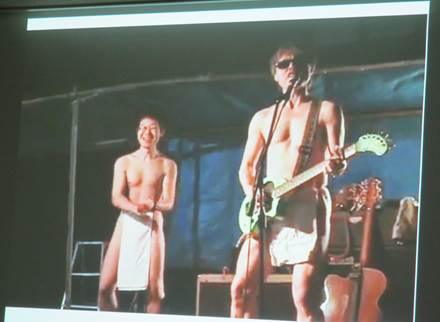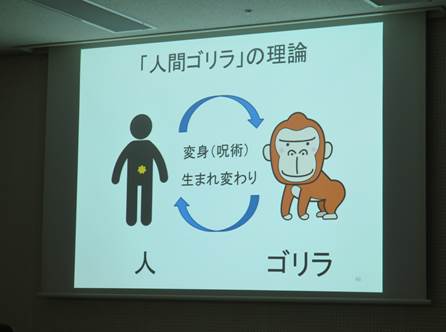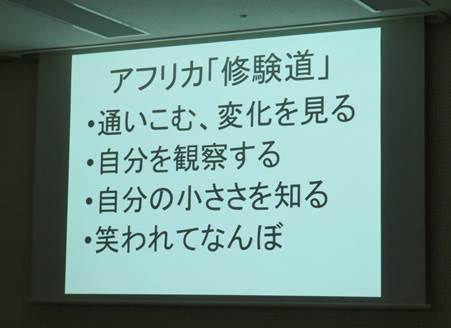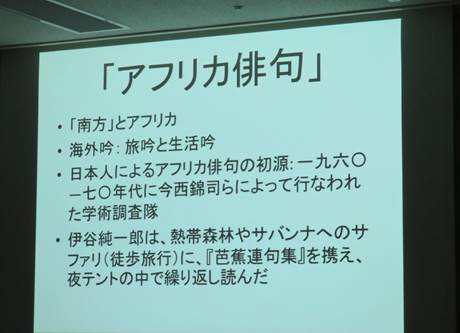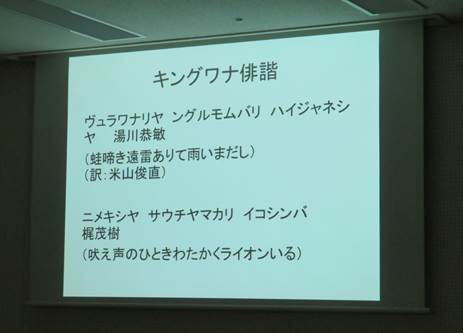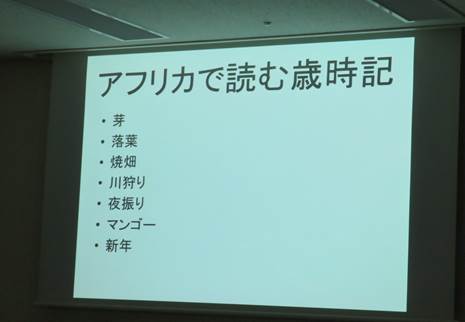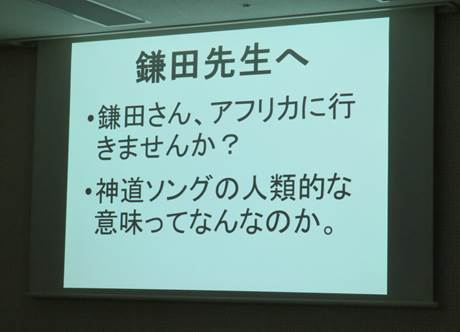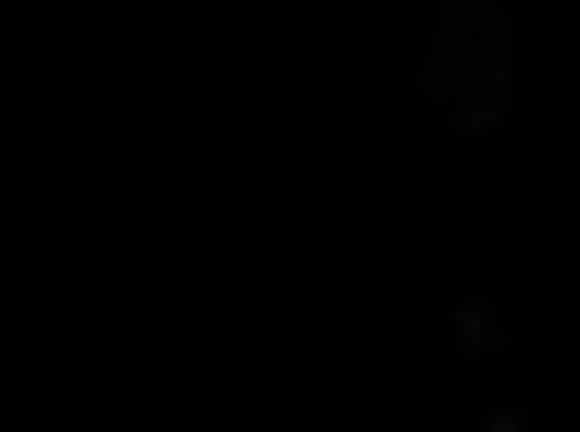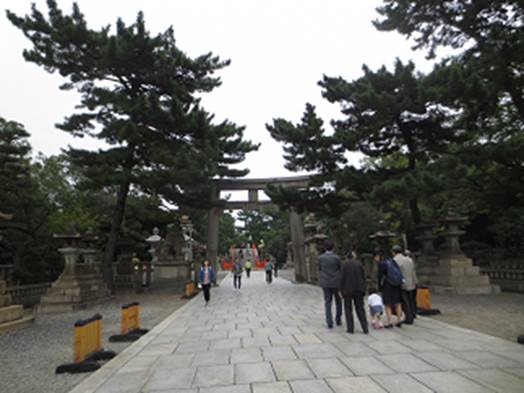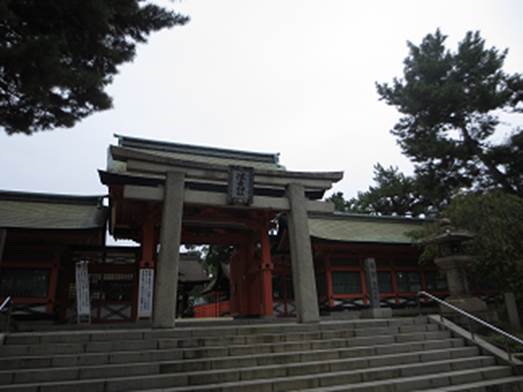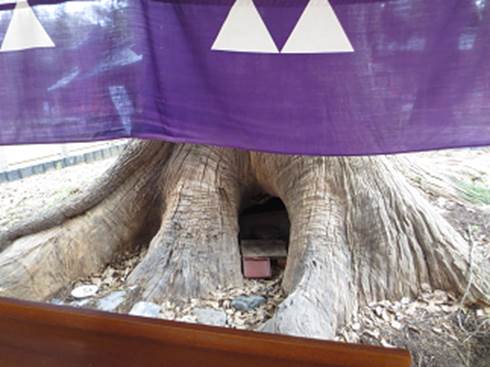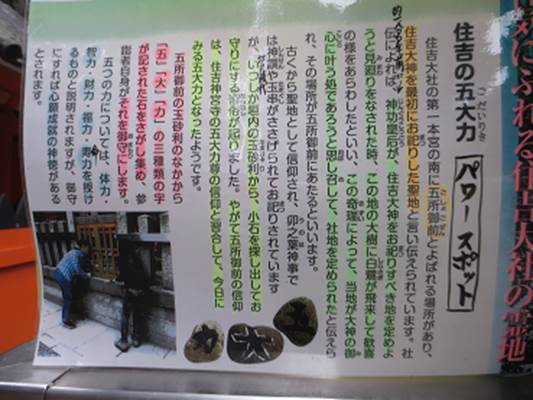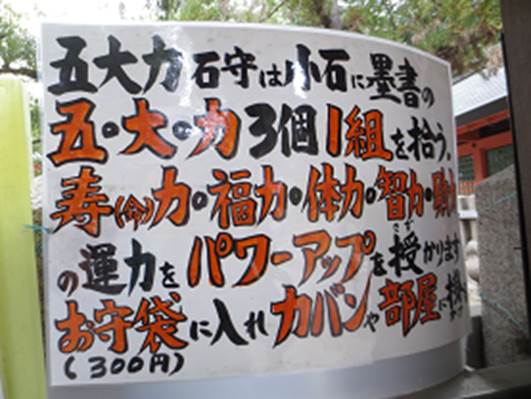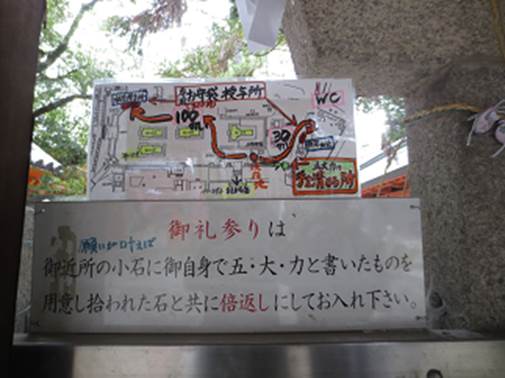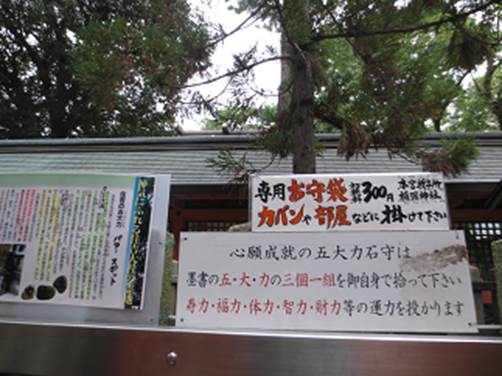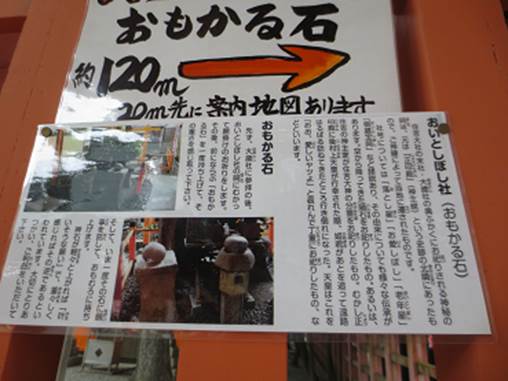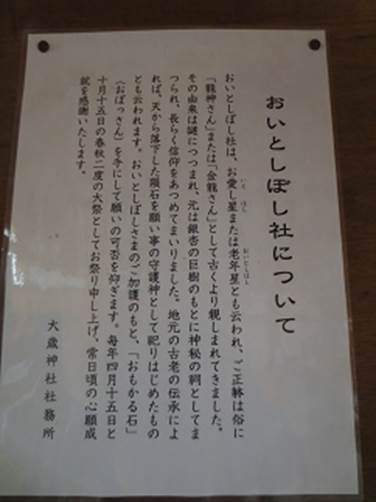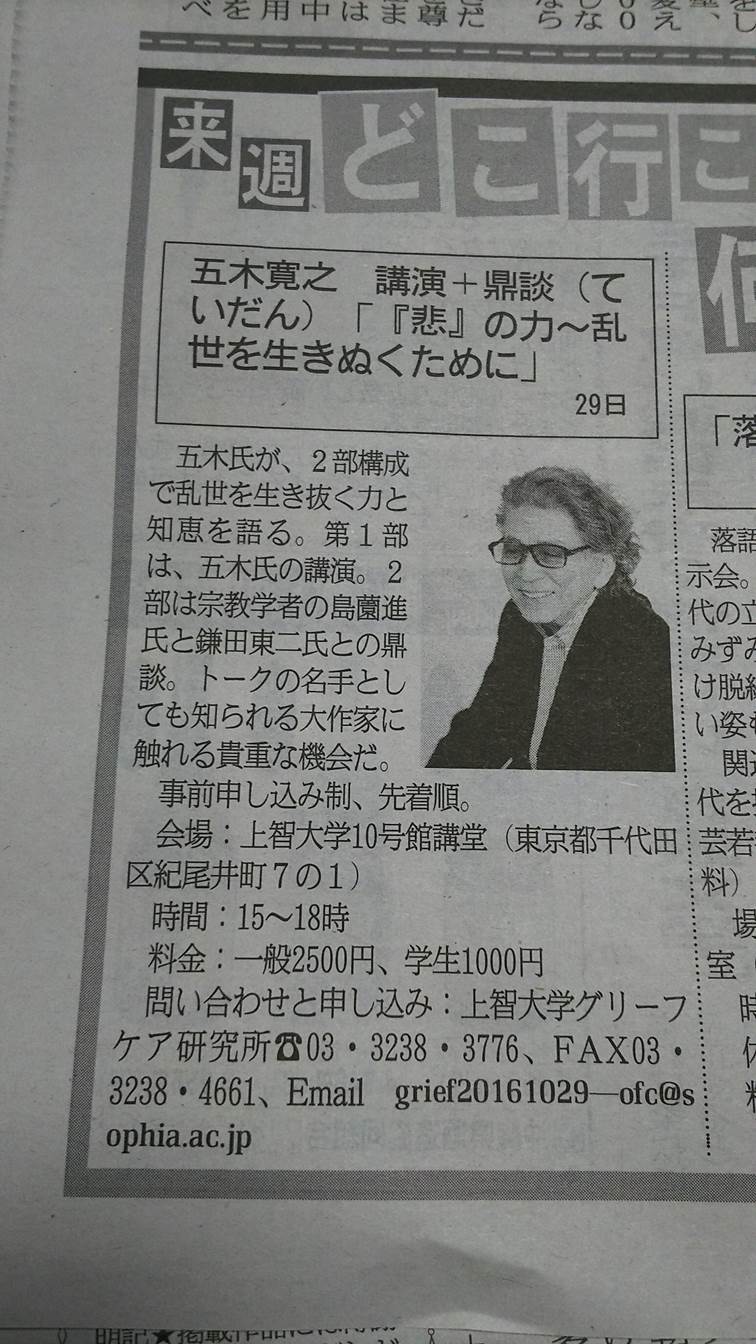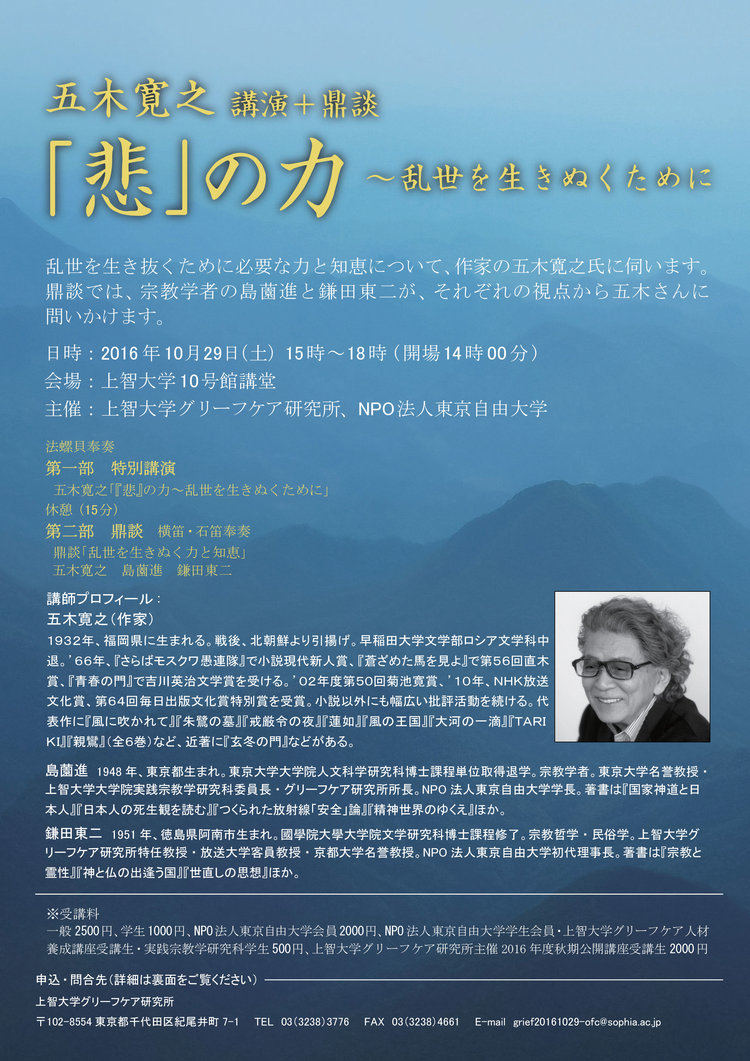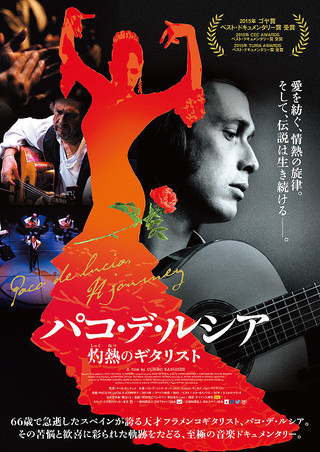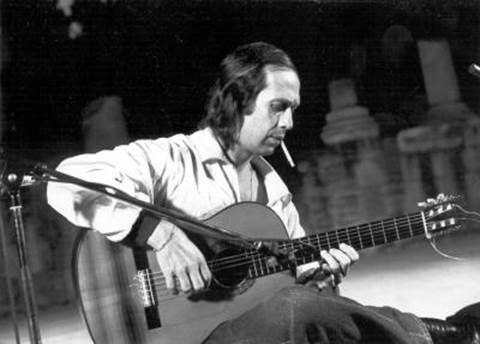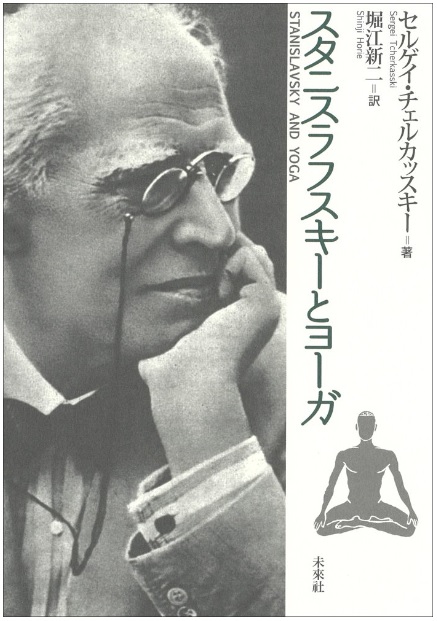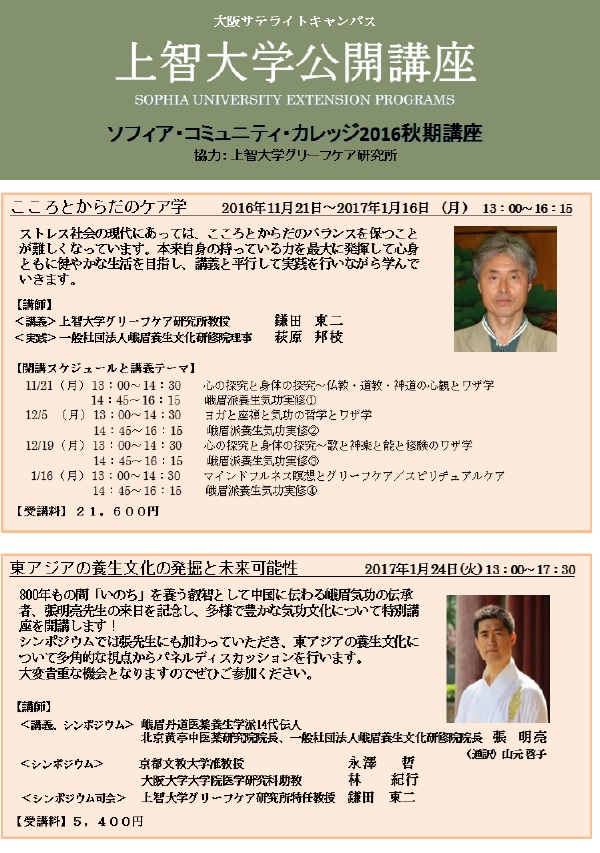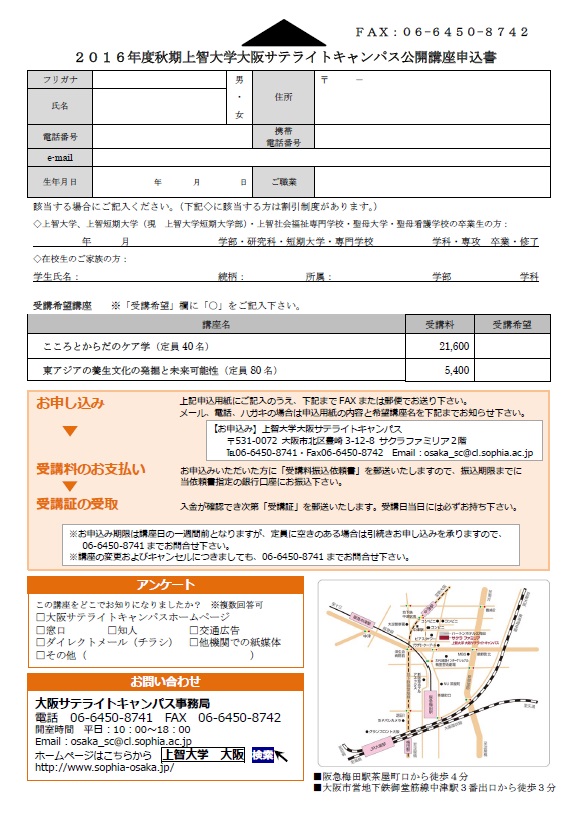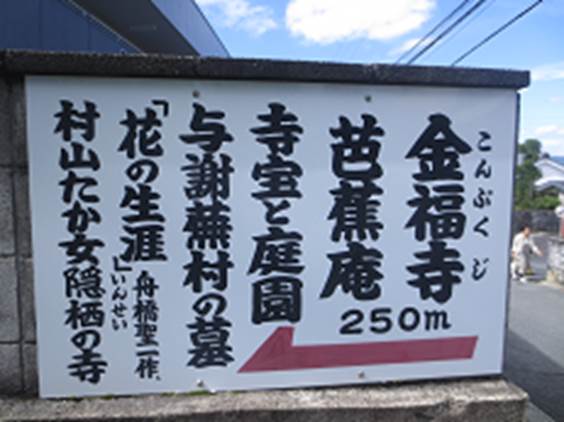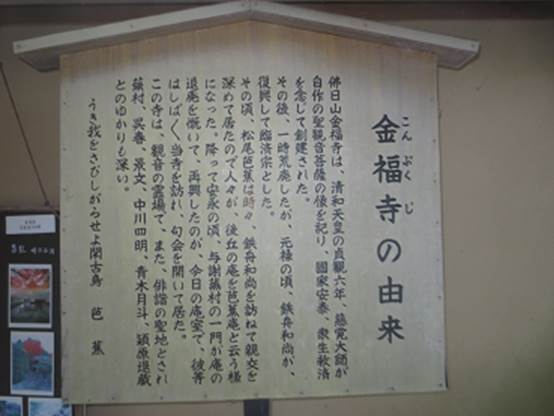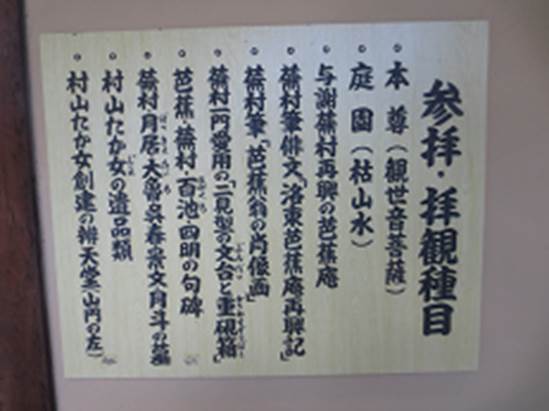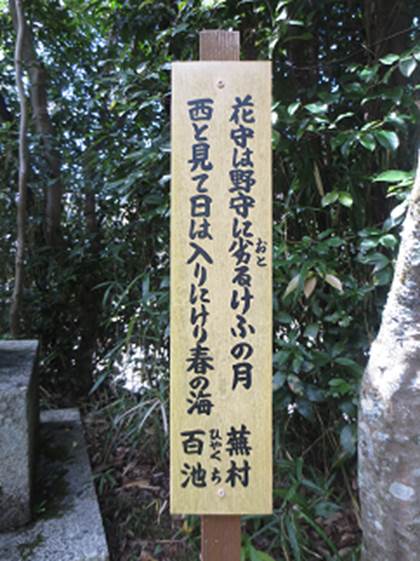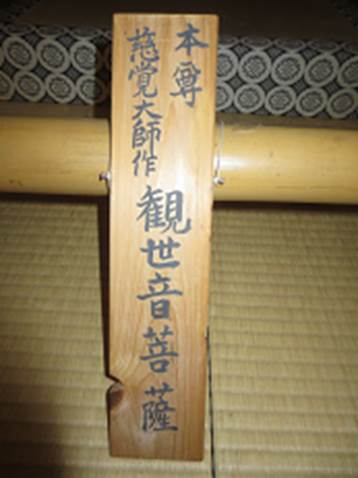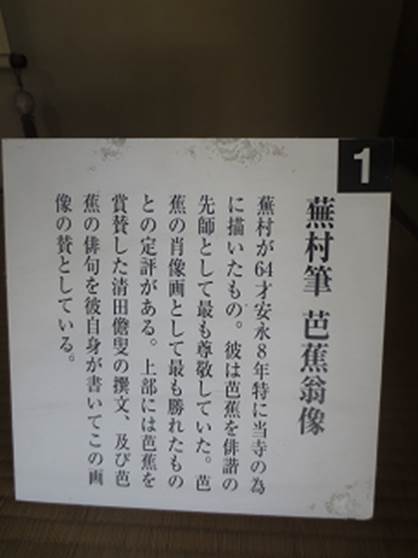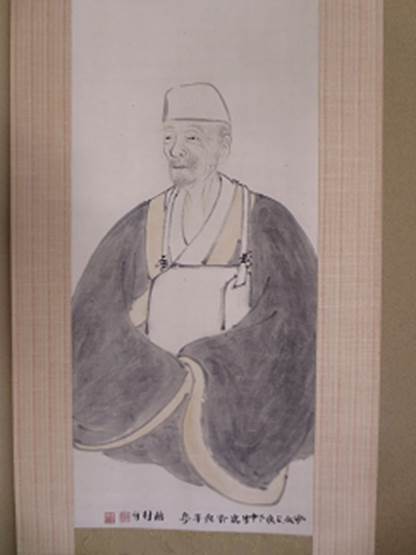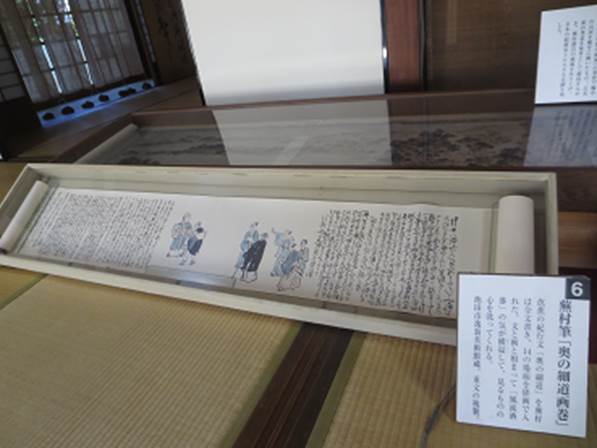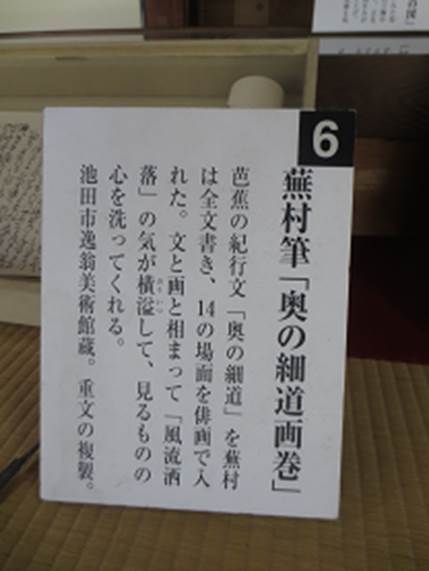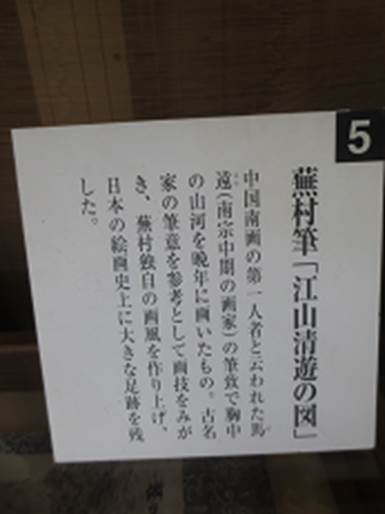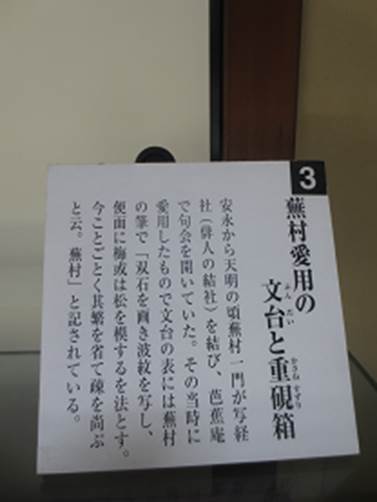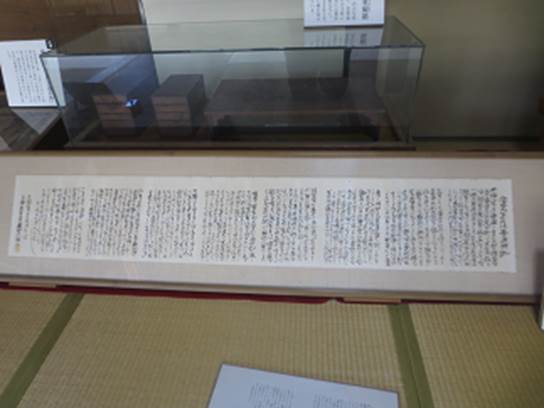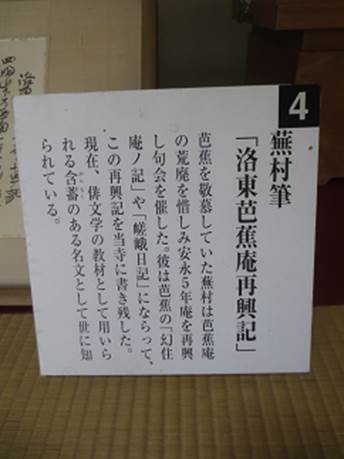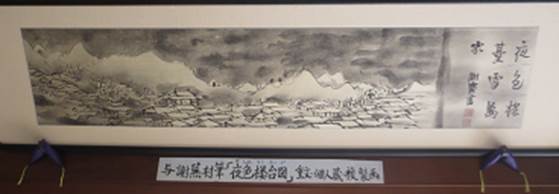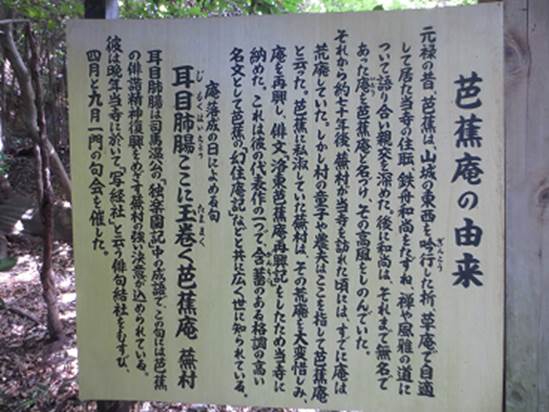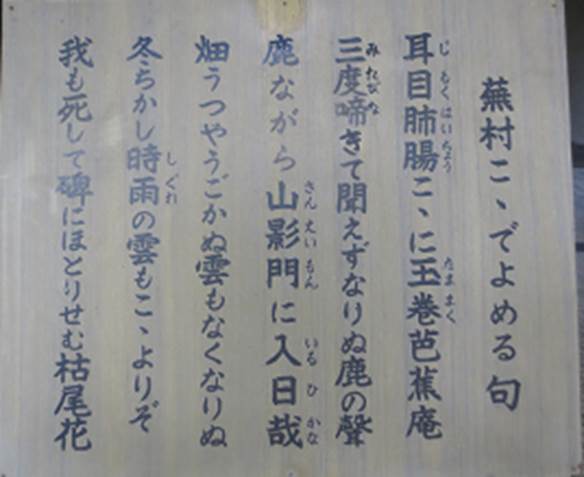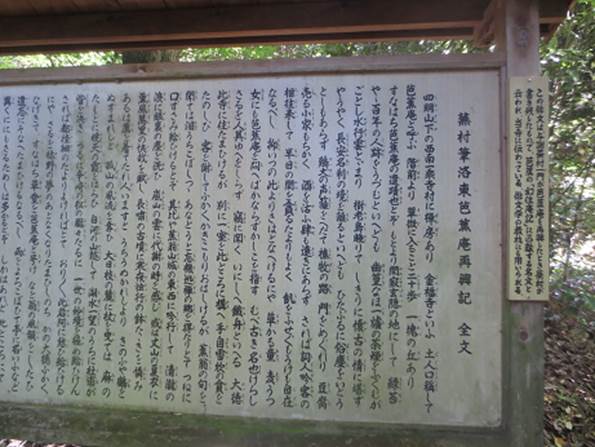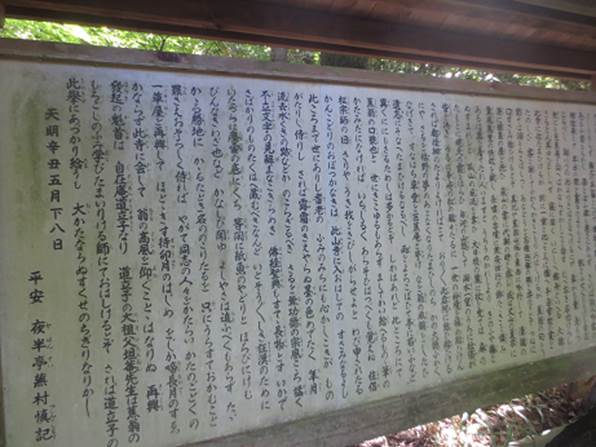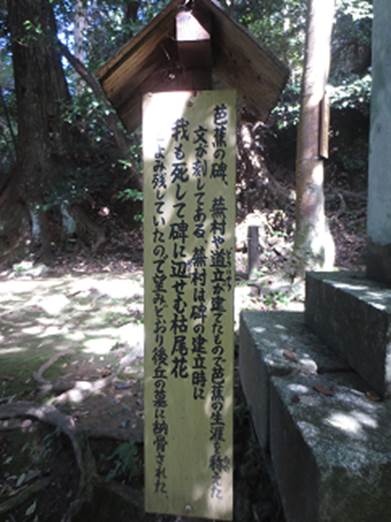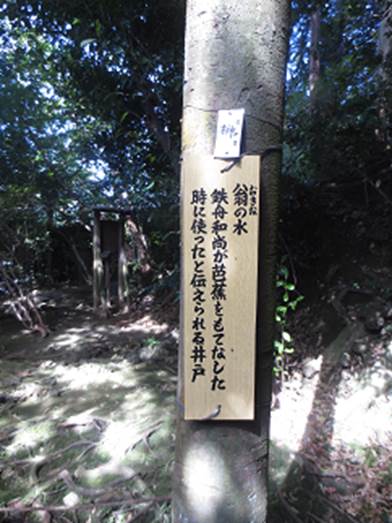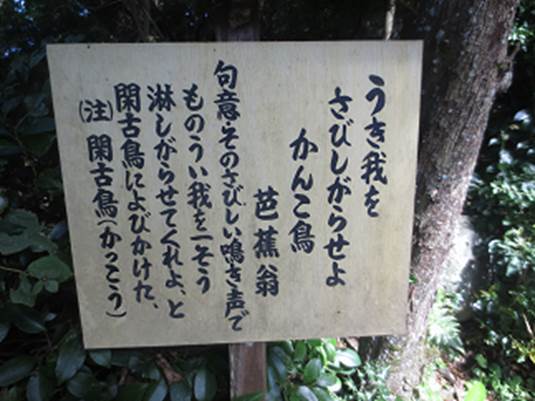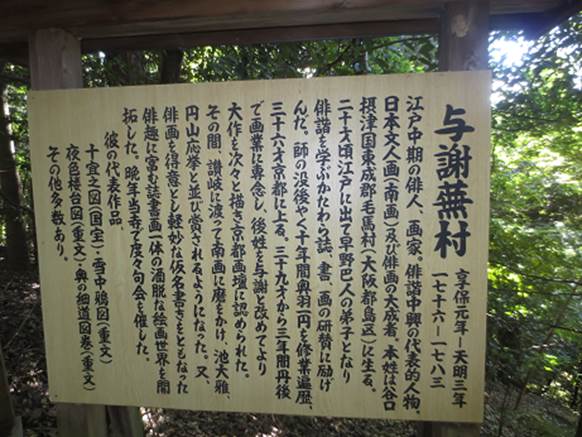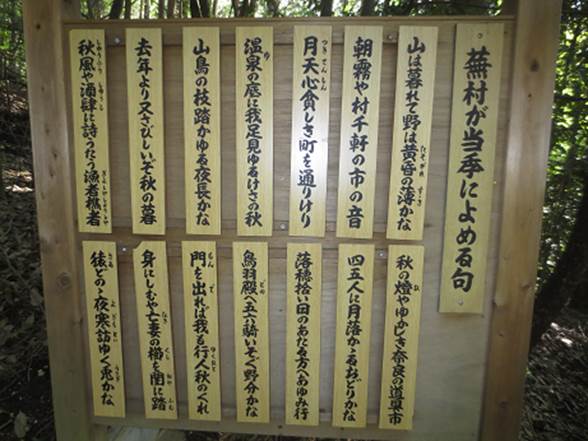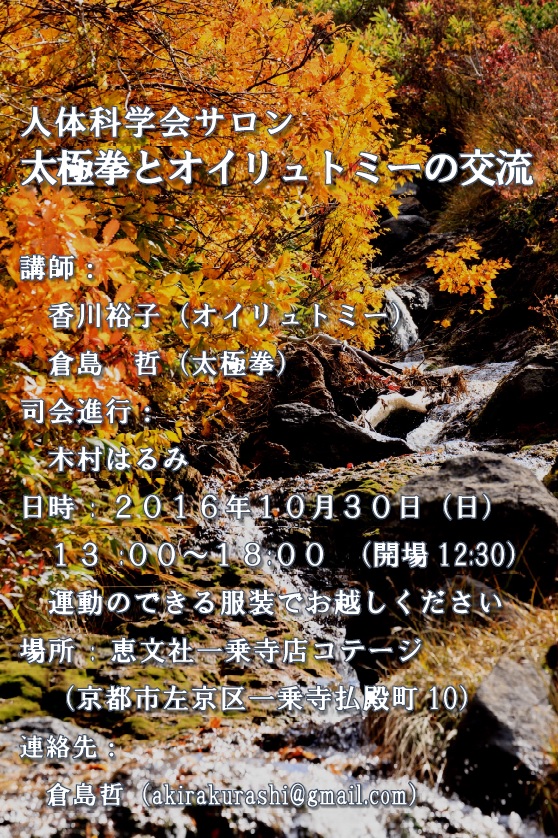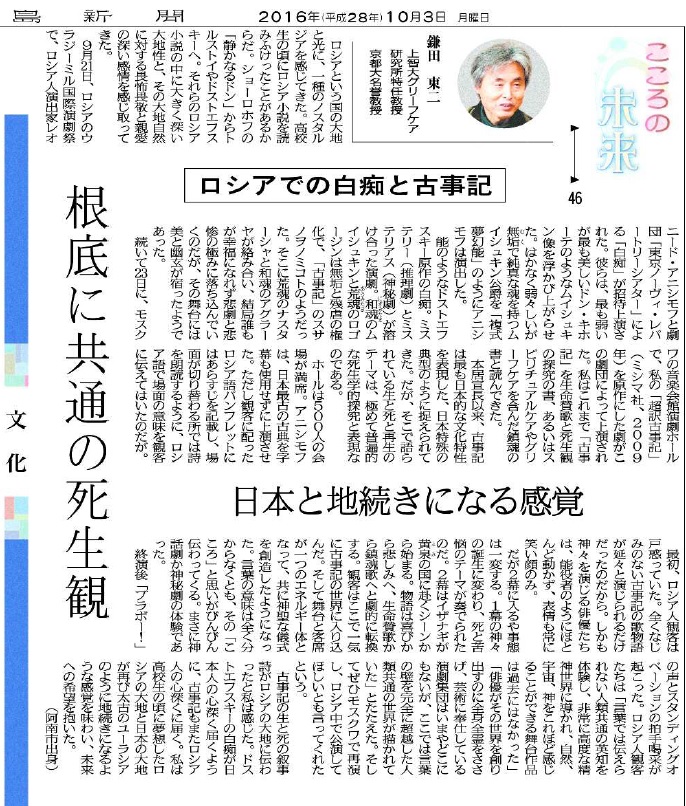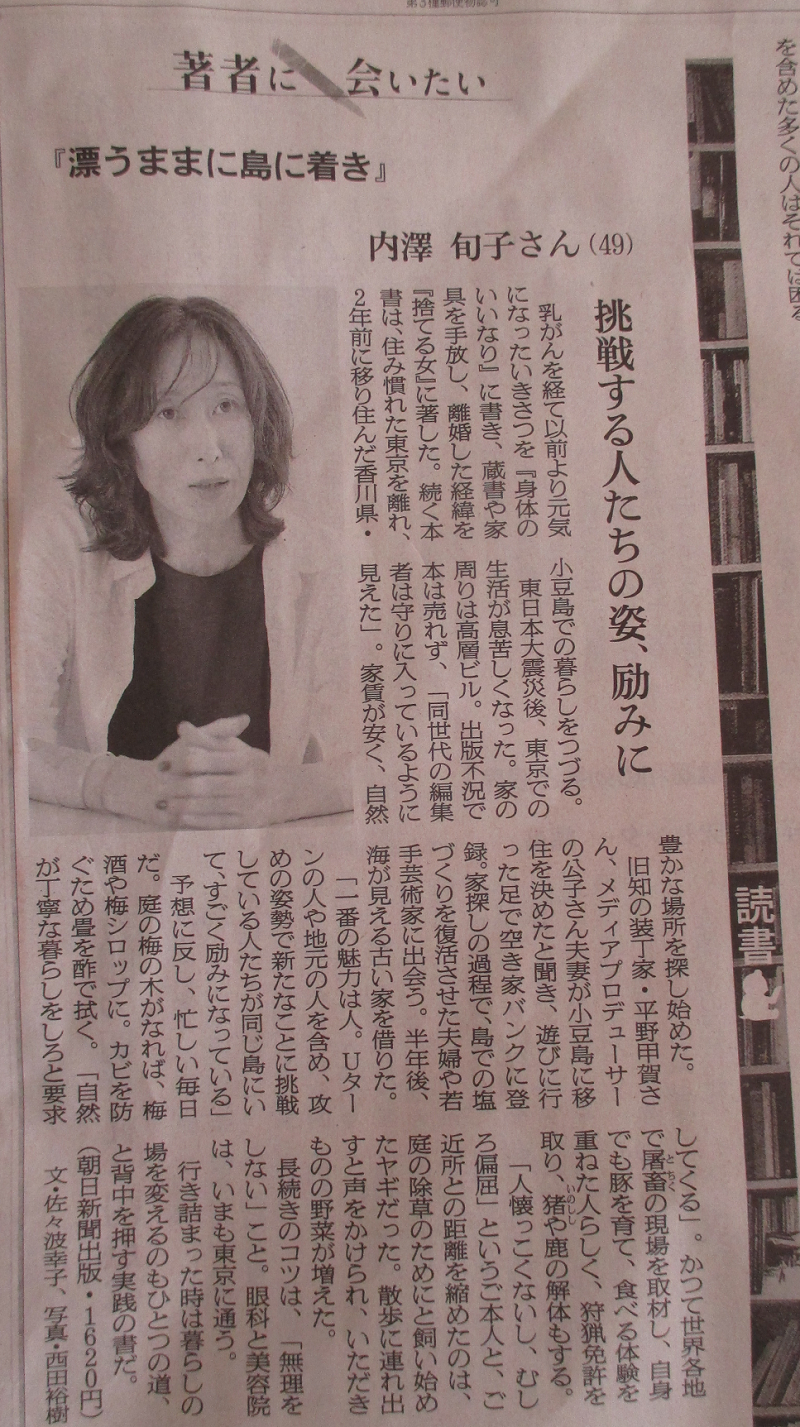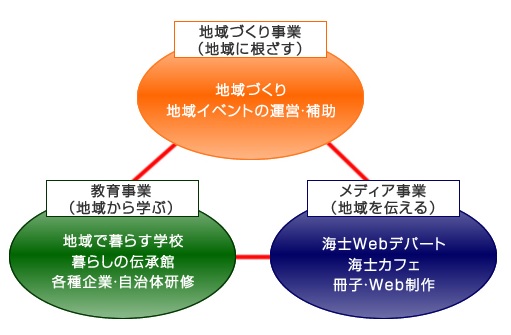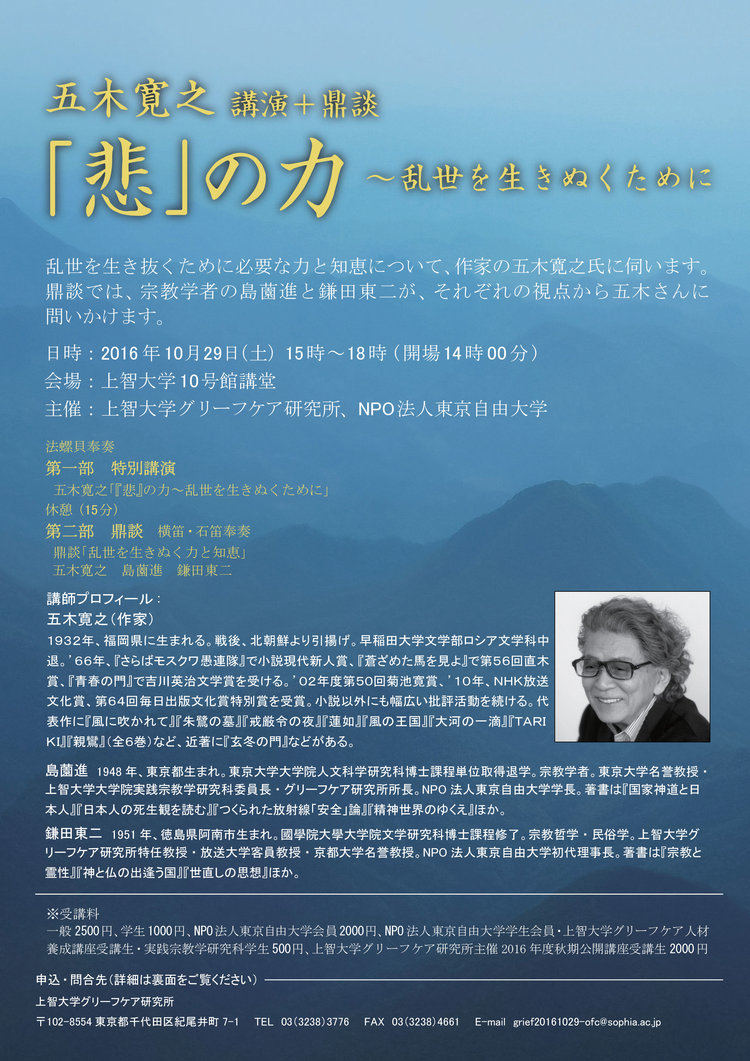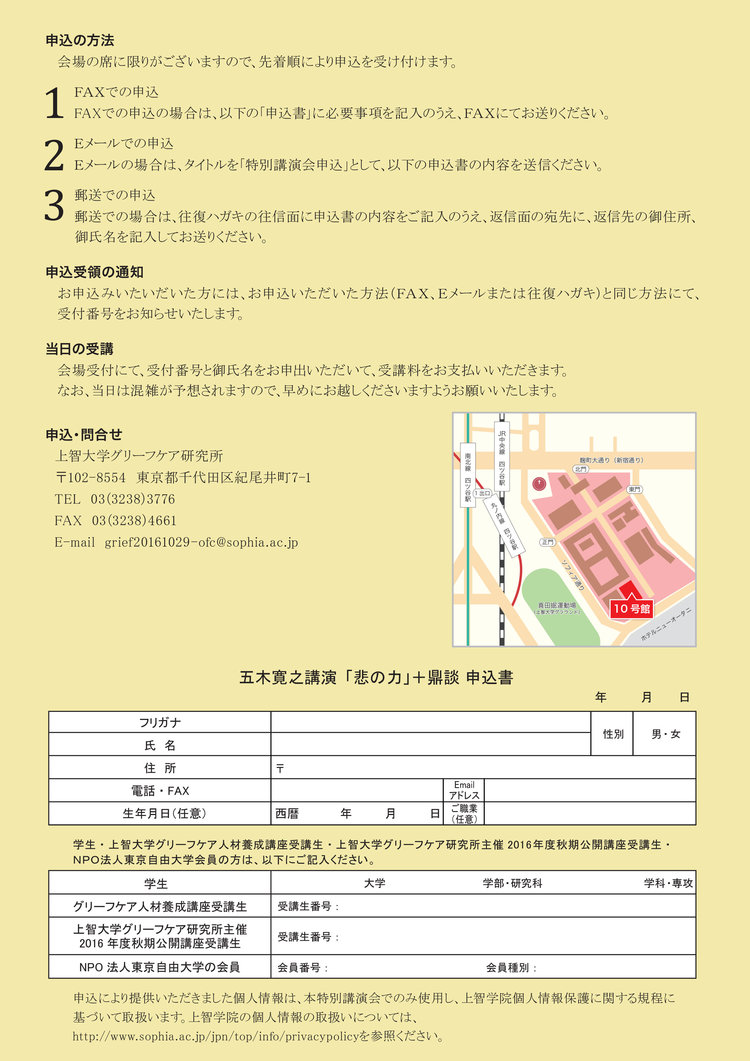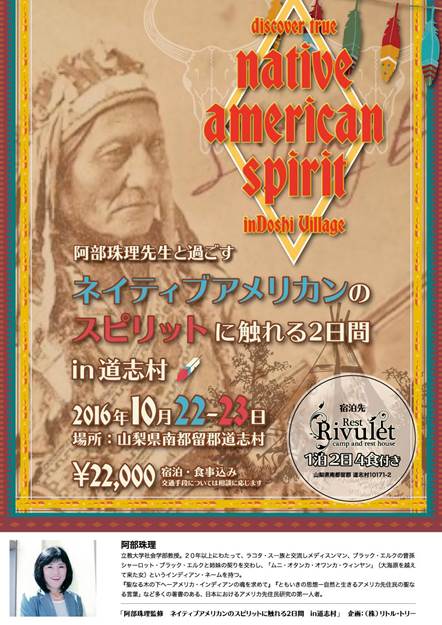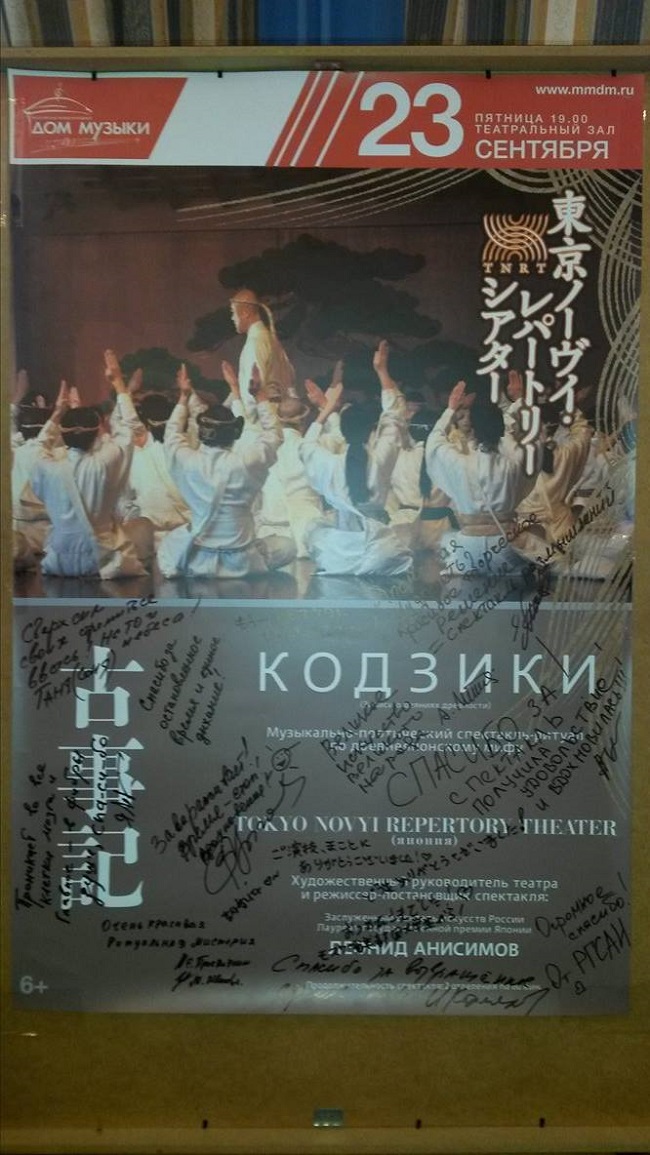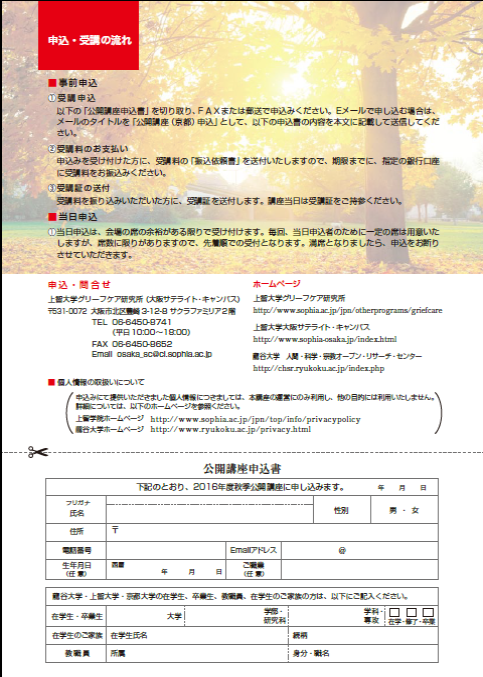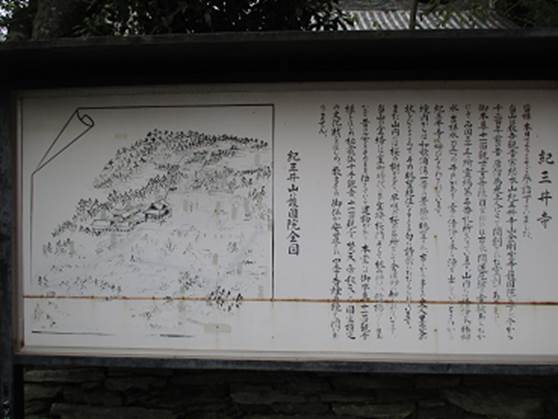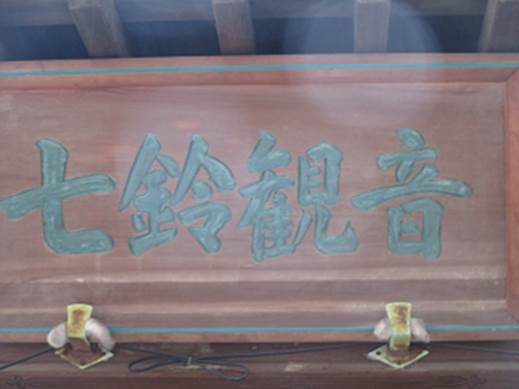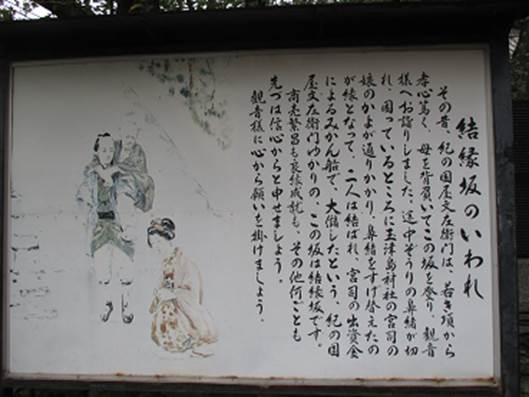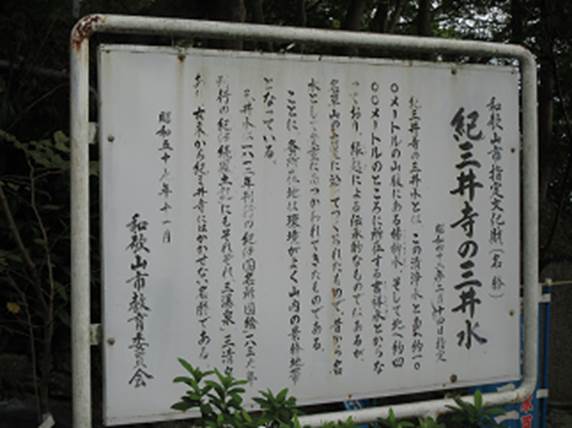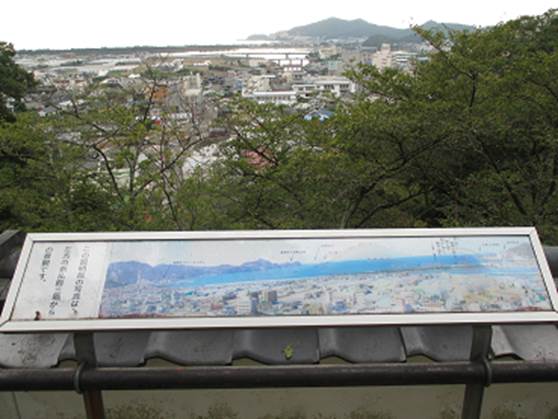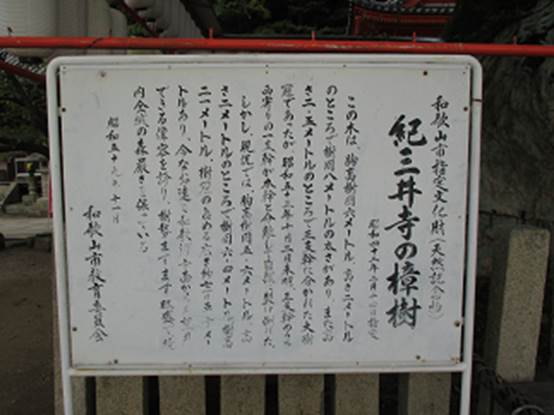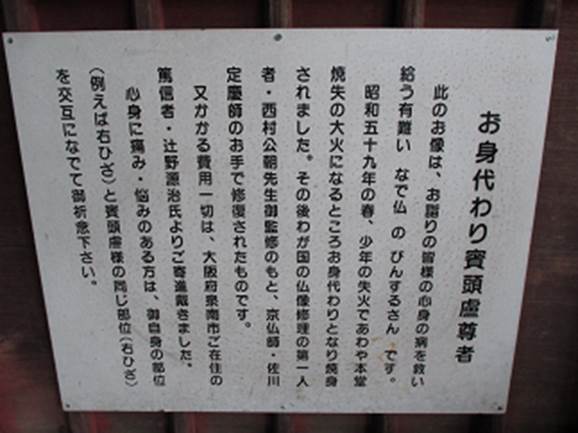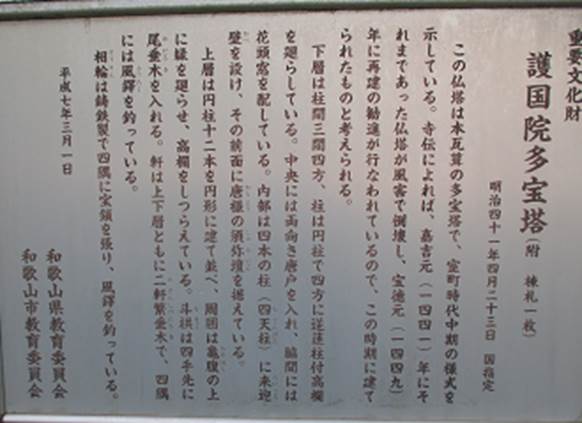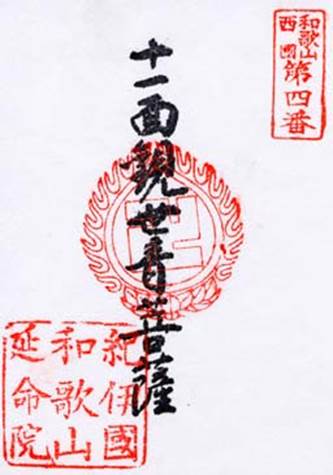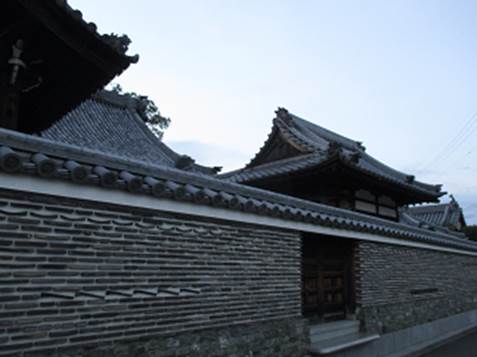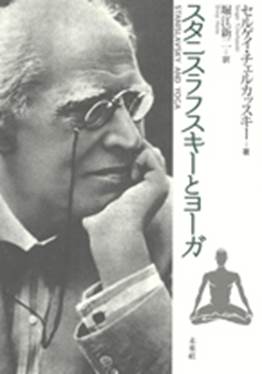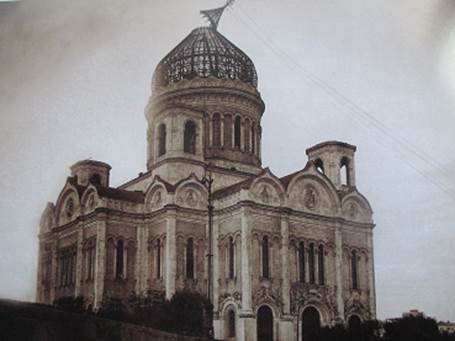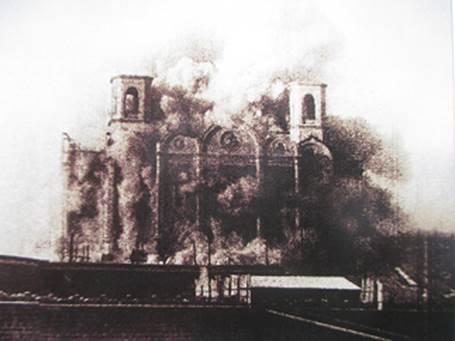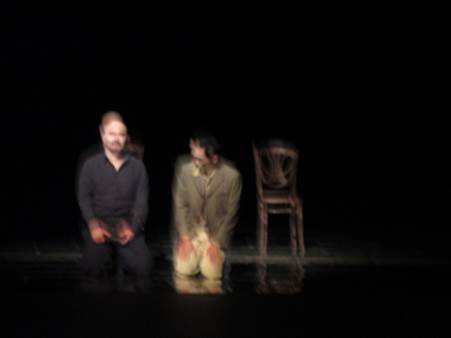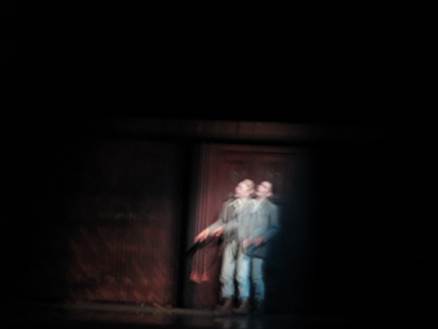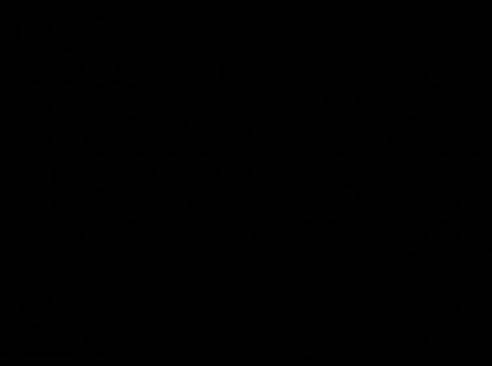�@
�g�n�l�d�@�ڎ�2�@�@������
2016�N10��30���@�Ï銰���F���v�����̑��@�@���ڎ�2
��Ηl
�����̓d�g�H���g���ċ��k�ł����A���S�ɂ��������āA���v���̘b�������Ă��������܂��B
���v���ł́A������i���j�̂���{�V�Y�Ƃ����Ƃ���ŁA�������߂����܂����B
����ȑO�́A���i�Ǖ����Ő��܂�܂����B����ɂ���ȑO�́A���e�͋v���āA�}��̂������
�o�ŁA�����͌����ߗ��ō��𐬂��A����͏����ł������A�ǂ�������v�����āA��̓���
�ĂĂ���悤���Ƃ����̂ŁA����Ă��܂����B���Ƃ́A���i�Ǖ��ł����v���ł������ł����̂ŁA
������ꎟ�Y�ƂƂ͖����́A�n�ɑ��̕t���Ȃ��炿�������܂����B���w�Z�܂ŁA�j���܂���ł����B
�F�l�̉Ƃ́A�_�ƂƋ��ƂƂ��̑��̌��Ƃ����������悤�Ɏv���܂��B�������l�͌�������������
������܂���B�R�͉��[���̂ł����A�F�͂��܂���B���Ǝ������āA���v���ɂ͐l�Q���A��2���A��
�Q���A�Ƃ���������������܂��B
���v���͉��v�������܂����̂ŁA�F���˂̂����Ō��ɂȂ����悤�ł��B�����I�ɂ́A�������Ƃ�
�Ⴂ�A���B���ł��B�n�u�����܂���B
�Ƃ���������ŁA����җ]���҂ł����̂ŁA���܂������Ƃ�����A�ւ邱�Ƃ��p���邱�Ƃ��ł����A
���S�ł������Ȃ�����ł��B
�������������ʒu���A�e���c�̓���������߂āA�����܂Ƃ߂Ă݂����Ǝv���Ă���܂��B
�F���܂ɂ́A�����Ŏ��炵�܂����B
�Ï銰��
���ڎ�2
2016�N10��30���@����T�FRe�F�������������F�b���@�@���ڎ�2
�Ï�搶
�u���O�ŏЉ��������Ƃ̂��ƁA���h�ł��B
��ւ���͌����Ɣ_�Ƃ̑g�ݍ��킹�̎��H�ł������A�������̋������������̃����o�[�������Ǝ�̑g�ݍ��킹�����H���Ă��邩�A���邢�͎�Ƌ��ێ��҂ł��B
����A��̐��Ƃ����ɓ�������̂ł͂Ȃ��_��Ȑ��ƕ����̂Ȃ��Ō���������l�������Ă����A���ꂪ�����Ɋҗ������Ƃ��낢��Ɩʔ����Ȃ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B
�Ƃ���ŒÏ�搶�͉��v���̂ǂ̂�����̂��o�g�ł����H��������܂��B
���
���ڎ�2
2016�N10��30���@�Ï銰���FRe�F�������������F�b���@�@���ڎ�2
��Ηl
�F����
��Ɩ쐶�b���̗��ʂɊւ��錤����̂��ē��A���肪�Ƃ��������܂��B
�����̃j���[�X�ł�����Ă��܂������A�F�⎭�⒖���A�l�Ԃ̐������A�s�s�ɂ܂�
�o�v����悤�ɂȂ��Ă���A�^�C�g���ǂ���A��������L����̂���e�[�}�ł����
�v���܂��B�b�������ʂ���悤�ȃR�[�X���ł���ƁA�H�����̌p���ɂȂ�܂����A
�������������������ƁA�e�ɂ��ƍ߂������͑����邩������܂���B
�N�O���̂悤�ȉf��̃��A���e�B���A�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���v���ł���ɂȂ�Ǝ����Z��n�ɂ���Ă��āA�����҂ւ̎��Q�͕����炢�ł����A
�_�앨��ыƂɂ́A�܂��ʂ̊Q������̂ł́A�Ǝv���܂��B
��ւ���̃R�����ƍ��킹�āA�_�Ƃ�ыƂ��̌��Ƃ������Ă����Ƃ����悤��
�C�����܂��B
�����ւ��[�����̂ł��̂ŁA���̃u���O�i�u�Ï銰���̓k�R���v�K��҂͋ɏ��j
�ł��A�Љ���Ă��������܂��B
���肪�Ƃ��������܂����B
�Ï銰��
���ڎ�2
2016�N10��30���@����T�F�������������F�b���@�@���ڎ�2
�Ï�搶�A
���j���́A�g�S�ϗe�Z�@������ł����b�ɂȂ�A���肪�Ƃ��������܂����B
���e��̐ȂŘb��ɂȂ�܂����쐶�b���ɂ��Ă̌�����͈ȉ��̂��̂ł��B
����10���ɗ����グ�܂����B
�u�����݂�������̐V�W�J�\�\�쐶�b���̗��ʂƐH�������߂��鉞�p�l�ފw�I�����v
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/project/iurp/16jrw012
���낢��A�ʔ�������������ł��ł��Ă����\��ł��̂ŁA���s���������Ђ��Q��������������Ǝv���܂��B
���
���ڎ�2
2016�N10��28���@�Ï銰���F��������@�@���ڎ�2
���c�搶
�e��
�{���́A�i��̑��������������A����ׂ�Ȃ���A�ǂ��ɂ��������Ƃ�܂����B
�ҏW�A���Ȃ��悤�Ƃ��v�����̂ł����A���̂܂܂̂ق����A�Տꊴ�����邩�ȂƎv���A
�Ƃ���Ƃ���̎������p�̂���ŁA���ǂ݂���������K���ł��B
����l���A�����Ȃ�܂����A���ڒʂ����������B
��
��������������������
52��g�S�ϗe�Z�@������2016�N10��28��
�P�j��֑��i���m��w���~�������Z���^�[��������E�������E�@���w�j
�u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v
�����̍ŋ߂̓����A�̋V��I�ȑ��ʂ�����
���ʓ����̑��ʁv�O�I���H�̑��ʁA�S�̎����������ł͂Ȃ��A�ӂ�܂����u��v�i�i�����j��y�j
�E�q�A�扤�́u��v���w��Ő������琧���B�`����`��ᔻ���A�Љ�I�E�S���I�E�F���_�I�Ӌ`�����T���B
�u�Ȃ����߂ė�ɕ����m�ƈׂ��v
�u���l�v�����
�u��������v����u��v�ցi�Ӌ`�A�@�\��₢�����j
���Ȃ鑭�A�����瑭�ւƗ�T�O���g�������̂���1��
�V��̓����@�\�A����̒[�X�Ɂi�t�B���K���b�g�w�E�q�\�\���Ƃ��Ă̐����ҁx�j
�u��v�Ɓu�y�v
���E�́A��y�̕���A���l�͗�y�ɂ���ċS�_�ƓV���̖����y���܂���
�p�t�H�[�}���X�Ŗ��ӎ����ɁA�ڕ��Ց��i��������������j
�u��v�̏K���A�g�̓I�ȏK�n�ɂ��B
�N�q�͏K�ЂĂ���ɏn���A�ق��Ă��������B���Ɍ���̋y�ԏ��Ȃ���B
�����p�A�|�\�A�E�l�|�ɒʂ���
�א��҂̗炩��A�m��v�i�m���l�j�̗�ցA����ɂ͏����̗�ցi���̏グ���낵�܂Łj
�u�u��v�͓��{�ɓ����Ă��Ȃ������v�H�����_�Ƃ��Ă̗�͓����Ă���A���A�������{���H
�����h�q�A�F��R��̌o���_�A���ӎ��Ɂi���x��ʂ��āj���ɓ���������B�u��v�I�Ȕ��z�B
�ߐ��̕��m�́A�_�n���痣���̂ɑ��A���m�̋A�_��i�߂�B�u��v�ɂ��o�ρB
���I�E�l�I�����̎����\�Ȕz���B�T�X�e�i�r���e�B�B�l��⎩�R���Ȃ����A������R���g���[�����邽�߁A���x���H�v����B
���݂̂`�h�A�������̏�z�肵�āA�s�����p�^�[�������Ă����B
�u�^�v�I�ȁA�u���H�v�I�Ȑl�ԊρA���E�ρA�Љ�ρB
��������H�̐g�S�ϗe
�s���A���H���A�g�S��ϗe������B�ǂ��ϗe�����邩���A�̉ۑ�ݒ�B
��֗����H
�q�̐_�c��ځi���c���s�v��j�A�c��ڂ̊J���ɎQ���B����́u�A�_�v�B�i��ꌩ�́u���܁v�j
�����Q�R�N�A���c���ڏZ�B�u��������_�̉�v�B
�R�����i�_�ƁA���̑��̂���`���j
�Q�T�N�A������ׂ��c�y��������A��ւ���̓��ӌ|�́A�_�y�B�_���T�[����i�}�g�̖����w�o�g�j�A�Q���i�_���A�P���A���A�����|�\�̕��͋C�j�B
�u���납���v�̂Ƃ��ɁA�q���̓D�V�тȂǁB
���n��̃p�t�H�[�}���X�A�����m���`�Ƃ��Č��o���镑��i�p��́H�j�A�ϗ����A�����������A�B
�b�e�@�O���l�������g���邩�ǂ����A�ɂ���āA�R�~�b�g�̎d�����킩��B
�ӂ�܂��ɂ���āA�����͂�������B
�Ï�u���x�ɂ���āA�Ƃ������_�B�u���v�Ƃ������[���b�p�l�v
��ցu�u���v�́A�t�B�������b�g�̃��[���b�p�l�ɑ������B�v
��u��ւ���Ƃ́A�g�S�ϗe�w�̑O�A���U�w�A���m�w�ȗ��ł��B�̂͏�c�H���Ȃǂ������B���̌�Ȃ��A�c�y�I�ȕ����ɂ������̂��B�v
��ցu�������̂̂��ƁA���̒��߁B�c�y�����������B��c�H���̌��t�̌�������A�F��R�ɍs�����B�s�א��s�I�Ȍ��́A����ł͂Ȃ��A���̍s�ׂɏd�_�B�v
�q���u�I�ȗv�f�����{�ɓ����Ă������B���n�L�s�̌����B��c���q�ɁA���A�W�A�I�ȗv�f�B�I�Ȃ��̂������Ă���B��ɂ́A�Љ�I�Ȃ��̂ƁA��c�Ƃ̂Ȃ�����l������̂ƁA2��ނ�����̂��B�v
��ցu���������Ă���Ǝv���B���n�̋c�_�́A��c���J�����ł͂Ȃ��A���_���ɂ���������Ă���B�v
�q���u�c����J�Ƃ��Ă̗�ɂ��āv
��ցu�F��R�≬���h�q�ɂ����āA�����I�ȗ�ł͂Ȃ��A�I�ȗ�B���l�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ƍl����̂��s�m�A���O�Ƃ܂����������ƍl����̂́A���ł���B�v
�q���u���g�����ǂ����A�J���N�����邩�ǂ����A�́A�Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B�J���N�����邩�ǂ����́A�ʂ̘b�B�����g���邩�ǂ����́A�l�ԎЉ�̍�@�B���Ɍ��ł́A�������ǂ����́A���h�ɂ���ĈقȂ�B�J���~�点�邩�ǂ����A�Ƃ����b�v
��ցu���p�Ƃ́A�ǂ��炩���������́A�Љ�I�Ȃ��́B���C�����[�J�[�́A���G�ɂ́A�~�点���Ȃ��B�V���[�}���̋Z�p���A�Љ�I�ȖB�g�̋Z�@�́A�l��������Ă���B�T�C�L�J�����T�[�`�ƈقȂ�A�^�U�Ƃ͕ʂ̌��B�v
�Ï�u�Љ�Ƒ��E�Ƃ́A�A�����Ă���B�v
�q���u���p�̋����́A�Љ�I�Ȃ��̂ƍl����Ƃ����l�����ɑ��āA�����O�̏�Ńo�g��������Ƃǂ��Ȃ邩�B���p�͎Љ���z���Ă���̂ł͂Ȃ����B�l�Ԃ̑̂͂������������B�g�����͈قȂ��Ă���B��������g�̂̎g����������̂ł͂Ȃ����B���E���܂߂��Љ�w���L���ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ï�̈ӌ��͋����[���B�����̑��E�͌����̊������̉����ł͂Ȃ����B�v
��ցu�����O�̏��������ƁA�ɂ�鏟�s�B�^���́A�n���Ɩ̊Ԃɂ���A�_�����邩�Ȃ������A�����ł͂Ƃ炦���Ȃ��B�����Ȃ����̂ɑ��ẮA�s�m�_�Ƃ������A���E��F�߂��������B�v
�Ï�u�ߐ���Ƃ́A��@��ʂ��āA�g�S���悢���̂Ɉ�ĂĂ������Ƃ�����Q�̐l�����v
��ցu�L���z�����A���������ɁA��@�����ꂱ������Ă���B�v
�Q���ҁu�̊w��ƁA���H���ɂ��āB�������Y�}�̎ĕ]���v�v
��ցu���Y�}�̎ĕ]���́A�����ē����̎��݁B���{�ł́A�ʂ̎�Ƃ��A�w�Ɨ�x��p���č�@�����悤�Ƃ��Ă����B�_�����v
��u�E�q���̕����d�����Ă���B����͎I���W�i�����A���邢�͓y���@���I�Ȃ��̂Ȃ̂��B���Ə���̊W�ɂ��āA��w�ɂ����Ăǂ���ʂ���Ă��邩�B�����t�B�[���h�Ƃ��Ă���A�t���J�ł��A�T�o���i�ƐX�ł́A�قȂ�B����̌�����X�ł́A�����d�v�B�v
��ցu������B���������Ƃ��ɁA�܂������łāA���ꂪ�g�̂̓����ɂȂ�B�|�\�d���ɂ��ẮA���ՓI�Ȏv�z�ł͂Ȃ����B�}�����镶���Ƒ厖�ɂ��镶��������B�v
��u�I���O�̖{�B��w���m���o�[�o���Ȃ��̂��Ɏc�������߁A��w�Ɏ�荞�܂ꂽ���̂ƁA���������̂�����̂ł͂Ȃ����B���̗쐫�͂ǂ��Ȃ����̂��v
��ցu�����Ƃ̃����N�̂������Ɏ̓��F������B���Ƃ��A�\���炩�ǂ����A��Ƃł��c�_������B���������Ă����o�C�A�X������A�m���o�[�o���Ȃ��̂����̂܂ܑ厖�ɂ���F��R�Ȃǂ͗�O�B���t�ɂȂ�Ȃ����̂��d���B�v
�q���u�c��ڂ�c�y�ɂ��āB�_���T�[���Ă�ŗx���Ă��炤�̂́A������ƈႤ�̂ł͂Ȃ����B���R�����I�ɐ��܂ꂽ���̂Ƃ͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����B���q�̈ӌ��ɂ��A���{�̌|�\�═�p�͔_��Ƃɍ����������́B�v
��ցu�_���T�[�́A�_��Ƃ��ꏏ�ɂ���Ă���ЂƂ����B���S�͓����B����̗x��Ƃ́A�قȂ�B����ɖO�����l�����v
����������
�Ï�܂Ƃ߁u�s���Ȃǂ���A�_�������Ƃ��A�������ĕʂ̋��n���J�����ƂɂȂ������Ƃ���A�s���͉����Ƃ����邩������Ȃ��v
�Q�j����T���i�����O�����w���C�u�t�E�l�ފw�j
�u�A�t���J�C�����ƃA�t���J�o��\�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�V�p�v
���P�A���Ԑl�ފw����݂��g�S�ϗe�Z�@�\�\�A�t���J����̎�ɒ��ڂ���
���Q�A�A�t���J�ɂ����钷���t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe
�w���͋��s��w�_�w���i�y��w�j�A�o��
�X�s���`���A���w�A�u�Ⴑ�̖����炽���邼���v
�A�t���J�̎���́A�s�O�~�[��80�����炢�c���āA������̎��H���Ă���B
�������u�����I�����v������B
�A�t���J�̓����A�ŋ߂͈����Ȃ����B
�P�O���ԃu�b�V���o���ɏ��i�g�S�ϗe�j
�M�щJ�тł̃t�B�[���h���[�N
�P�A�̂�A�߂�A�l��A�B��A�̐���
�Q�A��ޖL�x�ȐH��
�R�A�l�������l�X
�S�A�����ǁi�}�����A�j�i�g�S�ϗe�j
�ٕ����ɐG��邱�Ƃɂ��A�g�S�ϗe
����I�Ȑ��Ǝ��H�̂Ȃ��̐g�S�ϗe�v
��ɂ�����g�S�ϗe�i�_�k�Ƃ̔�r�j�E�E�E�c�y
���^�����Ƃ����T�O
So�i�o�J��j
Tit�i�o�N�E�F����j
��A���݂��A����so�A���݂��Ȃ��A����so�ł͂Ȃ�
�w�r�͒����ɎE�����i�H�p�ɂȂ�Ȃ��H�j
�ƃl�Y�~�͎E�����H�ׂȂ�
�T�X���C�A���A��Q�A�l�Ԃ�������
�~�c�o�`�͖I�̑����ƁA�H�ׂ�
���J�f�A�f��ł͐G��Ȃ��A�E���Ɩڂ̕a�C�ɂȂ�A�������瓦�����B��p�t�́A���J�f���g�҂Ƃ��Ďg���B
�J�����I���́A�E�����ɗV��
�H�ׂ邩�H�ׂȂ����B�H�̃^�u�[�B
��̕��@�i�e�A���A�Ȃǁj
�]�E�A�S�����̗�
�_�k���Ǝ��
�o�J���ɂ́A�S�����ׂ̍������ނ�����B
�u�l�ԃS�����v�E�E�E�O���̓S���������A���g�͐l�ԁB�l�Ԃ��S�����ɐ��܂�ς��A�l�ԂƃS���������݂ɕϑԂ���B
�ϐg�̔\�͂́A���l�ɂ͂킩��Ȃ��B
����ɁA�S�����ɕϐg���邱�Ƃ�����B
�S�����͐l�ԂɎ��Ă��邩�炩�H
�_�k���Ǝ�̏W���́A�݂��������W�Q���悤�Ƃ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��A�����l�ԁi�l�ԃS�����A�l�ԃ]�E�j�̊W�ŗ�������B
�A�t���J�C�����A�X�ɒʂ����ݕω�������A�������ώ@����A�l�Ԃ̏�������m��A���ĂȂ��
�A�t���J�o��A�����u����v�o��A����A������A1960�A70�N��ɍ��������̊w�p�����A�މ@���o��
�L���O���i�o�~�i���n��ʼnr�ށj�A�G��i��A���t�A�Ă����A�}���S�[�Ȃǁj
�o�J�ꎫ�T�A�����ۑ�
�]�E�̖����A
���̐��̎x�z�҂��A���������X�ɓ��邱�Ƃ��֎~�����B
�Z�@�A�ӎ��I�A���ӎ��I�i�����Ă��邱�ƂŁA�˂ɕϗe����j
����A�����
�l�Ԃ������Ɂi�t�j�Ȃ�Ƃ������ƁA���m���l�ԂɁi�t�j�Ȃ邱��
�g�̂��_�炩���l���������͂�������
�q���u����͉�����g�����v
��u�t�����X��A�p��A�o�J��A�ȂǁA�܂������Ⴄ�B�b�҂̏Z�܂��́A�����I�ɂ͉����Ȃ��B�v
�q���u�������̂��̂��g�S�ϗe�Z�@�B�����Ƃ���b���Ȃ��Ƃ����B���Ƃ������B������A�Z�@�����W���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��p�t���A�ŏ��̐��Ƃł͂Ȃ����B�����ł́A�������A�q���ɋ�����̂��A�g�̋Z�@�ɂȂ邩�v
��u��p�t���A��ʐl�Ɠ������Ƃ��s���B�閧�ł͂Ȃ��A�����I�ɂȂ�ɂ����B�Z�@�Ƃ������Ƃ���������̂́A���Ƃɂ���߂Ƃ��Ă����v���Z�X�ŏo�Ă���̂ł͂Ȃ����B�Z�@�Ƃ��ĈВ���K�v������̂��B�v
�q���u�C���́A�o�R�قNjꂵ���͂Ȃ��v
��ցu�ݕ��o�ςɊ������܂�āA���ł̎�����Ă���̂́A�ǂ������Ӗ�������̂��B�ǂ����ǂ��ς�����ƌ���Ă��邩�v
��u��̏W�̕����͌����Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ�Ȃ��B���̓^�N�V�[�̉^�]��ŁA���Ɏ������A�ȂǁB���̈Ӗ��́A�X�̂��̂����낢��H�ׂ����B�܂��킭�킭���邩��B�y��������B�A�C�f���e�B�e�B�Ɋւ�邩�B�ς�������Ƃɂ��āA��Z�����i��ŁA�x�肪�Ȃ��Ȃ����B�v
��ցu�x�肪�Ȃ��Ȃ����̗��R�́v
��u�o�[���ł��āA��҂������Ŋy���ނ悤�ɂȂ����B�v
�Ï�u����̗x��Ɣ_�k���̗x��B���ۑ��̎��݁B�Ȃǁv
��u�J�Z�b�g�e�[�v�̉��y�ŁA�x���Ă���B�x�肪�D���ȏ��N�A��@���Ăł��x��B�_�k���͂�����ėx��B
����͂���݂����ėx��B���Ƃɂ���Ă��܂��܂ȓ���������B���ۑ��ɂ��ẮA�哱�I�Ȃ̂́A�m�f�n�ȂǁB�o�J��͏��ł̊�@�ɂ͓����Ă��Ȃ��A�~�b�V�����Ƃ��Ă̎������B�v
���u�s�O�~�[���A�����̋�ʂ�����B�E���A�H�ׂ�A�E���Ȃ��A�H�ׂȂ��A�ȂǁB�E�����H�ׂȂ��A���V�̂��߂̂��Ƃ͂��邩�v
��u���V��ʂ����܂�Ȃ��B�l�g�䋟�����Ƃ��Ă͂���B�s���s���҂́A�����Ƌ^���邱�Ƃ�����v
����������
�Ï�܂Ƃ߁u���̎��R�������U�����Ęa�̂���邪�A���̊댯�͂قڂȂ��B���̊댯�̂���Ƃ���ł̏C���Ǝ��s�͑f���炵���v
���ڎ�2
2016�N10��28���@����T�FRe�F�S����̌���@�@���ڎ�2
�҂��܁A�݂Ȃ��܁A
���傤�͌�����肪�Ƃ��������܂����B
�҂���A�킩��₷���܂Ƃ߂����肪�Ƃ��������܂��B
�ق����\�ł������A���I�Ɍ����������Ƃ͌������̂ł悩�����ł��B
���������A�c�_�̗ւɉ����Ă��������܂����炤�ꂵ���ł��B
���ƁA���Ńv�����g�A�E�g�ƃR�s�[���ł��Ȃ�����������Y�t�ő���܂��B
�������������B
���
������T�u�M�уA�t���J�ōΎ��L��ǂށv �ipdf 554KB�j
������T�u�͓��̊�Ől�ފw����v �ipdf 244KB�j
���ڎ�2
2016�N10��28���@�ҐM�s�F�S����̌���@�@���ڎ�2
�g�S�ϗe�Z�@������݂̂Ȃ���
�����́B
������w��w�@�̒ҐM�s�ł��B
�{���J�Â���܂�����q��w�l�c�J�L�����p�X�ł�
������ł́A��ϋM�d�Ȋw�т������Ē����܂����B
�i��߂�ꂽ�Ï�搶�A���\�҂̈�ւ���A�����A
�Q���҂݂̂Ȃ��܁A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
���͕��ׂ��Ђ��Ă���A�����͌ܖ؊��V�u���̑����i��߂邽�߁A
�����͑��߂Ɏ��炳���Ē����܂����B�\����܂���B
���āA�����قǓ������R��w�̃��[�����O���X�g�ɁA
�����̍u���̌��ƍ����̌�����̕𑗂�܂����Ƃ���A
���c�搶���A�����g�S�ϗe�Z�@������̃��[�����O���X�g�ɂ�
�����肷��悤�ɂƂ��Ԏ�������܂����B
�������A���͂̕��܂�ɊȒP�ŁA����ςɂӂ������\���ł��̂ŁA
�݂Ȃ��܂ɂ����f�������邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
���������c�搶�́A���������w�ŊJ�Â��ꂽ���c�搶��
���u���̕L���������Ă����肷��悤�ɂƋ��܂����B
��������ƂĂ����̂���\�����܂݂܂����A
�ł�H���ΎM�܂łƐ\���܂��̂ŁA�����̕��䂩���э~���C������
�����肢�����܂��B��ϐ\�������܂���B
http://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/hakumon/2016_04/pdf/2016_04_17.pdf?1477662964259
-------------------
�����͋{�R����ƈꏏ�ɏ�q��w��
�g�S�ϗe�Z�@������ɎQ�����ĎQ��܂����B
���\�҂͂Q�l�ŁA��֑���́u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v�ƁA
����T����́u�w�A�t���J�C�����x�Ɓw�A�t���J�o��x
�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v�ł����B
���c�搶������������Ȃ����Ƃ������Ă��A
�����l���ł̃X�^�[�g�ƂȂ�܂����B

��ւ���̔��\���f���āA���c�搶���u�E�q�̓V���[�}�����I�v��
���������Ӗ������������ł��܂����B
�E�q�����߂����Ƃ����u��v�́A���݂̓��{��̈Ӗ���肸���ƍL���A
���J�V��I�ȗv�f�𑽕��Ɋ܂̂ł��ˁB


��ւ���͔��\�̌㔼�ŁA�ߔN�����g�����g��ł���������
�c�A����c�y�ɂ��Ă��f���������ďЉ�A
�g�̃��x���Ō�����[�������邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ⴂ�܂����B
���^�����̎��Ԃɂ́A�i��̒Ï�搶�Ɠr������Q�����ꂽ
�Љ�w�҂̑q���N�搶�Ƃ��������c�_���X�������O�ł����B
�Ï�搶���A
�u�Љ�Ƒ��E�Ƃ̋����́A�e�Љ�ɂ���ĈقȂ�B
���E�̃��A���e�B�[�����ꂼ��قȂ邵�A���E�ɂ����h������B
�Љ�w�ł����E�������ė~�����v
�Ɣ��������̂ɑ��A
�q���搶�́A
�u�����ł͂�����R�₵�Ă��̐��ɑ���B��������R�₹�ΔR�₷�قǗǂ��Ƃ����B
��������Đ��m�l�͂��������ƌ������B���̐��ō��͕����ł���ƁB
�����ł͂��̐���������`�I�ŁA����Ȃ͎Љ�w�ł������Ɉ����邾�낤�v
�Ɖ����܂��B
���������Ï�搶�́A
�u���̐��Ǝ��Ă��鑼�E�͎Љ�w�ň����₷���Ƃ����͕̂����邪�A
���E�����l�ł����āA������`�I�Ȃ��̂������łȂ����̂�����v
�Ɠ����܂����B
�x�e������Ō㔼�͑����̔��\�ł��B
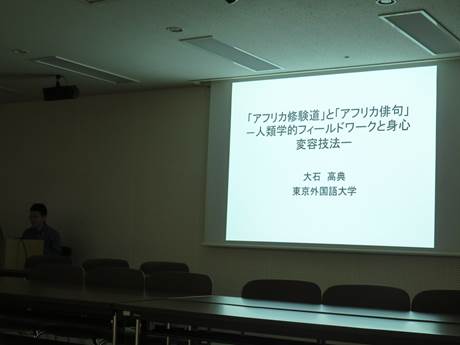
�u�A�t���J�C�����v�u�A�t���J�o��v�Ƃ́A�Ȃ�Ƌ����[���^�C�g���ł��傤�B
�����̔��\�ł́A���̂Q�̓��e�������܂����B
�@���Ԑl�ފw����݂��g�S�ϗe�Z�@�\�A�t���J����̎�ɒ��ڂ���
�A�A�t���J�ɂ����钷���t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe
�Ƃ��ɃJ�����[���̃o�J���ƃo�N�E�F����������ɂ��b���Ă��������܂����B

�i�E�H�[���[�̂悤�ȕ\��Ŕ��\��������j
�ŏ��ɒ��J�Ȏ��ȏЉ�����Ă��������܂����B
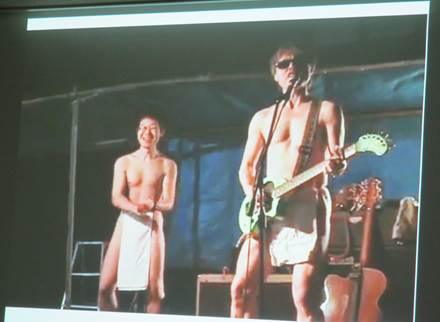
�i���c�搶�̃o�b�N�_���T�[�Ƃ��Ċ��Ă������̑����j

�i�A�t���J��10���ԃo�X�ɏ�����ۂ̊�ʕϗe�ɂ��Ă̕j
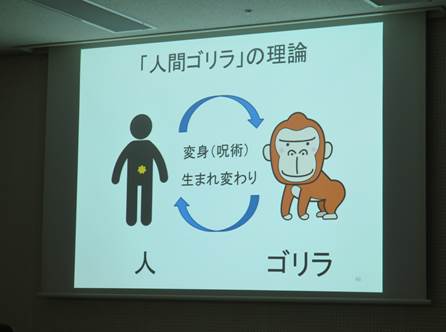
���n�ł́u�l�ԃS�����v�Ƃ������݂��M�����Ă��邻���ł��B
����́A
�@�l���d�p�Ŏ���ɃS�����ɂȂ�
�A�l�Ԃ��ˑR�ϑԂ��āA�S�����ɂȂ�
�o�X��10���ԏ������̑����̊�́A
�ǂ����Ă��u�l�ԃS�����v�ł����A�ϐg����̂�10���Ԃ��������Ă��܂����̂ŁA
���_��u�l�ԃS�����v�ɂ͊Y�����Ȃ��悤�ł��B
���Ȃ݂ɁA�u�l�ԃ]�E�v�Ƃ������݂����邼���ł��B
�����āA�{���̃e�[�}�ł���u�A�t���J�C�����v�ɂ��ďЉ��܂��B
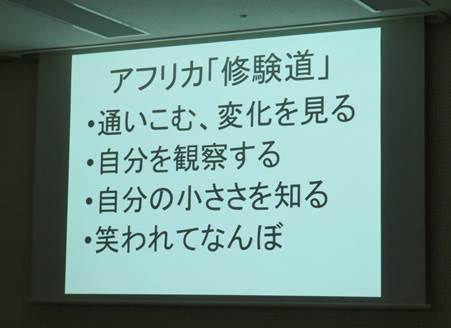
�u�A�t���J�o��v�ɂ��ẮA���ڂ����Љ�Ă��������܂����B
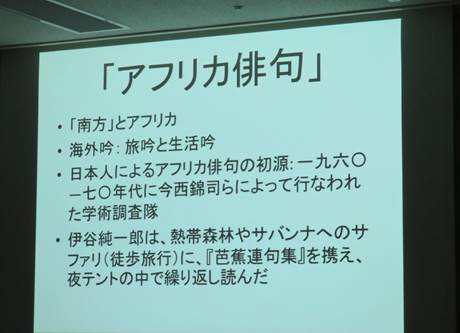
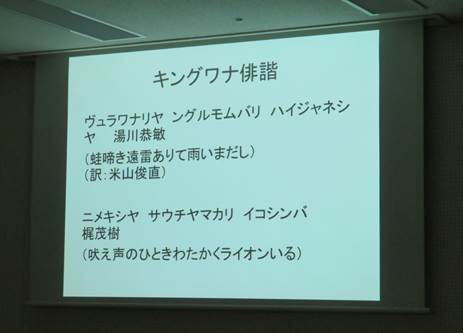
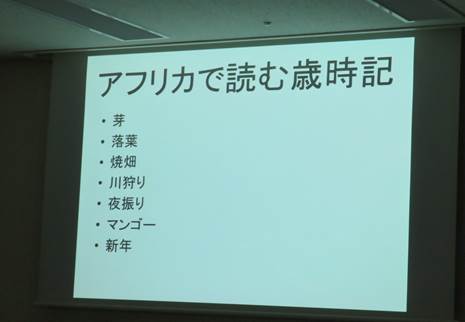
�Ō�ɁA���R�ɂ��銙�c�搶�Ɍ������ă��b�Z�[�W�����܂��B
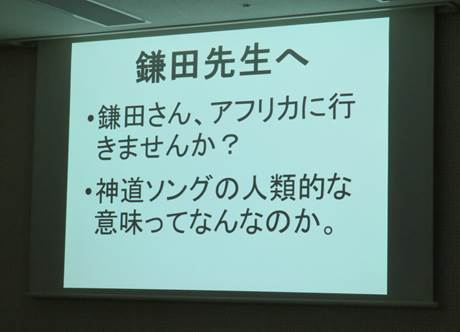
�����́A�u���c�搶�͂܂��A�t���J�֍s�������Ƃ��Ȃ��͂����v�Ǝw�E����܂��B
�Ï�搶�́u�m���ɍs���Ă��Ȃ��Ǝv���B���c�搶�̓A�C�������h��
�M���V���ɂ͍s���Ă���B�Ƃ��ɃM���V���ł̓p���e�m���_�a�ŊJ�������
�X�b�|���|���̑S���ɂȂ����B�ǂ����ĕ߂܂�Ȃ������̂��H�v�Ɩ���N����܂����B
�҂́A�u�X�b�|���|���ɂȂ����̂̓p���e�m���_�a�ł͂Ȃ��A
�I�����|�X�_�a�ł͂Ȃ����B�������Ƀp���e�m���_�a�ł�
�߂܂邾�낤�v�Ɣ������悤���Ǝv���܂������A
�L���Ⴂ�̉\�������邵�A���̏�ŃX�b�|���|���ɂȂ����ꏊ�ɂ���
�Ŏ�����K�v�͂Ȃ��Ɣ��f���A���ق��т��܂����B
�����́A�u���c����ɂ͐_���\���O���C�O�ł��̂��ė~�����v�Ƌ����B
���̔����̗��ɂ́A���c�搶�̃o�b�N�_���T�[�Ƃ��āA���g�����E�f�r���[�����肽����
�������N�̖�������̂��Ɗ����܂����B
�ȏ�A�{���̌�����̕ł����B
�ҐM�s�q
���ڎ�2
2016�N10��26���@���c����FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2
�Ï銰���l
����T�l
��֑��l
�݂Ȃ���
���肪�Ƃ��������܂��B
������͂�낵�����肢���܂��B
�P�O�E�Q�U�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��26���@�Ï銰���FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2
���c�Ȍ��ɂ��Q���̊F����
���j���̏o�Ȃɂ��āA���ꂢ�������̂͂����ւʓ|�ł��̂ŁA���L�̂悤�ɂ����������Ǝv���܂��B
50���51��̖�����A���c�搶���炢�������Ă���܂��B
�ǂ�����o�Ȃ��Ă����Ȃ����ŁA52��̌�����ɂ��o�ȂȂ��肽���A�Ƃ����������A�Ï�܂ł��m�点
���������B��������킹�āA�}���قɂ��m�点���܂��B
�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
�A�h���X�́Atsushiro.hirofumi.ge�A�b�g�}�[�Nu.tsukuba.ac.jp
��\��s�@�Ï銰���i�}�g��w�j
���ڎ�2
2016�N10��24���@�Ï銰���FRe�F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2
�g�S�ϗe�����E���c�Ȍ��ɎQ�������F�l
��\��s�̒Ï�ł��B
���łɂ��ē��̂Ƃ���A10��28���i���j�ɊJ�Â���܂��A��52����́A
��ނȂ����R�ɂ��A��\�̊��c�搶�����Ȃ���A���S�����҂̒Ï邪�㗝��
�i������܂��B
���܂��ẮA���Q���̉\���̂�����i��Η����Ȃ����ȊO�̕����ׂāj�́A
���L�̒Ï�̃A�h���X���ɁA�O���i�ؗj�j�܂łɁA�����O�������ȂǁA���m�点
��������K���ł��B
tsushiro.hirofumi.ge�A�b�g�}�[�Nu.tsukuba.ac.jp
�F�l�̂����́A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
�Ï銰���i�}�g��w�j
���ڎ�2
2016�N10��24���@���c����F10��28���i���j��52��g�S�ϗe�Z�@������ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
10��28���i���j�ɁA��q��w�����}����9�K��c���ő�52��g�S�ϗe�Z�@��������J�Â��܂��B
���Q���A��낵�����肢���܂��B
��52��g�S�ϗe�Z�@������
�����F2016�N10��28���i���j13���`17��30��
�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�XL���فi�����}���فj9�KL-911����
���\�@��֑��i���m��w���~����������������E�������E�@���w�j�u�]�ˎ�w�Ɛg�S�ϗe�Z�@�v
���\�A����T�i�����O�����w���C�u�t�E�l�ފw�j�u�A�t���J�C�����v�Ɓu�A�t���J�o��v�\�l�ފw�I�t�B�[���h���[�N�Ɛg�S�ϗe�Z�@
�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����E�@���N�w�E�����w�j
���͏�q��w�l�J�L�����p�X���̒����}���قȂ̂ŁA����ɍۂ��Ă͓o�^������o���Ă����K�v������܂��B
�Q���҂́A���ʓ|�ł����A���c���Ï銰���}�g��w�����ɂ����������B
����́A�킽�������̑O������X�����R�ɍs���ċ��R���ʎ��̓쒼�ƏZ�E����ƑΒk���Ȃ���Ȃ�܂���̂ŁA���̓��̎i��i�s�Ɠ����̉^�c��I����̋������u�����E�}�v�ł̍��e��̈ē����A�u������\��s�v�Ƃ��ĒÏ銰���}�g��w�����ɂ��肢���Ă���܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B
��ւ���Ƒ����͑O�r�m�X���钧��I�ȎႫ�@���w�҂ł���A�l�s��w�҂ł��B
��{�I�ɁA�e�������\60���{���^�����E�f�B�X�J�b�V����60������2���ԁ~2�ŁA�c�������Ԃ𑍍����_�⎟��̈ē��Ȃǂɓ��Ă܂��B
�Ï邳��A�����A��ւ���A�݂Ȃ���A��낵�����肢�������܂��B
�P�O�E�Q�S�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��23���@���c����F���R�C�����R�V�X�@�@���ڎ�2
2016�N10��23��
�����͓��j���B
�����A�ܓV�B
�J�������������A��������10���ȏ��b�R�o�q�͂ł��Ȃ��̂ŁA�G�C���b�A15���A���R�C�����o���B
��X�_�Зy�q�B
���R�����グ��B

�{���̔�b�R
�ǂ����ȁH
�����ȁH
�֎�@���o���Ă����ƁE�E�E

�֎�@�����
���c��i�H�Ɩ��O�̍g�t�������Ԑi��ł���B
���肵���A���ł͑�w�������Z���������w����B

���c��i�H�Ɩ����w��
��҂����͔M�S�ɖ̐������Ă���B
�����A�H���̍ۂ̍��h���ɂȂ�A���̐����̂悤�ȁB
�m���A�V�Ȃǂɂ�����R�����������H

�{���̙֎�@�ٓV��
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B
���Z�~�i�[�n�E�X����͍����̎Ⴂ���X���B
�_���͓ܓV�̂������A�Â��B
�����o��ƁA�X�̋��N���҂��Ă��Ă����B

�{���̐X�̋��N
����ɂ��́B
���̐�ɂ́E�E�E

�{���̐X�̗d���N
�X�̗d���N�͂ƌ���ƁA���̑O�����ʒu������Ă���B

�{���̐X�̗d���N

�{���̐X�̗d���N
����ȒN�������������H
����Ȃ��Ƃ�����l�����邩�H
���̂��߂ɁH
�ł́A�n�k�ŁH
���ŁH
������������������H
�킩���B
�Ȃ��A�����Ȃ����̂��H
�Y���R�����{�Ȃ�ǂ������H
�Ɛl�́H
�ƍs�̓��@�́H

�{���̉���
�N���H�@�Ȃ��H�@�ƁA�����̏o�ʖ₢��䍂��Ȃ���A���n�̔w�̉����q���B
�����Ԃ�A���ꂪ������悤�ɂȂ��Ă����B
�H���ˁB

�i���͂�̓�
���n�̔w�̃i���͂�̓���`���B
�g�g���͂ǂ��H
���Ȃ��H

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
�g�g���͂��Ȃ����ǁA���̐�ɁA���A�C�N�͂����B
�����āA���A�C�N�Ƃ��e�����X�̂��n���l���B

�{���̐X�̂��n���l
�����I�H
���^���H
���̊i�D���H
������ƕς���Ă邩���H
�X�̗d���N�ɂ������Ȉٕς�����A�X�̂��n���l�ɂ������Ȉٕς��B

�{���̐X�̂��n���l
�m���ɐΓ����ς���Ƃ�킢�B
�N���A���̂��߂ɁH
�Y���R�����{�Ȃ�ǂ������H
�Ɛl�́H
�ƍs���@�́H
�Ɛl���A�ƍs���@���킩��A���̑O�A���߂đ��́u�Z�g��Ёv�ɎQ�q���āA�Ռ������B
���̎Гa�̐v�{�s�҂́A�ǂ̂悤�Ȏv�z�ŁA���̎Гa�Ƌ����̋�ԃf�U�C���������̂��A�ƁB
�悤�킩������B
���̕�����A���{�{�A���{�{�A��O�{�{�Ɓu�Z�g�O�_�v���z�u����Ă���̂ŁA��O����Q�q����ƁA�\���j������O�{�{�A�����j�������{�{�A�ꓛ�j�������{�{�̏��ɎQ�q���Ă������ƂɂȂ�B
�\�E���E��A�Ɛi�s����ɂ�āA�[�݂ɓ����Ă����\���B
���݂̖{�a�͕���7�N�i1810�j�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����B
�����A���̋�Ԕz�u�͂���ȑO����̂��̂̂悤���B
������A���̂悤�ɋ�ԃf�U�C�����Ă���̂��H
�C�U�i�M�m���͉���̍��ł̍ȃC�U�i�~�m�~�R�g�̎����q��ɐG�ꂽ�Ƃ��āA�}���̓����̋k�̏��˂̈��g�̉͂ɓ������S������B
�ƁA���܂��܂Ȑ_�X���������Ă���̂����A
�����ɐ��̒�ɟ��i�����j�����ɁA�����_�̖��́A��ÖȒÐg�i�����킽�݂́j�_�B���ɒꓛ�V�j�i�����̂��́j���B���ɟ������ɁA�����_�̖��́A���ÖȒÐg�_�B���ɒ����V�j���B���̏�ɟ������ɁA�����_�̖��́A��ÖȒÐg�_�B���ɏ㓛�V�j���B���̎O���̖ȒÌ��_�́A���ܘA���i���Â݂̂ނ炶��j�̑c�_�i���₪�݁j�ƈȁi���j���q�i���j���_�Ȃ�B�́i����j�A���ܘA���́A���̖ȒÌ��_�̎q�A�F�s�u�����]�i�����Ђ��Ȃ����́j���̎q���i���݂̂��j�Ȃ�B���̒ꓛ�V�j���A�����V�j���A�㓛�V�j���̎O���̐_�́A�n�]�i���݂̂��j�̎O�O�i�݂܂ցj�̑�_�Ȃ�B���i�w�Î��L�x��g���ɁA32�Łj
�܂�A���̎��A
�@ ����Ő�������ɉ��������_���\�R�c���^�c�~�ƃ\�R�c�c�m��
�A ���قǂ���������ɉ��������_���i�J�c���^�c�~�ƃi�J�c�c�m��
�B ���ʂŐ�������ɉ��������_���E�n�c���^�c�~�ƃE�n�c�c�m��
�ł���B
�����āA���̓��A���^�c�~���C�_�O�_�́A�����̑c��_�ŁA�c�c�m���O�_�́u�n�]�v���Ȃ킿�u�Z�g�v�̎O�_�ł���Ƃ����B
���̌�ɁA�u�O�M�q�v�A���Ȃ킿�A
�@ �A�}�e���X�`�C�U�i�M�̍��ڂ���A���̐_
�A �c�N���~�`�C�U�i�M�̉E�ڂ���A���̐_
�B �X�T�m���`�C�U�i�M�̕@����A�C���̐_
������o���Ɓw�Î��L�x�͋L���̂��B
���́u�Z�g�O�_�v���Z�g��Ђ��J���Ă���̂��B
�������A������A�܂蓌�̕����琼�̕��ɁA��E��E�O�A�ƁB
�c���ɁB
�ӂ��A�t����Ђ��F�������{���A���ꂼ��l�a�A�O�a�̖{�a�Гa�����邪�A���ׂĉ����тŁA���ꂪ��ʂ̌`���ł���B
�����A�Z�g��Ђ͈Ⴄ�B�c���̎O�a�B�����Ƃ���l�{�{�����͑�O�{�{�̉E���ɕ��ĕ���ł��邪�B
����ȁA�c���O�a�̍\���́A�C�̕\�ƒ��ƒ�̗��̓I�Ȑ[�݂̕��ʓI�ȕ\���Ƃ������Ƃ��낤���H
������������Ȃ����A����ɁA���ׂĂ݂�K�v������B
���̂悤�ȋ�Ԕz�u�����ɂ��邩�ǂ����H
���̔Ɛl�T���͂ނ��������B
�Ɛl�T���ƌ����A�h�X�g�G�t�X�L�[�́w�߂Ɣ��x�̎�l���̃��X�R�[���j�R�t�B
�h�X�g�G�t�X�L�[�́A1866�N�A�G���w���V�A��m�x�Ɂw�߂Ɣ��x��A�ڂ��邪�A���̑O�N��1865�N1���ɁA���V�A�����̕����h�����X�R�[���j�L�̃Q���X���E�`�X�g�t��2�l�̘V�������E�Q�����������������Ƃ����B
���̑O�A�ܖ؊��V����Ɖ���āA���̘b�ƂȂ����B
�h�X�g�G�t�X�L�[�́w�߂Ɣ��x�́u���X�R�[���j�R�t�v�́A���̃��V�A���������h�����X�R�[���j�L�ْ̈[���q�Ƃ��Đݒ肳��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ����B
�m���ɁA���X�R�[���j�R�t�́A�u�I�ꂽ��}�l�v���V�炵��������邽�߂ɎЉ�̗ϗ������݉z���Ă��\��Ȃ��Ƃ������ݕs���̓��قȑI���v�z�̎�����ł������B
���X�R�[���j�L�Ƃ́A�����h�Ɩ�邪�A17���I�㔼�Ƀj�R���̉��v�ƌĂ�郍�V�A�����̓T����v�����ꂸ�ɐ�����番��������h�́u�ËV��h�v���w���Ă���B
���̕s�C���Ȉْ[�v�z�̎�����́u�����h���ËV��h�����X�R�[���j�L�v�̒j�u���X�R�[���j�R�t�v���\�R�����̃|���t�B�[���E�y�g���[���B�`�ɒNjy����Ȃ���A��������Ƃ��蔲���Ă悤�Ƃ���W�J�͎��Ɏ�Ɋ�����X�������O�ȓW�J�ł������B
�Ɛl�̖ڐ��͂��Ă���B
�����A������ؖ��ł��Ȃ��B
���̔Ɛl���X�R�[���j�R�t���������̂��A�n�����䂦�ɏ��w�ƂȂ炴������Ȃ������\�t�B���E�Z�~���[�m���i�E�}�������[�h�����Ɓu�\�[�j���v�ł������B
���̃\�t�B�A���A�q�b�q����́A���X�R�[���j�R�t���u�����v�i�H�j�ɖ߂����B
�Ɛl�ɐ[���u�߁v�̈ӎ������N�������B
����͉��ɂ���Ăł����̂��H
�\�t�B�A�Ɛ���̂͂��炫�H
�����Ƃ������邩������A�����}��̌����鑶�݂����Ȃ���Γ�����B
�h�X�g�G�t�X�L�[�̓\�[�j�����Ăяo�����ƂŁA�u�߂Ɣ��v�𐬏A�������B
�ޏ������Ȃ���A�u�ْ[�v�z�v�Ƙ��ݕs���ȁu�ƍ߁v���������c��Ȃ����������m���B
�ǂ����悤���Ȃ��ُ�ƍߎ҃��X�R�[���j�R�t�Ə��w�\�t�B�A�B
����2�̕��̈��͂��u���z�v�ݏo�����B
����ɂ���āA�u�߂Ɣ��v�����A����B
����ɂ��Ă��A�h�X�g�G�t�X�L�[�Ƃ�����������́A�Ƃ�ł��Ȃ��������́`�B
�悤�܂��A����ȉߌ��ȏ����������āA�����ł������B
���炢�������B
�Ƃ�ł��Ȃ���������B
��������������B
�܂˂ł�������B
�Z�g��ЂƓ������炢�Ƃ�ł��Ȃ��V�X�e���B
�h�X�g�G�t�X�L�[�ƏZ�g��Ђɂǂ�ȊW������̂��H
���̊W���Ȃ��Ƃ�������B
�ƂĂ��Ȃ��[���W������Ƃ�������B
�Ȃ��Ȃ�A�h�X�g�G�t�X�L�[�����A�l�Ԑ[�w�S���̎O�w�\���A�u�ꓛ�V�j�E�����V�j�E�㓛�V�j�v��`��������Ƃ�����B
���グ��ƁA��c�c�m���������ɂ����I

�{���̞w��
�j�āA��̒�B
����̒�B
�E���O�����g�̃O�����g�B
���ꋽ�B
�P�[�u���w���߂����X�̒��ŁA��2�����Ζʂ��삯����Ă����̂������B
�����āA�����u�ցB

�������Ɛ���R
��b�R�R���͏��X�ɍg�t���i��ł����B

�����u�̍g�t

�����u�̍g�t
�����u�̂��n���l�̑O�Ŕʎ�S�o�Ɗe��^���B�����ĘZ���q�B

�{���̂����u

�{���̐���R

�{���̔��i��
�匴�̗���]�݁A����R��]�݁A���i��]�ށB
�����āA�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�15��B
������Ƃ��A�ł�Ԃ��̉������Ă���B
���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̉��H��
���H���n��A��X�_�ЎQ�q�B
���q12�q�B
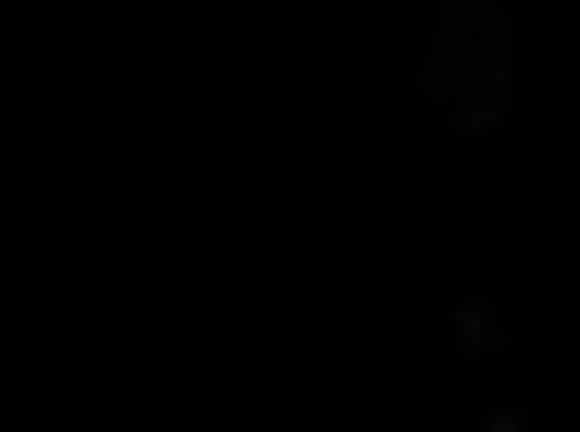
�{���̍�X�_�Ђ̐_��
�{�a�_����]�ށB
���������Ȃ��悤�ł��邪�A�Ɛl�����������ȁE�E�E

�{���̍�X�_�Ђ̎Q��
���́A���̔Ɛl�H
���E�͔Ɛl�ɖ����Ă���B
�����A���ꂪ�ƍ߂ł��邩�ǂ����́A�s�m���ł���B
�Ɛl���ƍߎ҂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�Ɛl�́A�͐l�B
�V�������E��˔j���郂�f���P�[�X�Ƃ��Ȃ�B
�ƍߎ҂Ƃ��Ď��Y�ɏ����ꂽ�\�N���e�X�R��B
�\���ˏ�����ƂȂ����C�G�X�R��B
�s�h�߁E�V�����@�ᔽ�E�����ێ��@�ᔽ�œ�x�ߕ߂��ꂽ�o�����m�O�Y�R��B
�Ɛl���͂������炷�ٗ�̃��f���P�[�X�����̗����ɂ͕K�v�ł͂Ȃ����B
�Z�g��Ђƃ��X�R�[���j�R�t�N�A������肫�B
���ڎ�2
2016�N10��23���@���c����F���R�C�����A�Z�g��ЂƓV�����E�V���E�������@�@���ڎ�2
2016�N10��22��
��q��w���T�e���C�g�L�����p�X�O���[�t�P�A�������Œ���9��������u�@���w�v��2�R�}�̎��Ƃ�������A�����H�����ǂ��T���āA�Z�g��ЎQ�q�B
���̌�A�����O�\�O����5�ԎD���̊��䎛�i�ӂ����ł�j�ɎQ�q�ɍs�����Ǝv�������A�ڑ������܂��s�����A�V�����ɖ߂��āA���v���Ԃ��10��̏I���ɓ���Z���Ă����ʓV�t�̂���u�V���E�v�ɍs���A���\�N�Ԃ肩�ŃR�e�R�e�̑������\�����B
���₠�`�A�Z�������`�B�Z�������`�B
���A�����낷���邺�I
�Z�g��Ђ́A�V��������H�ʓd�Ԃ̍��d�Ԃɏ���Ė�20���B�����O�ʼn��ԁB
�m���ɖڂɒ������B
�����āA���ۋ���
�Z�g��Ђ͓��{�L���̌ÎЂŁA�u���_��Ёv�̊i���������쎮���Ђł���B
��������ɒ�܂���22�В��̒�7�Ђ̒���1�Ђł���B��������Ђł�����B
�n��̏Z�g��Ђ͑S���ɖ�2300�Ђ���Ƃ����B
���́u���݂������v�ƈ��̂����ےÍ���{�̏Z�g��Ђ́A���ւɒ������钷�卑��{�̏Z�g�_�Ёi���_��ЁE���������Ёj�Ɣ����ɒ�������}�O����{�̏Z�g�_�Ёi���_��ЁE���������Ёj�Ƌ��Ɂu���{�O��Z�g�v�Ə̂����B
�Ր_�́u�Z�g��_�v�Ƒ��̂����C�̐_�����A�w�Î��L�x�̃C�U�i�M�m�~�R�g���S�̏�ʂʼn�������u�ꓛ�j���i���{�{�j�E�����j���i���{�{�j�E�\���j���i��O�{�{�j�v�i�Z�g�O�_�j�Ɛ_���c�@�i��l�{�{�j�̎l�_�B
�R���́A�w���{���I�x�̐_���c�@�ې��O�I�ɁA�V�������̐_����_���c�@�ɉ��������������Ƃ���B�܂��A�A�҂̍ۂɂ��u�Z�g�O�_�v����삵�������ƋL�ڂ���Ă���B
�����ɏo�Ă���u��Âْ̟��q�̒����v�ɁA��ɁA�Z�g��Ђ��n�����ꂽ�Ƃ����B
���݂́A���̏Z�g��Ђ̂����O�͊C�ł͂Ȃ����A�]�ˎ���܂ł͋����܂Ŕ������̊C������A�u�Z�g�͗l�v�Ƃ��ĊC�ӂ̐_�Ђ̒�^�̑�\�ł������B
�L���Ȕ\�́u�����v�ɏZ�g�̐_�ƍ����̐_�������̏��̈тƉW�̉~�������̕v�w�_�Ƃ��ďj�������B
�u������ ���̉Y�M�� �����グ�� ���̉Y�M�ɔ����グ�� ������Ƃ��� �o���� �g�̒W�H�̓��e�� �������̉��߂��� �͂�Z�g�i���݂̂��j�� �����ɂ��� �͂�Z�g�i���݂̂��j�� �����ɂ���v�Ɨw����B
�܂��A�w�ꐡ�@�t�x�ł́A�q��Ɍb�܂�Ȃ��V�v�w���Z�g��Ђɂ��Q�肵�Ď��������̂��u�ꐡ�@�t�v�Ƃ���A�e���܂ꂽ�B
���ۋ���n��A�����ɓ����āA���������Ƃ́A3�B
�@ ���̖{�a�̔z�u�I�@����ȕs�v�c�Ȗ{�a�z�u�\���͓��{�S���ǂ��ɂ��Ȃ��B
��������{�{�A���{�{�A��O�{�{�ƕ��сA�Z�g�O�_���J���A��O�{�{�̉E�ׂɑ�l�{�{�̐_���c�@���J���Ă���Ƃ����\���Ȃ̂��B
���ց`���I�@�������I�@���̋�ԃA���@���M�����h�I�@����͂������H
�z���}�A���ǂ낢�������ĂȂ�́B�r�b�N���V�I
�A ���ɁA�ׂ̃g�������������ȁA�������Ђ́u��N�Ёv�̑��B
�����ˁI�@�����ˁI�@�����ˁI
�g�g���ɉ�����ˁI
�{��x����́A���́u��N�Ёv�̂��Ƃ͂悭�m���Ă����̂��낤�ˁB
�B ��O�ɁA�Z�g��Ђ́u�p���[�X�|�b�g�v�I
�����ɁA�吨�̎Ⴂ�����������K��Ă��āA�����Ɂu�ܑ�́v�̎��̏����ꂽ����T���Ă����B
�����ˁA�u���݂������I�v
��������I
�������A�R�e�R�e�̃I�[�T�J��I
�܂������́`�I
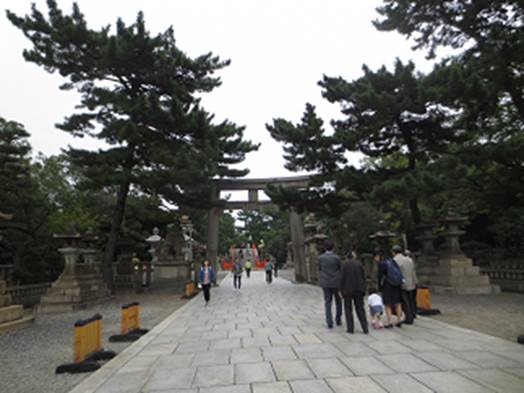
���d�ԁu�����O�v���Ԃ��Ă����̐��ʕ��i

���Α���U������ƁA��C�d�Ԃ̏Z�g��Љw

�Z�g�����

�Z�g��Б��ۋ�

�����̉��i���j�ɃR�}�l�R�H



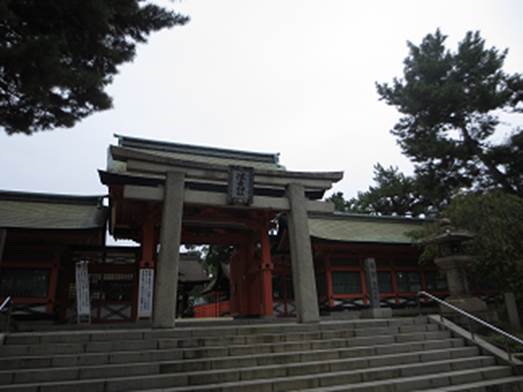

�Z�g��А_��


�Z�g��Б�O�{�{�Ƒ�l�{�{

�Z�g��Б�O�{�{�i���j�Ƒ�l�{�{�i�E�j


��l�{�{

��l�{�{



���{�{

���{�{

���{�{

���{�{



�ɐ��_�{�y�q��

��



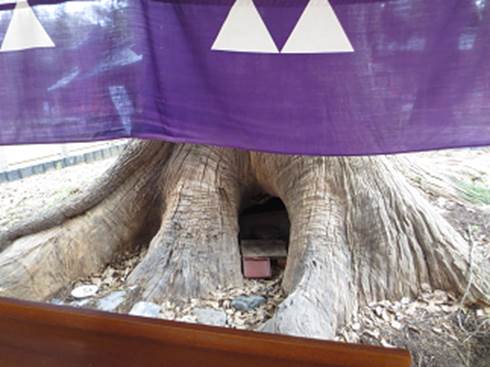


��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N��

��N�_��



�p���[�X�|�b�g�I
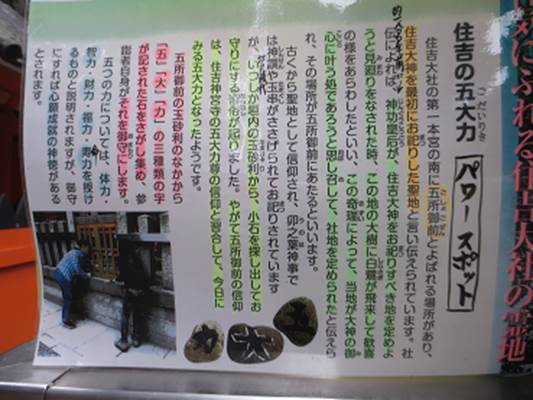
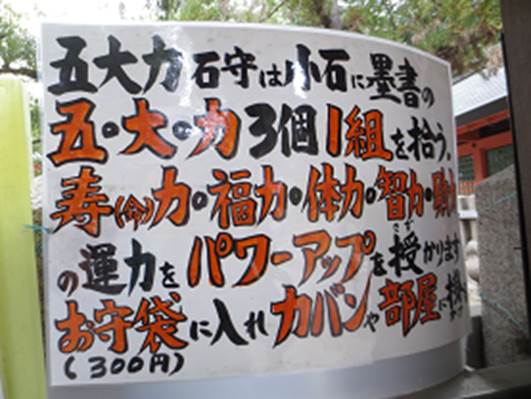

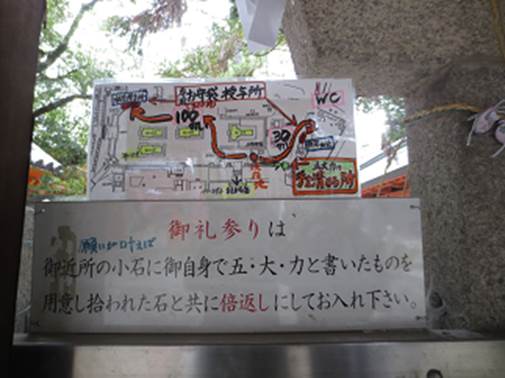
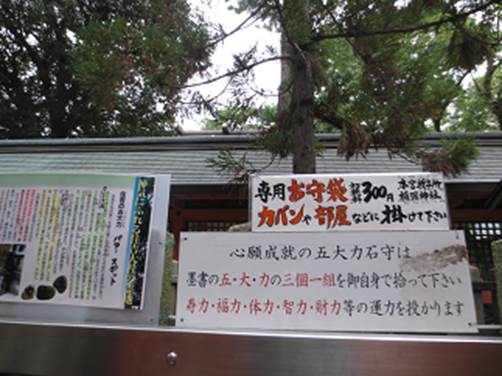


�p���[�X�|�b�g�Q��

�p���[�X�|�b�g�Q��


�����Ǝ�



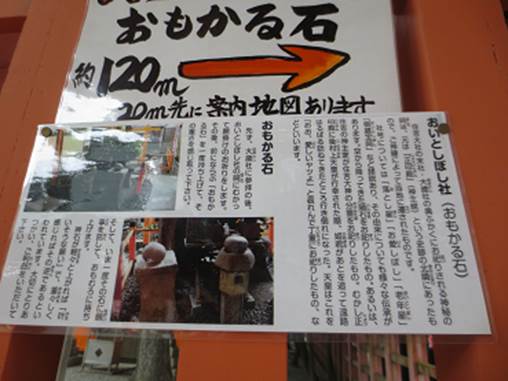

�Z�g�����ق̌f��

���V�_��

���V�_��

���V�_��

���V�_��

��ΐ_��

��ΐ_��

�����Ƃڂ���

�����Ƃڂ���
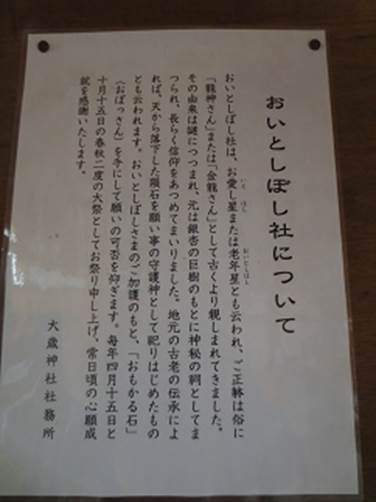
���́A�u���݂������v�́u���ł��A���v���S����`�ɓ��Ă��āA��͐����O�\�O���Ɍw�ł�C�͂��킪��A���̂܂��Ɉ���������悤�ɓV�����ɖ߂�A�t���t���Ɓu�ʓV�t�v�ɋz����ꂽ�̂ł������B
45�N�Ԃ�ɁI
�ʓV�t�ɁI
�V���E�ɁI
�u�����E�l�v���I
�ƁB

�V�����V���E�@�W�����W��������
��������͗l�ς�肵�Ă����W�����W���������B

�W�����W���������̏����E�͌鏊
�ł��A���A�u�����v�̓`���̂��鏫���̓a���ŁA�����w���̉������I

�������w���l�X
���������I
�����ˁI
�����ˁI
�����ˁI
�����āE�E�F

�V���E
�e�[�}�p�[�N���A����́I
�u�Z���g��q�̐_�B���v�̐_�X�̓������H

�ʓV�t
���݂Ȃ�I
�ʓV�t�͂�I

�V���E�Âڂ��
���݂Ȃ�I
�Ă�����A�u�Âڂ��v�͂�I
�Ȃ������̂��`�I

�V���E

�V���E
�ݘa�c�̂��肩�I�H�H���H

�V���E
���Ă��Ă̂Ă��Ă��̂���������`�I

�V���E
�m�b�N�A�E�g�������I

���ׂ̃n���J�X
�����ɒ����_���A�j���[���[�N�A�}���n�b�^���H
���Ă̂��������肪�����V���������͂��Â��ɁH

�V�ƒʐM����p���[�X�|�b�g�i�I�j�u�ʓV�t�v
���A�ʓV�t�͂�́A���Ȃ��ɒʓV���A���M���Ă����I
�j�āA�얳�ɓ_�I
�ʓV�t�l�I
���ڎ�2
2016�N10��22���@���c����F10��21���Ɂu�[���t�W�v�ɁA10��29���J�Áu�ܖ؊��V�u���{�C�k�v�̋L�����o�܂����@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
����A10��21���́u�[���t�W�v�ɁA10��29���J�Áu�ܖ؊��V�u���{�C�k�v�̋L�����o�܂����B
���A�ܖ؊��V�����������āA10��29���̑ł����킹�����܂������A�u�߂ƈْ[�́v�ɂ��Ă��b���Ă����悤�ł��B
��ϊ��҂��Ă��܂��B
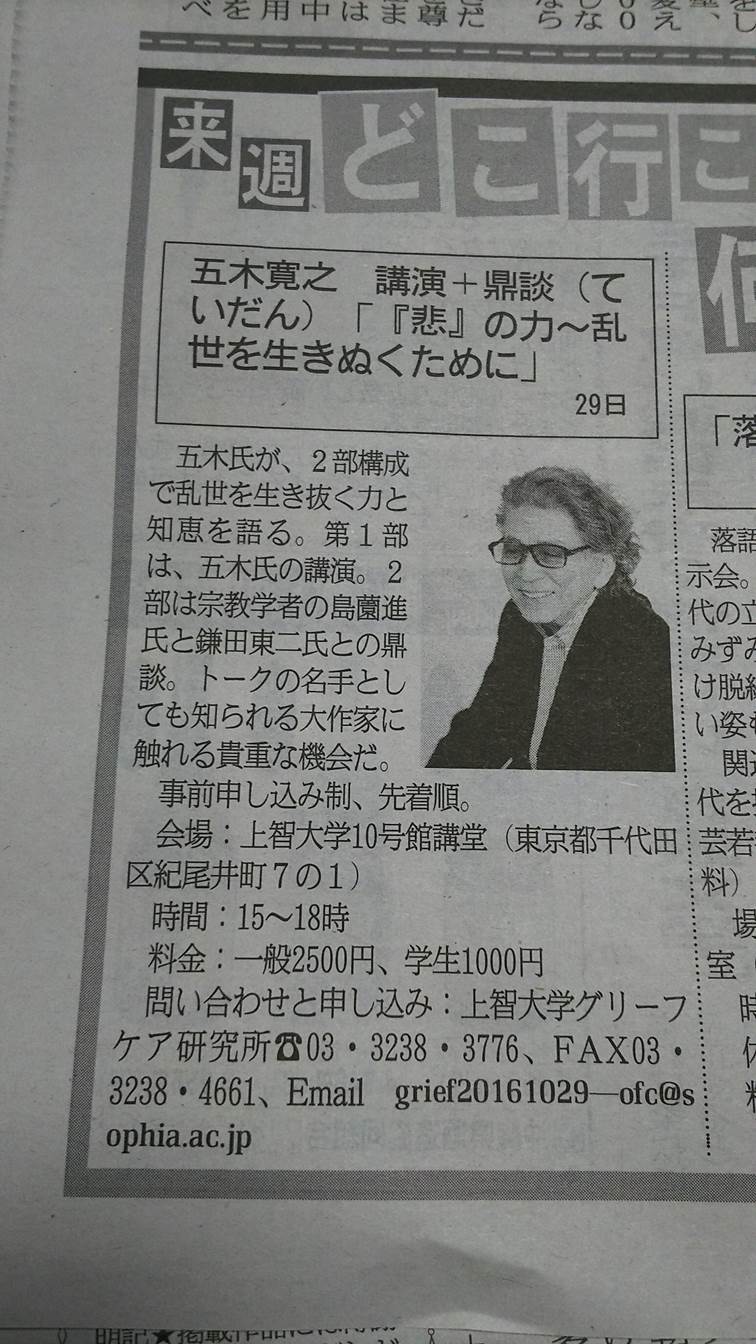
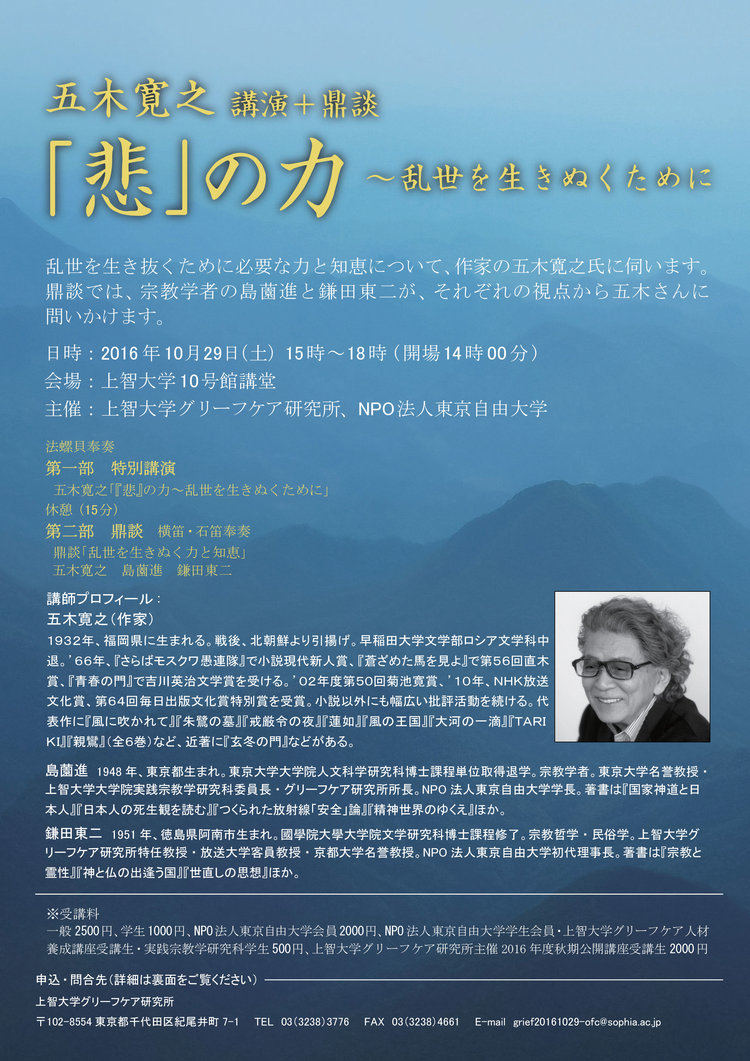
�P�O�E�Q�Q�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��20���@���c����F10��16���i���j�������ʃV���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v���@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�x����Ȃ���A10��16���i���j�������ʃV���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v�̕ƁA�������W�����̓Y�t�����܂��B
�Q�l�ɂ��Ă��������B
�Q���҂�50�l��Ə��l���ł͂���܂������A���Ƌc�_�͗L�Ӌ`�ŏ[�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����Q���҂���̂��̂悤�Ȑ����͂��Ă��܂��B
���ѐ��킳��́u�_�ЂƐ����v�B
�_�Ђ����u���̌����`���ԐM��K���_���̑��ʁv�Ɓu���̌����`���Ɛ_���I���ʁv�̗��ɂ̒��ŁA���͂Ɩ����\���ɂ��Ẵf�U�C��������܂����B
�܂��A���{��c��_�������A���ȂǁA�������Ɋւ��̐[���c�̂ɂ��Ă̌��y������܂����B
�����I�c���q����́u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v�B
������AIS�̌���A�A�����J�𒆐S�Ƃ����ĐA���n��`���̋c�_�A�����̖��O�̃A�����J�ƗL�u�A����IS�ւ̔ᔻ�ӎ��̍��܂�Ȃǂ̌���ƌ��͂�����܂����B
�I�c����́A���{�����w���ł�����܂��B
����̐��E�ƒ����̍ĐA���n���A�Ē鍑��`���APKO�@����e�����[�@�A�C���N���[�@�A�C���Ώ��@�A���ۖ@���ւ̓��{�̗���̖��_�Ɗ댯���B
2011�N�́u�A���u�̏t�v�Ƃ����]���_�B�e�[�v�N���������āA2017�N3�����s�\��̌����N��
�킽���̘b�́u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v�B
����ɂ��ẮA�Y�t���W�������������������B
�������ωs���L�Ӌ`�ŁA
�@�����@���Ǝs���@���Ƃ̊W�ɂ���
�A�R�Y�A���邢�͌R�Y�w�����̂ɂ���
�B�A�d���E�A�d�j�ςɂ���
�C�����ېV���̔p���ʎ߂̔w�i�ɂ���
�D�ɐ��_�{�̍��Ɨ��p�ɂ���
�E�V�c�̍����s�ׂƁu���O�ވʁv���ɂ���
�ȂǂȂǁA�c�_�͐s���܂���ł����B
�����ѐ���u�_�ЂƐ����v �X���C�h �ipptx 100KB�j
�����ѐ��� ���\�}�� �ipdf 224KB�j
���I�c���q�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v ���W���� �idocx 28KB�j
���I�c���q �����n�} �ipdf 618KB�j
�����c���� �����V���|�W�E���u���a�E�@���E�����v ���W���� �idocx 64KB�j
���ʍ����V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v
�����F2016�N10��16���i���j13���`18���i�����E�\��s�v�E���ډ��ɂ��z�����������j
�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X10����1�K�u���i�l�b�J�w���k��3���j
���ÁF��q��w�O���[�t�P�A�������E�g�S�ϗe�Z�@������/�n�����a�����l�b�g���[�N
���́F���ۊ����w�iICU�j���a������/��t��w�n�������������Z���^�[
�u���F
�@���ѐ���i��t��w�����E�����N�w�j�u�_�ЂƐ���--���܍Ăѕ��a�ƌ�����₤�v40��
�A�I�c���q�i��t��w�����E���������j�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v40��
�B���c����i��q��w�O���[�t�P�A�������E���s��w���_�����E�@���N�w�j�u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v40��
�R�����e�[�^�[�E�i��F��t�� ���ۊ����w�iICU�j���C�����i�����v�z�j�E�������_�j�A�R�����g�F15��
�������_�F���ѐ���{�I�c���q�{���c����{��t���i�i��j

�P�O�E�Q�O�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��15���@���c����F���R�C�����R�V�W�@�@���ڎ�2
2016�N10��15��
�����́A10��15���ŏ\�ܖ�B
�����������������̂��B
�V���̗�̈�v��������B
�����͏H����B
���͂��̎�����Ԃ̗₦���݂��������A�C���͂������ɂ͂��Ȃ�㏸�B
15��10���A���R�C�����o���B
���グ���ɁE�E�E

�{���̔�b�R
�u�₩�B
�H�̋�C�ƐF�B
��X�_�Ђ�y�q���āA�֎�@���o���Ă����ƁE�E�E

�֎�@��̉��t

�֎�@�ٓV�r�̍g�t

�֎�@�ٓV���̍g�t
���X�ɍg�t���i��ł���B
���A�܂��܂��B
���ꂩ��B
���A�����͓y�j���Ȃ̂ŁA�ό��q�͌��\���n�߂Ă���B
�g�t�̎ʐ^���B���Ă���l���`���z���B
���Z�~�i�[�n�E�X�̘e�̗т�ʂ��āA�_���ցB
�X�������ɏH�C�z�B
�X�̃��A�C�N���H�C�z�B

�{���̐X�̃��A�C�N
���Ȃ�A�������B

�{���̐X�̗d���N
�X�̗d���N�͂����ς�炸�������B
�|�ꂽ�܂܂����ǁB
����͂����Ԍ��ʂ����悭�Ȃ��Ă����B
���E���L��������B

�{���̐X�̉���
���n�̔w�̃i���͂�B
�ւ��`�B
�i���̖ɓ����������Ă���B
����Ȃ��Ə��߂āB
�Ƃ������Ƃ́A�����Ԃ�A�����̓��˂��̊p�x����ɂ���ė��Ă���Ƃ������ƁB

�i���͂�̓�

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
�X�̃��A�C�N���H�̓������̒��A�N�炩�Ɍ��グ�Ă���B

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l
���n���l�́A�������V���[�v�B
�ŋ߁A����ȁA���n���l�̂悤�Ȑl�ɉ�����B
����́A����̊�����Ѓ��[�c��\������̍��ÐV�V������B
���Â��ŋߍl���Ă��邱�ƁA���g��ł��邱�ƁA���g�����Ƃ��Ă��邱�ƁA�Ȃǂ����B
���ÐV�V������́A1975�N���A���{�r�c�s�ɐ��܂ꂽ�B
���C�Ȏq��������߂��������A�������A12�̎��A1�^���A�a�i��N�����A�a�j�Ɛf�f����A�a�C�Ƃ̐킢�ƕt�������̒��Ŏ��Ȍ`�����Ă����B
�����āA�S���w���w�ڂ��Ƌ��s��w����w���ɐi�w���āA�{�g�S�ϗe�Z�@������E�������͎҂̔��B�S���w�҂Ŏ��I�����̑��l�҂ł����܂��悤�����s��w�����i���݁A���s��w���_�����A�����ّ�w���ʏ��ً����j�̃[�~�ɓ���B
5�`6�N�O���������A���̂�܂��悤���搶�̃[�~�ɎQ�������ہA���ÐV�V��������Љ��A�������̏�ō��Â���ɓd�b�����̂������B
����ȗ��̕t�������ł���A��d����Y�ēɂ��Ȃ����o�܂�����B
���Â���͋��呲�ƌ�A2001�N�ɉ���ŏA�E�B��������V�����l�ނ�d���ݏo���u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�̗̈�Ŋ������Ă����B
�u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�Ƃ́A���َ��ȗ̈��}��A����܂ɂȂ��ω��ݏo���u�������̒m�v�̒S���聄�̂��Ƃ������B
����́A�����푽�l�ȃv���W�F�N�g�̃N���G�C�e�B�u�E���[�N�`�[���̌`���E�W�J��S���u�V�����^�C�v�̔}��ҁv�Ƃ��āA�����ɂ���~�b�V�������������A�َ��ȗ̈��}��A�v�V�I�ȉ��l�n����W�J�����Ă����Љ���Ƃ̂��ƁB
�_�b�Ō����A�u�g���b�N�X�^�[�v�I�Ȃ͂��炫�����鑶�݁A�Ƃ�������B
��͂���Ȕ}��҂̂��Ƃ��A�u���̍s�ҁv�ƌ����āA�������Ɏ��H���Ă������A���Â���͎��̐���̐V�����u����̉��̍s�ҁv�ł���B
�����́u�Љ�f�U�C�i�[�v�u�n��R�[�f�B�l�[�^�[�v�Ƃ����Ă��悢�B
�����āA��ォ�����Ă����}���r�g�I�u�悻�ҁv�Ƃ��āA�ً��̉���̒n�ŁA�n���̃��f�B�A��l�b�g���[�N�����p���A���̉����n���S���l�ވ琬��u�������v���Ȃ������ɓ��z�������Ă���B
�����āA�v�z�i�N�w�E���O�j�Ɛ������H�Ƃ�Z���������V�����Љ�Ɛ����������N���G�C�g���Ă���B
���Â����̉�Ёu���[�c�v�̃��b�g�[�́A�u����̃C�m�x�[�V�����A���ꂩ��̃C�m�x�[�V�����v�ł���B
�܂��́A����ɐV�����d���ݏo���A�l�ނ���āA����̕������f�B�A�����p���A�������Ɍ������Љ�f�U�C�����N���G�C�g���Ă����B
���́A�������ȁu�d���v����肽���������A�����Ȃ�ɂ���ė����B�u�y�����������v�Ə̂��Ȃ���B
NPO�@�l�������R��w�̊����Ȃǂ����̈�����A�܂������r�W�l�X�ɂ͂Ȃ炸�A���v���オ�炸�A���N�Ԏ��c�̂������B
�ނ���A�����������B
�Ƃ͂����A�����`�Ŏ�����Ɉ����p����Ă���B
�{�g�S�ϗe�Z�@��������A�u�C���^�[�~�f�B�G�C�^�[�v�I�Ȍ����I�Љ�ϗe�f�U�C�������Ƃ�����B
�Ƃ����킯�ŁA�b�����Ȃ���A�ƂĂ��A�������A�ӂ�ʂ��A�ӂ��������A�����������A�����Ɋ�]�Ɗ��҂��������̂ł��`��I
������l�̂��n������́A�X�y�C���̃M�^���X�g�̃p�R�E�f�E���V�A�iPaco de Lucia�A1947-2014�j�B
�p�R�̓X�y�C���̃A���_���V�A�n���ɐ��܂ꂽ�B
�����Z���t�������R�E�M�^���X�g��t�������R�̎�B
5�l�Z��̖����q�Ƃ��Đ��܂�A����ɉ��y�����Ă͂������A�n���������p�R�́A1961�N�A�Z�y�y�E�f�E���V�A�Ƃ̃f���I�ŏ����R�[�f�B���O���A1963�N�ɓn�āB���J���h�E���h���[�S�Ⓑ�Z�������E�f�E�A���w�V���X�ƃf���I�Ŋ����������B
1967�N�A�wLa Fabulosa Guitarra De Paco De Lucia�i�V�ˁj�x�Ń\���E�f�r���[�B
1973�N�A�wFuente Y Caudal�i�M��E��̐�j�x���́u��̐�v���X�y�C���q�b�g�E�`���[�g��1�ʂƂȂ�A���E�I�ɗL���ɂȂ����B
���̃X�y�C���́u���n���l�v�A�p�R�̃h�L�������^���[�f��u�p�R�E�f�E���V�A�`�ܔM�̃M�^���X�g�v���ς��̂��B
�ḗA�p�R�̒��j�ŁA1983�N�A�}�h���b�h���܂�̃N�[���E�T���`�F�X�B

�p�R�E�f�E���V�A
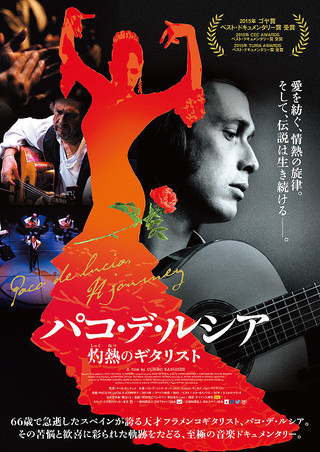
�f��̃|�X�^�[
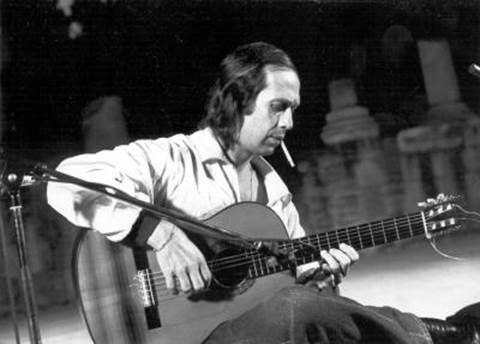
�p�R�E�f�E���V�A
�p�R�́A�t�������R�݂̂Ȃ炸�A�W���Y�Ȃǂ̕���ł�����B
�܂��ɁA�u�U���y�v�����y�����V���̉��y�Ƃ��B
1979�N�ɂ́A�p���̃W�����E�}�N���t�����A�č��̃����[�E�R���G���Ƃ�3�l�ŁA�A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[3�{�݂̂́u�X�[�p�[�E�M�^�[�E�g���I�v�c�A�[���s�Ȃ��A�]�����ĂB
�A���o���wFriday Night In San Francisco�x�i1981�N�j�A�wPassion, Grace & Fire�x�i1983�N�j�A�wSiroco�x�i1987�N�j�A�wZyryab�x�i1990�N�j�Ȃǂ\�B
�t�������R����Ղɂ����A���̘g�Ɏ��܂�Ȃ����݂ȉ��y���E������𑱂������A2014�N�ɑ؍ݐ�̃��L�V�R�ŐS������Ŏ��B���N66�̎Ⴓ�������B
�p�R�͌��������B
���y�̐����A����́A�u���Y���v�A���A�ƁB
�ނ̃O���[�v�ŁA�u�J�z���v�Ƃ������^�y����g���n�߂�ƁA����͏u���Ԃɐ��E���ɍL�������B
�Ⴊ�g��ł������c����ƃ��[���T���g�E�v���W�F�N�g�̃p�[�J�b�V���j�X�g�̌Ð�͂��߂�����J�z�������p���Ă��B
�V���v���ł������o���Ŋy�킾�B
���̉f��̒��ŁA�p�R�͌����Ă�B
�u�M�^�[�̂������Ŏ��R�ɑz����\���ł���B�M�^�[���Ȃ���Ύ����̊k�ɕ��������Ă����B�������g��\��������@�͂���ȊO�ɂȂ����炾�v
�u����ł������������Ɨ͂��N���Ă���B���x�����̌���ʼn��t���邤���ɁA�Ђ�߂��͓V����~��Ă͂��Ȃ��ƋC�Â����B�̂̉����炻����������Ƃ��A�����������܂��v
�u���Ȃ��Ƃ��J����1���ԑO�ɂ͊y���łЂƂ肫��ʼn߂��������B1���̒܂��ق���菭�����������ł��A�����ł��\�z���Ȃ������~�X���N����v
�u���̐l�����Ő����Ă����v
�u���Ɍւ����̂�����Ƃ���A�c�������爤���Ă������y�ɍv���ł������Ƃ��B�����Ƒ����t�������R�̉��t�Ƃ������B���ɂƂ��Ĉ�Ԃ̌ւ�͉��y��ʂ��ė��̑��Ղ��c�������Ƃ��v
���̃X�y�C���́u���n���l�v�ɂ́A�u���y�̓N�l�v�̕��e�ƕ��i���������B
���̃p�R�̃h�L�������g���ςȂ���A������l�A���V�A�́u���n���l�v���v�������ׂ��B
����́A�����̐_�l�A�X�^�j�X���t�X�L�[�B
�Ƃ����̂��A���ŋ߁A�Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�i�x�]�V���A�����ЁA2015�N�j��Ǘ����A����Ȉ�ۂ��o�����̂��B
���̖{�̒��ɂ́A1911�N�ɁA�X�^�j�X���t�X�L�[�����[�K�Əo��������Ƃ��L�x�Ȏ������p��ʂ��Ė��m�ɏ��q����Ă���B
�u�����@�c�L�[�̐_�q�w��h���t�E�V���^�C�i�[�̐l�q�w�ɐG��Ă������Ƃ��L����Ă���B
1911�N�A�X�^�j�X���t�X�L�[�́A���q�̉ƒ닳�t�ł��������X�N����w�̈�w���Ń`�x�b�g��w�̌��������Ă����f�~�[�h�t����A�C���h�́u�n�^�E���[�K�v�Ɓu���W���E���[�K�v�̐g�S�ϗe�Z�@�̘b���A���X�N���ɖ߂��Ă����ɁA���}�`�����J�́w�n�^�E���[�K�[���N��ۂ��߂̃��[�K�N�w�x�̖{���w�����A�Â�悤�ɓǂݒ^�����̂������B
���̌�A�X�^�j�X���t�X�L�[�́A�u�v���[�i�v�Ƃ������[�K�p����g���Ĕo�D�w��������悤�ɂȂ����B
�����A1917�N�̃\�r�G�g�v����A�u�v���[�i�v�Ƃ����g�`���ێ�u���W�����ϔO�p��h�́A�u�G�l���M�[�v�Ƃ����A���g�B���Ȋw�h�I�ȗp��ɐ�ւ���ꂽ�B
�����A�`�F���J�b�X�L�[�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�̎��̈�߁B
�u�����̊�b�Ƃ��Ă̌ċz�Ƃ������[�K�̍��{�v�z���A���Y�����������|�p�̊�b�ł���Ƃ����X�^�j�X���t�X�L�[�̊j�S�ƌ��т����̂́A�܂��ɃI�y���������ł̂��Ƃł������v�i62�Łj�B
�t�������R�E�M�^���X�g�̃p�R�́A���y�̂��̂��́u���Y���v�ł���ƌ��������B
�X�^�j�X���t�X�L�[�̉����|�p�_�ɂ����l�̊j�S�c��������B
�܂��A�u�D���ő��`�I�ȓ����ɂ́A�w������ϑ傫�ȈӖ������v�i65�Łj�Ƃ���̂́A�����I���B
������̌|�_�́u�ڑO�S��v�ɂ��ʂ���B
�u�H���v���������ɂ͔w�������Ȃ�����I
����ϐ����v����́u�䓛�v���ςāA���Â������������B
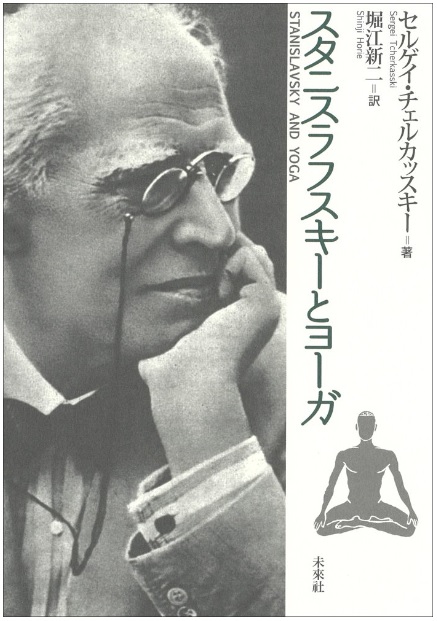
�Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�́A�T���N�g�E�y�e���u���O����������w�̋����ł���B
����Ȉ�߂�����B
�u�����I�ړI�Ń��[�K�𗘗p����ɂ́A���[�K�̂������̕���������]�����邱�Ƃ��K�v�������B�X�^�j�X���t�X�L�[�ɑ����āA���̖��������Ƃ��[���𖾂��悤�Ƃ����̂��A�O���g�t�X�L�ł���B�ÓT�I���[�K�������ɓK�������悤�Ƃ��āA�ނ͑�ςȍ���𖡂�������A����ł��ނ̃��[�K�M�͗�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B����ɁA�����̐l�i�����ɂ̓X�^�j�X���t�X�L�[���܂܂�邪�j�ƈ���āA�O���g�t�X�L�̃��[�K�ւ̊S�́A�o�D�̃g���[�j���O�̐��ݓI�\���Ƃ����ʂ��炾���ł͂Ȃ������B�O���g�t�X�L�̊S�́A�����Ƀ��[�K�𗘗p����\���Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɂ������B�����A���������Ă悯��A����͉����w�ȑO�x�̂Ƃ���ɂ������̂ł���B�����āA�����w�Ȍ�x�̂Ƃ���ɂ��c�c�B���[�K�ւ̊S�Ƃ��̌����́A�O���g�t�X�L�������̐��E�֓���ȑO���炠�����B�����āA����聄�̏h���I�ȓ����������邽�߂ɓ`���I�ȉ����̐��E���痣�ꂽ���Ƃ��A�ނ̉��o�Ɓ��v�z�ƂƂ��Ă̊�{�p����@���Ɏ����Ă���B�܂�A�ނɂƂ��ĉ����́A���ꎩ�̂��ړI�ł͂Ȃ��A���̖ړI�ɂ������i�Ȃ̂������B����ɂ��āA�V�F�t�l���͌����ɂ������q�ׂĂ���B�v�i80-81�Łj
�����āA���̃V�F�t�l���̒�������̈��p���B
�u�ށi�O���g�t�X�L�j�̍ŏI�I�ȖړI�́A�u���q�g�̂悤�ɐ����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�X�^�j�X���t�X�L�[�̂悤�Ɍ|�p�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��A�A���g�[�̂悤�ɔ��R�I�Ȃ��̂ł��Ȃ��B�O���g�t�X�L�̋��ɂ̖ړI�́A���_�I�Ȃ��̂��B����́A������҂̐S�̒T���A�S�̈琬�v�ɂ������v�i81�Łj
�O���g�t�X�L�i1933-1999�j�̍ŏI�ړI���u������҂̐S�̒T���A�S�̈琬�v�ɂ������Ƃ����̂́A������̖��������Z���^�[�ɂ�����ɂƂ��đ�ϋ����[���_�ł���B
���̂�����A�O���g�t�X�L�̉����������̊����������ƒ��ׂĂ݂�K�v������B����������̗͂���āB
���̖{�̍ŏI�͂ł́A�X�^�j�X���t�X�L�[�́u���ӎ��v��u���݈ӎ��v�̊T�O���l�@����A�����āA���̂悤�ȃz���C�g�̌��t�����p�����B
�u�T�}�[�f�B�͂������̒i�K�ɕ�����Ă��邪�A���̈�ԍ����i�K�͏C�s�҂��A�������ґz�̑ΏۂɊ��S�Ɉ��ݍ��܂ꂽ���w���B���[�K�ɂƂ��Ă����ґz�̑Ώۂ͐_�ł���B�X�^�j�X���t�X�L�[�ɂƂ����ґz�̑Ώۂ͖��ł���v�i134�Łj
�����ށB
�܂��ɁA�X�^�j�X���t�X�L�[����̔o�D�p�Ƃ́A�u�g�S�ϗe�Z�@�v���̂��̂ł���A�u�g�S�ϗe�v���̂��́A�ł��킷�ˁB
�����āA�����āE�E�E
�u���䂠�聄�i�A�C�@�A���j�̏�Ԃɂ����ċN���邱�Ƃ́A���}�`�����J�̏ꍇ�A��q�ƃG�l���M�[�̐��E�����Ƃ̐_�I��̉��ł���A�X�^�j�X���t�X�L�[�̏ꍇ�́A�o�D�Ɩ��Ƃ̈�̉��ł���B�����ł́A�����̕����I�g�̂ɑ��邬�����Ȃ���s�����͏����Ă����̂ł���B�o�D�����䂠�聄�̏�Ԃɓ��荞�Ƃ��A�w�ϋq�̑O�őz������Ƃ�������ł͂Ȃ������ɂ�������炸�A�o�D�̐��_�I�A�g�̓I�튯�͕����ŁA�l�Ԃ̖@���ɏ]���A�������ɂ�����̂Ɠ����悤�ɐ���ɓ����x�v�i136�Łj
�u�o�D�Ɩ������S�ɗn�������X�^�j�X���t�X�L�[�́��䂠�聄�̏�Ԃ́A�C�s�҂Ɛ_�I�Ȃ��̂����S�ɗn���������[�K�̃T�}�[�f�B�ƌĉ����Ă���B�X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���̂Ȃ��ŗB�ꋳ��X���u�ꂩ����ꂽ���̗p��ɂ����āA���[�K���ґz�ł����I�[����̐_���ȉ����{�����ċ��������Ă����̂ł���v�i137�Łj
�ƁA���̃��V�A�̂��n���l�́u���v�̋��ʂ������̂ł���B
�����ށA�����ށB
�����낢�B
�����낷����B
���̃��V�A�̂��n���͂�́B
12��18���̍��ۃV���|�W�E���u������ƃX�^�j�X���t�X�L�[�v����ϊy���݂��ˁB
���́A���̖{�̓��{�ł܂������̒��ŁA�u�V���̕��v���R���O�i1881-1928�j���A1913�N�ɃX�^�j�X���t�X�L�[���o�́u�ǂ��v�Ȃǂ�A�����X�N���|�p���Ŋό����A�X�^�j�X���t�X�L�[�̎���ɏ�����č��k���A�X�^�j�X���t�X�L�[�́u�V�X�e���v�Ɛ�����Ƃ̊Ԃɋ��ʓ_�������������Ƃ������Ƃ��w�E����Ă���B
�c�O�Ȃ���A�ǂ̂悤�ȋ��ʓ_�ł��邩���A��̓I�ɋL����Ă��Ȃ����A�u���R�����X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���̂Ȃ��Ɏ����ɓ���݂̂��̂��݂��A���ꂪ�����팳���̌|�_�ł������ƋC�Â����Ƃ��̋����͂����قǂł������낤�v�i4�Łj�Ƃ���̂��B
���̓_�A�`�F���J�b�X�L�[�����ɏڂ��������Ă݂����ˁB���x����Ƃ���������A���Аu���Ă݂悤�B
�Ǝv���Ă��邤���ɁA���n���l�̒n��𗣂�āA�w�ђn�тցB
�����ɂ��A�悭�H�̐������������Ă���B

�{���̞w��
�����āA�����u�ցB
�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o1���Ɗe��^���ƘZ���q�B

�{���̂����u

�{���̐���R

�{���̔��i��
�����āA���i�����n���A�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��Ƃł�Ԃ�14��B
���邭�邭��B
���邭�邵�Ȃ���A�X������B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̉��H��
�����āA��ꗎ�����������̍�X�_�ЂցB

�{���̍�X�_�Ђ̐_��
�Q�q12�q���q�B
�����āA�_��������B
�����Ɏʂ肵���m�́H
����̂��n���l�H
�X�y�C���̂��n���l�H
���V�A�̂��n���l�H
�n�N�̒n����F���݂Ȃ�I
���ڎ�2
2016�N10��14���@���c����F10��16���i���j13���`�V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v���ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�܂��܂��u���a�v���ێ����Ă����̂���ύ���Ȍ������u�����v�ɓ˓������l����悵�Ă��܂����A����10��16���i���j�ɏ�q��w10���ٍu���ŁA��t������⏬�ѐ��킳���I�c���q�����Ƌ��ɁA���a���l����u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v�V���|�W�E�����s�Ȃ��܂��B
�����ŁA�\��s�v�̍Â��ł��B
���s�������܂����為�Ђ��z�����������B
���ʍ����V���|�W�E���u���ӂ����ѕ��a�Ə@���ƌ�����₤�v
�����F2016�N10��16���i���j13���`18���i�����E�\��s�v�E���ډ��ɂ��z�����������j
�ꏊ�F��q��w�l�J�L�����p�X10����1�K�u���i�l�b�J�w���k��3���j
���ÁF��q��w�O���[�t�P�A�������E�g�S�ϗe�Z�@������/�n�����a�����l�b�g���[�N
���́F���ۊ����w�iICU�j���a������/��t��w�n�������������Z���^�[
�u���F
�@���ѐ���i��t��w�����E�����N�w�j�u�_���Ɛ���--���܍Ăѕ��a�ƌ�����₤�v40��
�A�I�c���q�i��t��w�����E���������j�u������Ɠ��{�E���E�̂䂭���v40��
�B���c����i��q��w�O���[�t�P�A�������E���s��w���_�����E�@���N�w�j�u���a�Ɛ_���̖�萫�Ə@���̖����`�䂸��Ƃ�邵�ɂ��ϗe�ƌ����v40��
�R�����e�[�^�[�E�i��F��t�� ���ۊ����w�iICU�j���C�����i�����v�z�j�E�������_�j�A�R�����g�F15��
�������_�F���ѐ���{�I�c���q�{���c����{��t���i�i��j

�P�O�E�P�S�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��14���@���c����FRe�F�u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L�i�j�[�X�j�@�@���ڎ�2
����ɂ���
�b������̊������ւ�A���肪�Ƃ��������܂��B
�{�N7��14���Ƀe���������N�������j�[�X�ŁA�������x�̉����Ɓu�v���I�f�b�Z�C��O�� ���́v�̏�f���s�Ȃ�ꂽ���ƁA���������L������낢��ƍl���������܂��B
�����āA�|�\��|�p���A������I�Ɍ����Ȃ�u�V���̌�F���v�i�w���p�ԓ`�x�j�ł��肤�邱�Ƃ̈Ӗ����ēx�˂������܂��B
��d����Ɖ��x������Ă��鉜��N�Ɍ��Ă�����āA������i�퐢�H�@�j���C�J�i�C�H�@����Ƃ��H�H�H�j�̑�d�ǂ�������������ł��邱�Ƃł��傤�B
�P�O�E�P�S�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��14���@����ɁF�u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L�i�j�[�X�j�@�@���ڎ�2
���c�搶�A������̐搶��
�݊O�������̉���ł��B
���������������Ă���܂����A���ς�育�����܂���ł��傤���B
���Ƀ^�C�����O�����苰�k�ɑ����܂����A9�����̓��j���A�j�[�X�ɂāu�v���I�f�b�Z�C��O�� ���́v�̊ӏ܂����Ă܂���܂����B���傤�ǂ��̎����}���Z�C���ɍs���Ă���A���܂��s�����������߃j�[�X�܂ő���L�����Ƃ��ł��܂����B�Ȍ��ł͂���܂����A�ȉ��ɂ��\���グ�܂��B
***
�E�j�[�X�́u�v���I�f�b�Z�C��O���@���́v�ӏ܋L
9��25���A�j�[�X�͂��܂��ē��a�A�삯���݂ő��z�𗁂тɗ����ό��q�œ�����Ă���B�ǂ�������������������A�J���b�Ɗ������n���C�̊y���͂ǂ��܂ł����邭�u�₩�ł������B����40�ȂقǁA��⏬�Ԃ�ł��邪�A�Α���̗��h�ȃz�[���ł���B�ׂɂ͐Α���̌Â��������A���͂ɂ́A���F��s���N�ȂǓ앧�炵���F�N�₩�ȏZ��Ђ��߂������Ă���B
���ꕶ���Љ�̃C�x���g�Ƃ������ƂŁA�������x�E���y�̃p�t�H�[�}���X���疋���J����B���̌�u�v���I�f�b�Z�C�v�̊ӏ܁A�Ō�ɉ��ꗿ���̎��H�Ƒ����B�f��̓t�����X��̎��������J�ŁA�F����H������悤�Ɍ��Ă�����B�I����Ă���R�ꕷ�����Ă���Ƃ���ł͔��ɍD�]�ł������B�ul'esprit de transmettre�i�`���̐��_�j�v���������ƌ����l�������B����閽���`��ς��āA������V���̒[�X�ɑ��Â��Ă���p���S�ɋ������̂��Ƃ����B
�f��̏I�ՁA�C�U�C�z�[�ɂ��Ă̏�ʂ��I���A�������f���o���ꂽ�Ƃ���ŁA�j�[�X�ׂ̗̋������炵���B�S�[���S�[���ƁA�����ő����ȉ��������B���R�̃^�C�~���O�Ƃ͎v�����A�����d�ēɕ��������A���邢�́A���𗁂т�n���C�̃j�[�X���A���������m�ɕ����ԋv�����ɋF���������悤�ȏ��Ɏv�����B
���́A�f��̍Ō�ő�d����̃i���[�V���������Ƃ���ŁA�v�킸���ݏグ�Ă�����̂��������B�������悤�Ɍ����������A�܂��`��ς��ĉ萁���̂��Ƃ����Ƃ���ŁA��d�ēɐG�ꂽ�C�������B
***
��Î҂̕��X�ɂ͊��ӂ��Ă���܂��B�F���܂��܂��d����̂��Ƃ��������Ȃ������悤�Ȃ̂ł����A���̎����Ɋς邱�Ƃ��ł��Ė{���ɂ悩�����ł��B
�p���⑼�̓s�s�ł��A�t�����X�̐l�����ɊςĂ��炤�@���������Ȃƍl���Ă���܂��B
����Ɂ@�q
���ڎ�2
2016�N10��12���@���c����FRe�F�l�̉Ȋw���26����̂��ē��@�@���ڎ�2
�I�����a�l
���ē��A���肪�Ƃ��������܂��B
��ϋ����[�����ł��ˁB
�Ƃ�킯�A2���ڂ�
��2016�N12��4���i���j
9�F00-10�F30�@A-1�@�u�C���̉\�����l����v
�������a�q�i����{���������C�@�j�@������v�i�V�����ыC����j
���� ���i���{�C���{���w������j�@�����i�C�������������j
���c���d �i�G���u�V������g�́v�ҏW�ҁj
�c������i�C�̈�w��E�������q��ȑ�w���_�����j
�o���O���Y�i���R�g�@������j�@������Y�i���C���������j
�́A25�N���̒m�F�ł���A�Ñ���������`���v�����o���O���Y���������W�����ϋL�O���ׂ��Â��Ƃ��Ȃ�A2017�N1��24���i�j�ɍs�Ȃ�����O���{���C���̑�14��`���҂̒��������̍u���E���[�N�V���b�v�E�V���|�W�E���Ɩ��ڂȊW������܂��B
�݂Ȃ���
���s�������܂�����A���Ђ��Q�����������B
�P�O�E�P�Q�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��12���@�I�����a�F�l�̉Ȋw���26����̂��ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�����������Ă���܂��B
���c�搶�̌䋖�����������܂����̂ŁA
�u�l�̉Ȋw���26����v�̌�ē�������
�Ă��������܂��B
�ڍׂ͓Y�t�t�@�C�������������������
�K���ɑ����܂����A���̑��̃e�[�}��
�u��w�E��Â�N�w����[���̂��̍�����
�������āv�Ƃ������̂ŁA������Ẩ\
����T�����ł��B
�����������b�ɂȂ��Ă���x�c���O��t��A
���삢�Âݐ搶�̂悤�ȃ��j�[�N�Ȑ搶��
���o�d����܂��B�x�c�搶�́A���u���
�i���҂̓��̂���O�ɂȂ��Ă��f�f�j���ł�
�閼��E�B�l�ł��B����搶�̓T�E���h�E�q�[
�����O�̃J���X�}�I�Ȋw�҂ł��B�g�̊ρA
�l�̊ς����{����ς��͂��ł��B
���J�u���ł́A�݂Ȃ��܂�����݂̑���
�a�Y�搶�⏼�����搶�����b�����������܂��B
���S�̂�����́A���ЂƂ����Q�����������B
������A�ꐶ������܂���B������A
�ǂ����ŕ������悤�Ȑ�`����ł��ˁB
�@�@�@�@�I�����a�@�q
���l�̉Ȋw���26����ē� �idocx 37KB�j
���ڎ�2
2016�N10��12���@���c����F2017�N1��30���i���j��54��g�S�ϗe�Z�@������J�Èē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
���N�̂��ƂɂȂ�܂����A2017�N1��30���i���j13���`18������q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ŁA��54��g�S�ϗe�Z�@��������J�Â��܂��B
���Ђ��Q��������B
�I����A�k��1���̋������u�k�̉v�ō��e����s�Ȃ��܂��̂ŁA����������Q�����������B
��54��g�S�ϗe�Z�@������
�����F2017�N1��30���i���j13���`18��
�ꏊ�F��q��w���T�e���C�g�L�����p�X���O���[�t�P�A�������i�T�N���t�@�~���A����2�K�A����}�~�c�w����������k��4���j
���\�@�H�ےm�M�i�����ȑ�w���u�t�E���w���p�j�j�u���R�̌��Ɛg�S�ϗe�`�u���̔h�v��������̃A�v���[�`�v�i����j
���\�A�H�얃���v�i�c��`�m��w�����E�Q�[�e�����j�u���R�̌��Ɛg�S�ϗe�`�Q�[�e���R�w����̃A�v���[�`�v�i����j
�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����j
�e60�����\�{60�����c
�P�O�E�P�Q�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��12���@���c����F11��21���i���j�`�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�S4��{2017�N1��24���i�j�������V�t�u�`�{�V���|�W�E���ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�g�S�ϗe�Z�@�������2�x���ۃV���|�W�E�����s�Ȃ�������C���̒������V�t�̍u�`�{�V���|�W�E���ƁA���̑O����Ȃ��u�������[�N�V���b�v�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�i�S4��j����q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ōs�Ȃ��܂��̂ŁA���ē����܂��B
�V���|�W�E���ɂ́A�{�g�S�ϗe�Z�@������E�������S�҂̉i�V�N���ƗыI�s�����Q������܂��B
2016�N�x�H�����T�e���C�g�L�����p�X���J�u���i���ʍu���j
http://www.sophia-osaka.jp/lecture/index.html
1�j�u������Ƃ��炾�̃P�A�w�v�S�S��i�S�W�R�}�A�P���Q�R�}���{�j�@�@
�u�t�F�u�`�@��q��w�O���[�t�P�A���������C�����@�@���c����
���H�@��ʎВc�@�l����{���������C�@�����@�����M�}��
����F40�l
�j�����ԁF�w�茎�j���A�u�`13�F00�`14�F30�@���H14�F45�`16�F15
�J�u�X�P�W���[���F
�@2016/11/21
�@�@�S�̒T���Ɛg�̂̒T���`�����E�����E�_���̐S�ςƃ��U�w�F���c
�@�@����h�{���C�����C�@�F����
�@2016/12/05
�@�@���K�ƍ��T�ƋC���̓N�w�ƃ��U�w�F���c
�@�@����h�{���C�����C�A�F����
�@2016/12/19
�@�@�S�̒T���Ɛg�̂̒T���`�̂Ɛ_�y�Ɣ\�ƏC���̃��U�w�F���c
�@�@����h�{���C�����C�B�F����
�@2017/01/16
�@�@�}�C���h�t���l�X�ґz�ƃO���[�t�P�A�^�X�s���`���A���P�A�F���c
�@�@����h�{���C�����C�C�F����
��u���F21600�~�i��2700�~8�j
2�j�u���A�W�A�̗{�������̔��@�Ɩ����\���v�S1��i�P���Q�R�}�j
�u�t�F
�u�`�A�V���|�W�E��
����O�����{���w�h14��`�l�A�k������������@�@���A��ʎВc�@�l����{���������C�@�@���@�������V�t�@���ʖ�F�R���[�q��
�V���|�W�E��
���s������w�y�����@�@�i�V�N��
����w��w�@��w�����ȏ����@�@�ыI�s��
��q��w�O���[�t�P�A���������C�����@�@���c����i�i��j
����F100�l
�j�����ԁF2017�N1��24���i�j13�F00�`17�F30�i�x�e�܁A�u�`�A�V���|�W�E���e2�����x�j
��u���F5400�~
�P�O�E�P�P�@���c����q
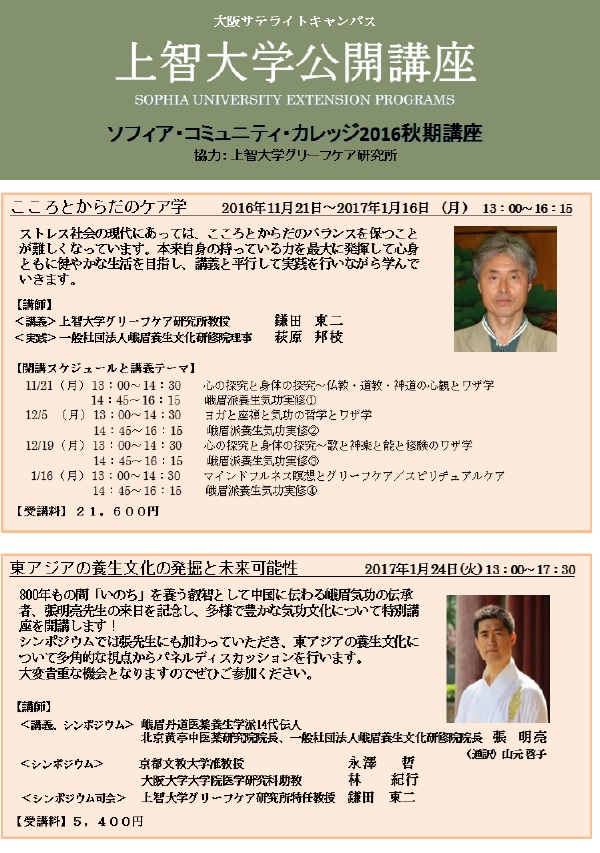
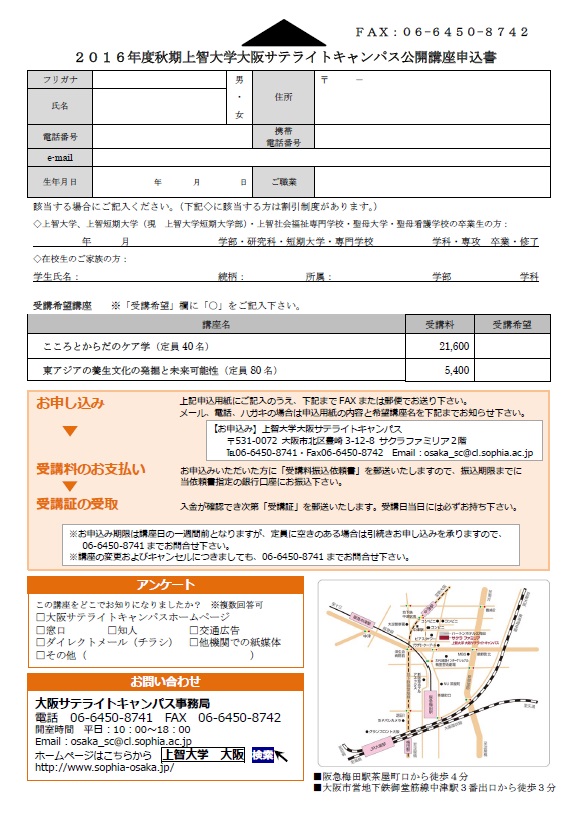
���ڎ�2
2016�N10��11���@���c����F���R�C�����R�V�V�@�m�Ԉ��ƕ������s�@�@���ڎ�2
2016�N10��10��
�����́A�u���{�̏@���ƕ��w�U�v�̎��Ə����̂��߂̋������t�B�[���h���[�N�B
�������̔m�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕��K�˂�̂��B
�o�~�̐��n�𓌎R�C��������킯�ł���B
�Ⴊ�ԂƓ�����掛�n��ɂ���o�~�̓a���E�������B
�֎�@�̕����玍�哰�̕��ɓ쉺����B
���哰���z���āA����ɓ쉺�B
���s���`�|�p��w�܂ł͍s���Ȃ����A���̎�O�ɃS���t���K�ꂪ����A����ɂ��̎�O�ɋ�����������B
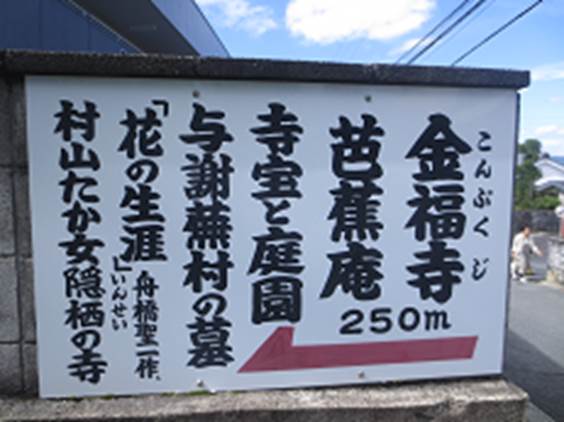
�������E�m�Ԉ��E�^�ӕ����̕�ւ̓��̖��
�������ɍs���r���A�{�莛�k�R�ʉ@������B
���̖{�莛�k�R�ʉ@�͏�y�^�@���{�莛�h�̕ʉ@���B
�e�a�i1173�|1263�j�́A����5�N�i1181�j�A8�̎��A�@�@��3�����̎��~�i1155�|1225�j�̂��Ƃŏo�Ɠ��x�����B
���~�͂��̌�A4�x���V�����߂��B
��62���A��65���A��69���A��71����4�x���B
����ȓV�����͎��~������l�����B
���x��A��b�R�ɓo��O��1�N�ԁA���̖k�R�ʉ@�̂���n�ŏC�s�����Ƃ����B�k�R�ʉ@�̋����ɂ͐e�a���N���Őg�𐴂߂��Ƃ�����˂�����B
���̌�A�e�a�́A���~�����Z�߂鉡��̎��@�̓��m��20�N�ɋy�ԔO���C�s���������A�����͐s�����A���͏C�s�̌��E�������A��������@�R�̐�Α��͂̔O���M�S�ɎQ�����Ă����̂����A���̑O�A��b�R����Z�p����100���Ԃ̎Q�Ăɕ����ۂ�������ɗ���������ƌ����邪�A������R�̂��ƂȂ���A���̎���Ɂu�{�莛�v���u��y�^�@�v�����܂��Ȃ��B
���̐@�@�́A�匴�O��@�▭�@�@�ƕ��сA�V��O��Վ��@�Ə̂����B���̎O��Վ��@�ɔ����哰�ƙ֎�@�������āA�V��ܖ�ՂƂ��̂����B

�e�a���l����
���̍≺�̊p���Ȃ����ď����s���ƁA�{���E���������B

�œ��R�������R�����
�����R��ɕ����킳���Ă���B
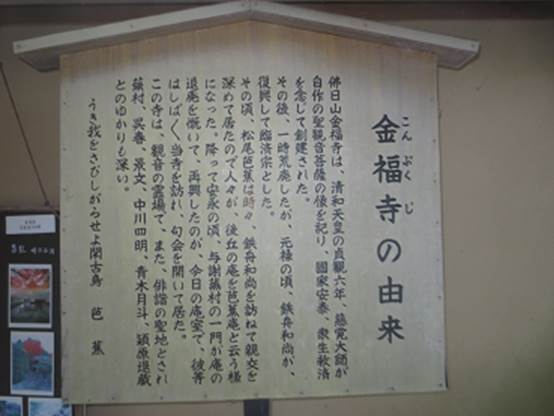
���������N
�������́A���6�N�i864�j�A���o��t�~�m������̐��ω���F�̑����J���āA���ƈ��ׁA�O���~�ς�O���ēV��@�̎��Ƃ��đn�����ꂽ�̂��n�܂肾�Ƃ����B
���̌�A�r�p���������A�]�ˎ���̌��\�̍��ɓS�M�a�����������ėՍϏ@�ɂȂ����B
���̍��A�����m�Ԃ����̒n�ɓS�M�a����K�˂Đe����[�߂��B
���炭�o���āA���i�N�Ԃɗ^�ӕ������m�Ԉ����ċ����A���̒n��o�~�̋��_�Ƃ����Ƃ����B
�������āA���̔m�Ԉ��ׂ̗ɗ^�ӕ����̕悪�����ƂɂȂ����B
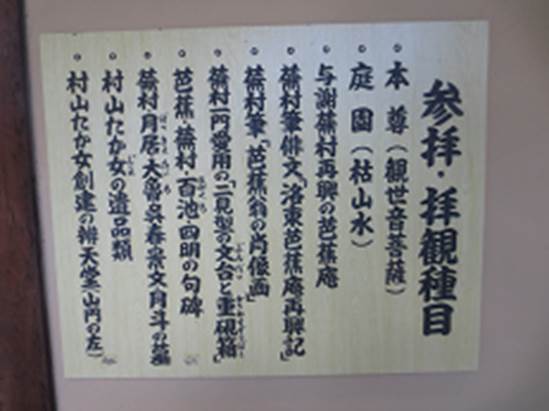
�������q�ώ�ڈꗗ
�܂��́A���̔m�Ԉ��ɁB

�m�Ԉ��R��

�������{��

�������{��

�������뉀�E���ɔm�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕悪����

�������뉀

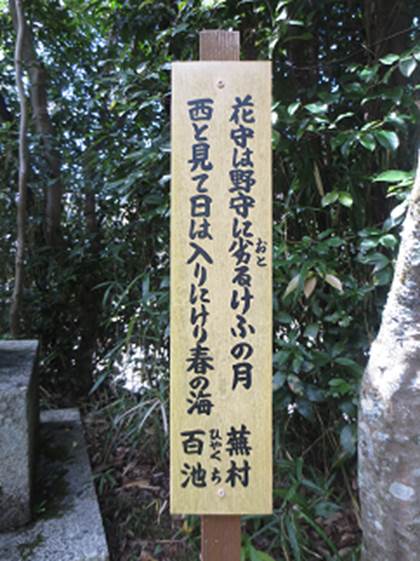
�^�ӕ����̋��
�^�ӕ����́u�Ԏ�͖��ɗ�邯�ӂ̌��v�̋�肪�B
�܂��́A�������A�{���̐��ω��l���Q�q�B

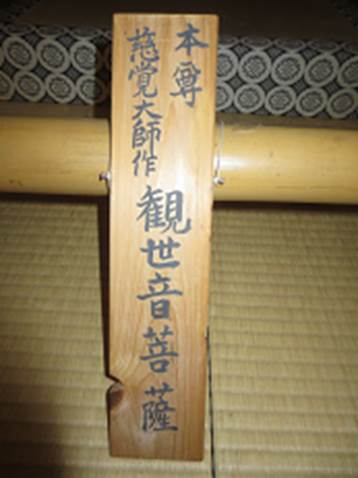
���̐��ω��������o��t�~�m���������Ƃ����B
���̂����̒��ɁA�^�ӕ����̈�i���������B
�܂��A�^�ӕ����̕`�����u�m�ԉ����v�B
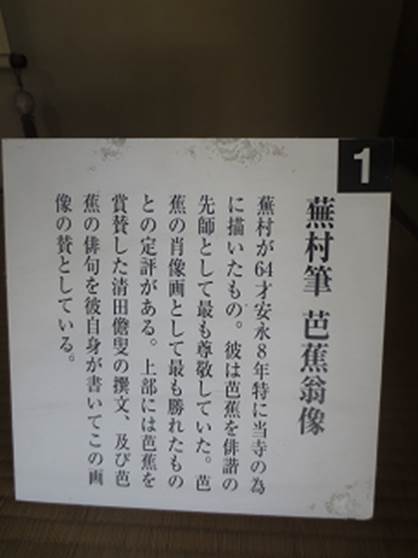

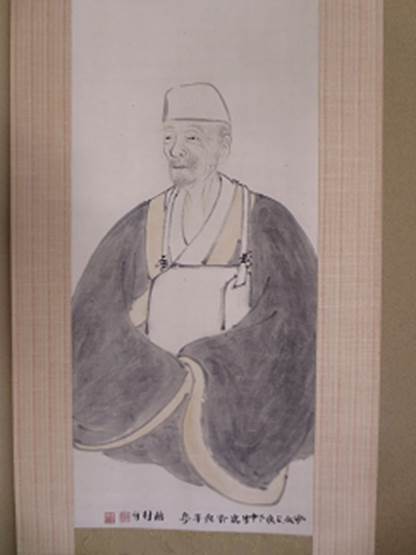
�^�ӕ����M�u�m�ԉ����v
���₩�Ȗ������������悤�ȟ��E�ȕ��͋C���Y���B
�^�ӕ����͑�ϐ[�����h�̔O�������m�Ԃɕ����Ă����悤���B
�����炱���A���̋������̔m�Ԉ����ċ������B
���̃��X�y�N�g�̎v�����A���̕����M�̏ё��悩��悭�`����Ă���B
�^�ӕ����i1716�|1784�j�́A�ےÍ��i���{�j���܂�ł���B
�����m�ԁi1644�|1694�j���ɉꍑ�i�O�d���j���܂�Ȃ̂ŁA����قlj������݂ł͂Ȃ����A���悻�m�Ԃ���70�قǔN���ł���B
�^�ӕ��������܂ꂽ�A1716�N�́A�������������狝�ۂɕς����N�ŁA7�㏫�R����ƌp�i1709�|1716�j���͂��Ŏ���������A�I�B�˂���g�@���}�����āA��8�㏫�R�ƂȂ����ϊv�̓s�s�ł���B
���̔N���炢����u���ۂ̉��v�v���n�܂����B��ɁA�������v�ƊJ���̑��i�ɂ��o�ψ��艻��}�鐭������s�����B
���̔N�A�����R�̐V�R�x�������Ă���B
���N�ɁA�ɓ���t�i1716-1800�j�����s�̋юs��̐����̑��q�Ƃ��Đ��܂�Ă���B
�܂��A���̔N�A�Ԕh�̓V�ˁE���`���ԁi1658-1716�j���S���Ȃ����B
����Ȏ���ɐ��܂ꂽ�^�ӕ����́A��ƂƂ��Ȃ肪�A�m�Ԃ�[�����h���A���s�������Łu�m�Ԉ��v���ċ������B
�����āA�o��̋ߑ㉻��}���������q�K�ɑ���ȉe����^�����B
��\��́A
�t�̊C�I���̂���̂����
�ĉ͂��z�����ꂵ�����ɑ���
�䂭�t�₨���������i�̕��S
���V�S�n��������ʂ肯��
���݂�����͂�O�ɉƓ�
�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���
�������Ȃ����̓V����
�������ł̍�Ƃ��ẮA
���ł⓮���ʉ_���Ȃ��Ȃ��
�ĎR��ʂЂȂ�ɂ��ዷ�l
�O�x�e�ĕ������Ȃ�ʎ��̐�
�~�߂����J�̉_��������肼
�Ȃǂ�����B
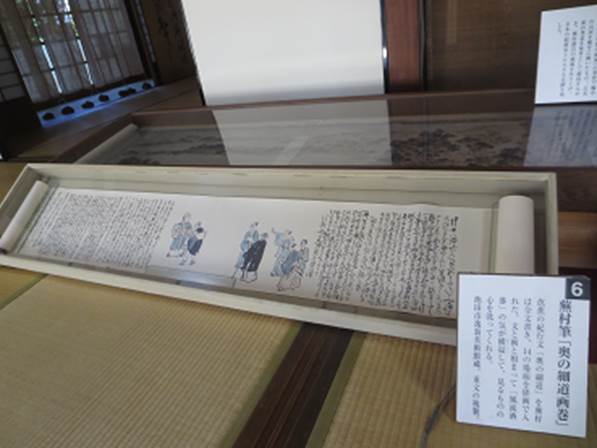
�^�ӕ����́u���̍ד��抪�v
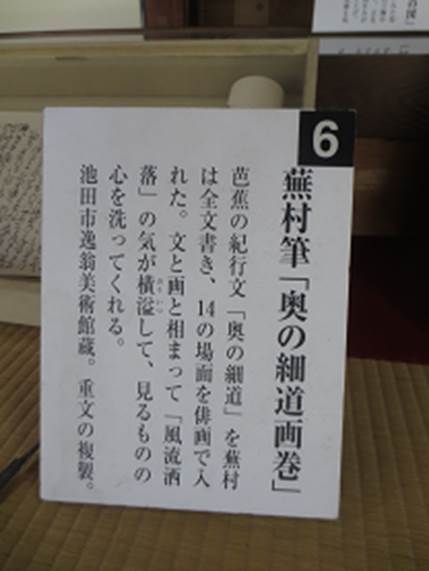
�^�ӕ����M�u���̍ד��抪�v

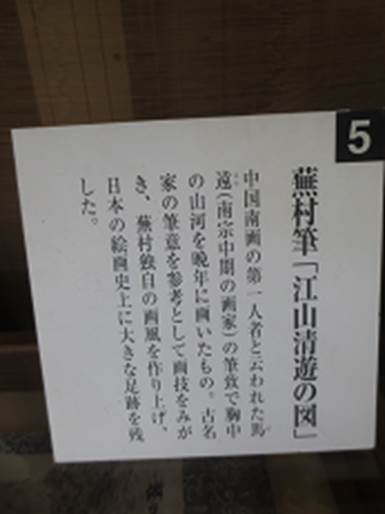
�^�ӕ����M�u�]�R���V�̐}�v

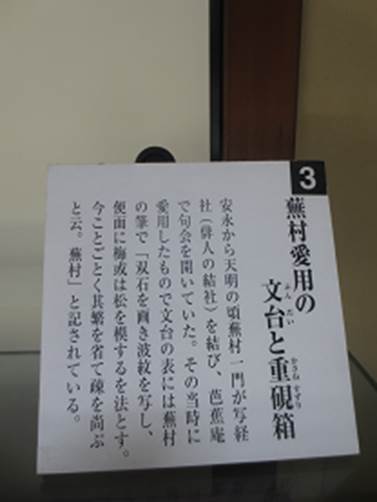
�^�ӕ������p�̕���Əd����
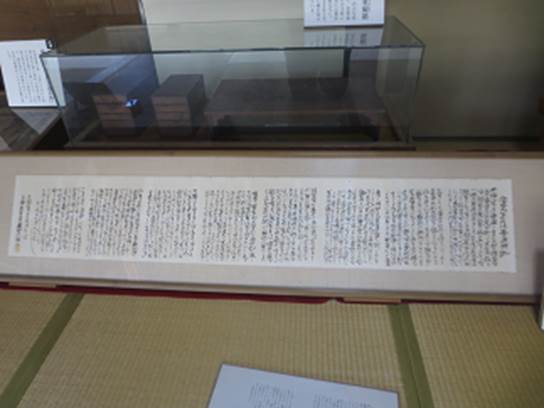
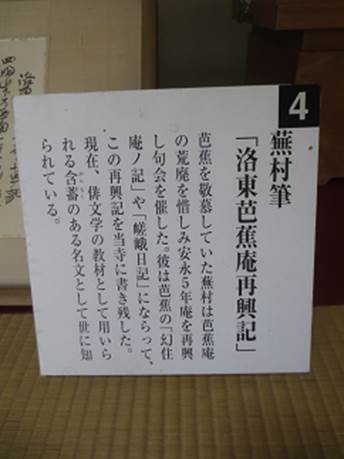

�E�������m�ԁA�����^�ӕ���
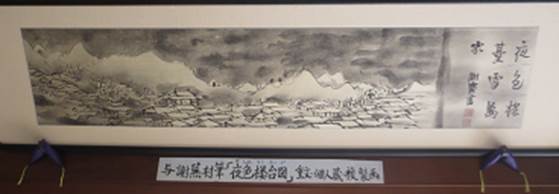
�{�������Q�肵�Ă���A�m�Ԉ��Ɍ��������B

�m�Ԉ��Ɨ^�ӕ����̕�̕\����
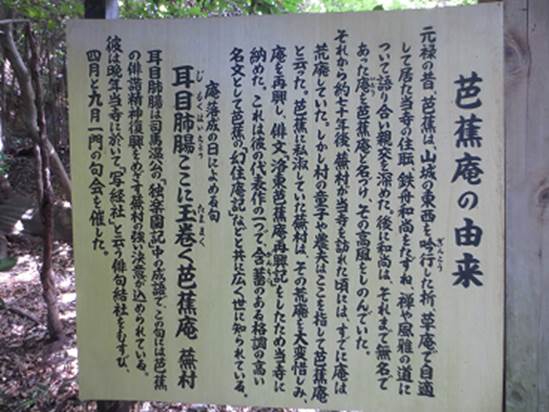
�u�m�Ԉ��v�R���̊Ŕ�
���\�i1688-1704�j�̍��A�m�Ԃ͎R��̍��̂��������ŋ�s���A���̒n�ŁA�����̏Z�E�̓S�M�a���ƌ𗬂����B
�S�M�́A���̌�A���̈����u�m�Ԉ��v�Ɩ��t�������A���ꂩ�炨�悻70�N��A�^�ӕ��������̒n��K�˂����ɂ́A���̈������ʂĂĂ����B
�����ŁA�����́A�u���Ƃ��Վ⌺�B�̒n�ɂ��āA�Αۂ��S�N�̐l�Ղ����ÂނƂ��ւǂ��A�H⹂Ȃو�ࢂ̒������ӂ��ނ����Ƃ��B���s���_�Ƃǂ܂�A���V������āA������ɉ��Â̏�Ɋ��ւ��v�ȂǂƁA�u�����m�Ԉ��ċ��L�v�����߂ď����グ�āA�ċ����͂������̂������B

�m�Ԉ�

�m�Ԉ�

�^�ӕ������m�Ԉ��ŋႶ���o��
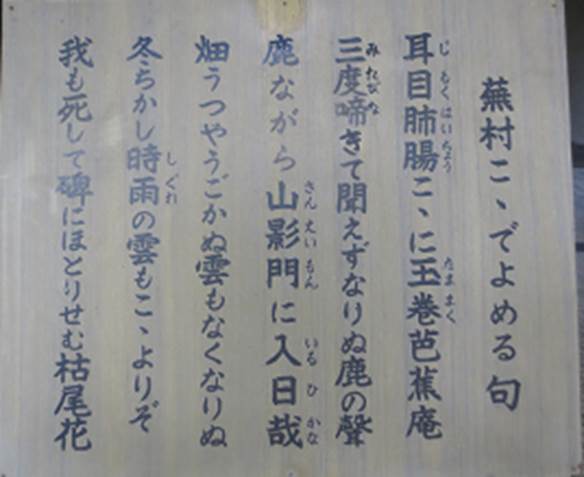
�^�ӕ������m�Ԉ��ŋႶ���o��
�M���ɁA
�u���ڔx�����T�ɋʊ��m�Ԉ��v
�����ɁA
�u��������Ĕ�ɂقƂ肹�ތ͔��ԁv
�̋傪�������Ă���B
�����̊o��̂قǂƎ����ς��Â��B

�m�Ԉ�
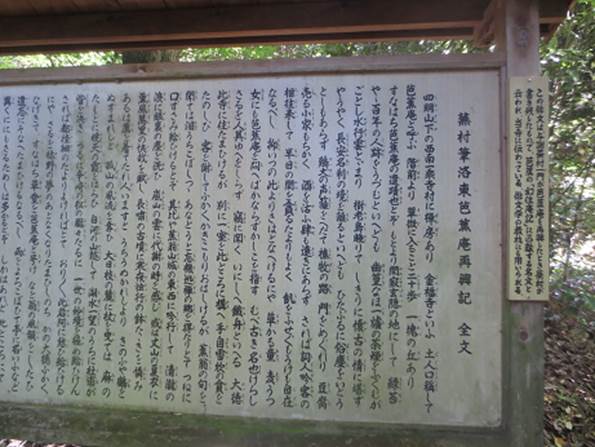
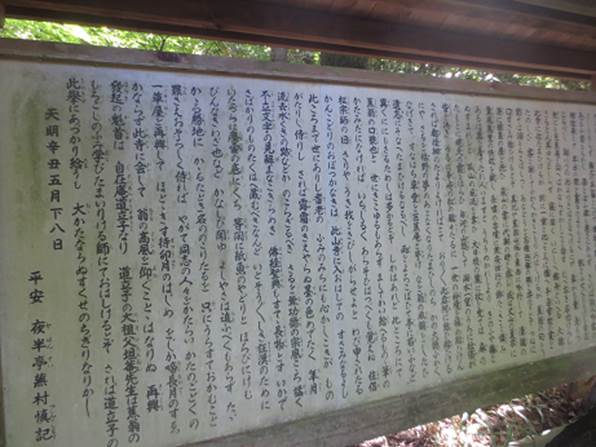
�^�ӕ����M�u�����m�Ԉ��ċ��L�v

�m�Ԃ̔�
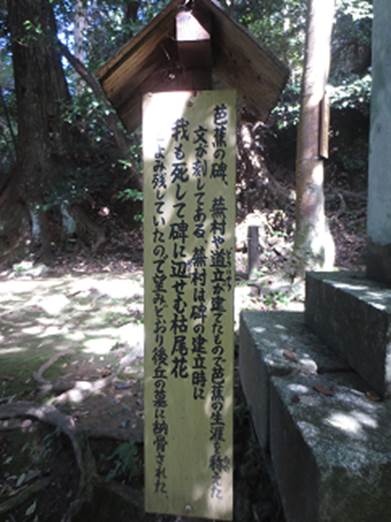
�m�Ԃ̔�̐����̊Ŕ�

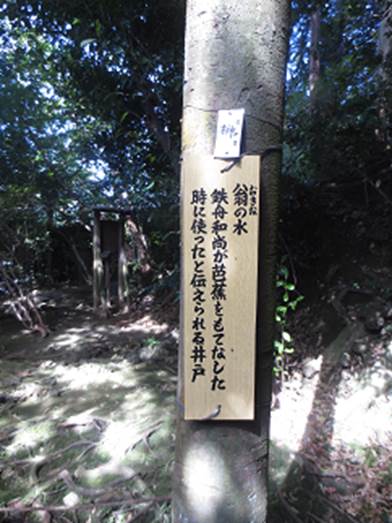
���̐�

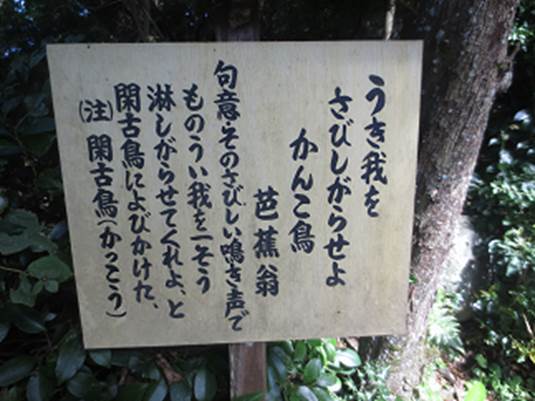
�u����������т����点�悩���v
�̋�B

�m�Ԃ̔�̏�����ɂ���^�ӕ����̕�

�����̕�̑O�Ŕʎ�S�o�������A�L�O�Ɉꖇ�p�`���B
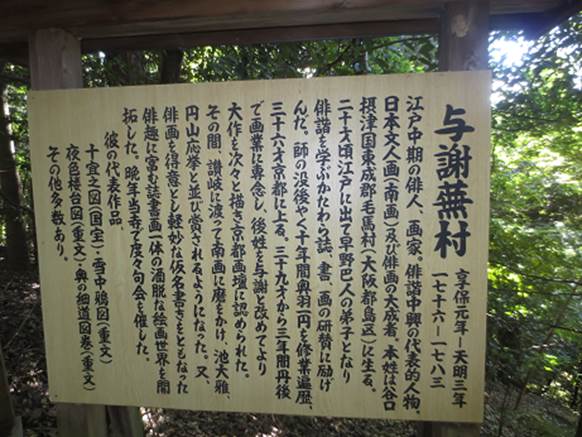
�^�ӕ����̗���
����ɂ���1752�N�A36���ɋ��s�ɂ���Ă��āA���炭�O��Ȃǂł���Ƃɐ�O�����Ƃ����B
�O��ɂ́u�^�Ӂv�̒n��������A����𐩂Ƃ���悤�ɂȂ����킯������A���ƒO��́A�����̔o��Ɖ�ƂɂƂ��āA�i�ʂ̒n�ł������B
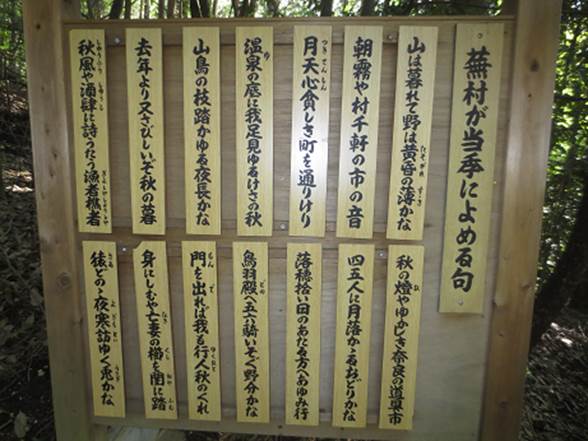
�^�ӕ����̋�
�^�ӕ����̋�́A�悭�G��I���ƌ�����B
�m���ɁA
���V�S�n��������ʂ肯��
���݂�����͂�O�ɉƓ�
�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐���
�������Ȃ����̓V����
�Ƃ��̋������ƁA�N���A�[�Ȉꕝ�̊G��������ł���B
�܂��A
�t�̊C�I���̂���̂����
�ĉ͂��z�����ꂵ�����ɑ���
�������ł���B
���A�Ⴊ�ƂĂ��D���Ȉ��A
�䂭�t�₨���������i�̕��S
�Ȃǂ́A�d���u���i�v������ďt�̏I���ɗ��Q���Ă���Y���S���A�����͂��ƂȂ����ݏo�Ă��āA�����ւ���L���ŁA���݂���̂�����B
�Ƃ��킯�ŁA�m�Ԃƕ�����S�ɕ����A�u���S�v�������āA15��15���A���̂܂܁u���v�ɏo��C�����ŁA���R�C�����o���B
��X�_�Зy�q�B�����āA��R�����グ��B
���ギ��@���u�̓V�@��R����

�{���̔�b�R
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B�_���ցB
�@�@�_���@����肫���Ɓ@�����뗎��

�{���̐X�̋��N

�{���̐X�̗d���N
�@�@�X�̃k�V�@���Εs�|�́@�Ӑg����

�{���̉���
�@�@����Ɂ@�����~�߂�ꂽ�@�g�t����

�i���͂�̓�
�@�@�i���͂�́@���[�������ā@�⒆�V

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l
�@�@�X�n���@�����O���Ɂ@�X�Ԃ���

�{���̞w��
�@�@�g�𓊂��ā@�w�т́@�C�ɒĂ�

�{���̂����u
�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B
�@�얳�قƂ��@�����u�́@��y����

�{���̐���R
�@�@�R�̉ʂā@��̉ʂĂ܂Ł@�����뉝��

�{���̔��i��
�@�@���i�̊C�@�V������ށ@�ʂ̌i���݁j

�����u�̌͂ꗎ���t
�@�@�͗��t�@�Ă��s����́@�݂قƂ���

�͂ꂷ����
�@�@�V�����@�͔��ԁ@����g��
�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�13��B
�@�@���Ԃ�@���ĉʂẮ@�F����

�{���̐X�̗d���N��2��
�@�@�X�[���@�����߂����̂́@������

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
�@�@���A�C���@���ʂĂʐ�́@���{�C

�{���̔���
�@�@�����Ɂ@�Ƃ炳�ꕂ���ԁ@�H���

�[�鎞�̉��H��
�@�@���炳��Ɓ@���H����@���o�̗�

���_�̂悤�ȕ������̗[�鎞�̉_
�@�@���_�Ɂ@���ēV�C�@�т���

�{���̍�X�_�Ђ̐_��
�@�@��X�́@�Ŕ�߂ā@������

�{���̍�X�_�Ђ̎Q��
�@�@�����f���@������̉ʂĂɁ@��������
���e���I
���ڎ�2
2016�N10��8���@�ؑ��͂�݁FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2
���c�搶
�݂Ȃ���
����̂����t���肪�Ƃ��������܂��B
�����܂��I�@�@�q���搶�A��낵�����肢�������܂��B
�F���܁A���Ђ��炵�Ă��������B
10��30���́A���c�搶�́A�����s�Łu�v���I�f�b�Z�C�@�|���́|�v�̏�f�ƃg�[�N���̂ł��ˁB
https://www.facebook.com/okieikenooshige/
���́u�v���I�f�b�Z�C�v�Ƒ�d�ēA��D���ł��B
�~�V�}�Ђł��q�����܂������A���̉f��͉��x���Ă��O���܂���B�f���炵���f��ł��B
���c�搶��������Ă��������B
����ƂȂ�܂��悤���F�肢�����Ă���܂��B
�w��E�|�p�̏H�̓C�x���g����������ł��ˁB
���炾����������������̂ł����A�A�A�B
�ł́A���ӗ₦�Ă܂���܂����B
�F���܁A���g�̂ɂ͂��ꂮ��������ӂ��������܂��悤�B
�ؑ��͂�݁��R��

���ڎ�2
2016�N10��8���@���c����FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2
�q���N�l
�ؑ��͂�ݗl
�݂Ȃ���
�u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�v�A��ϋ����[����r�����ł��B
�g�S�ϗe�Z�@�����̏d�v�����r�����ł��B
���̂悤�ȗL�Ӌ`�ŋ����[���������ǂ�ǂ�E����E���i�߂Ă��������B
��낵�����肢���܂��B
�݂Ȃ���
���s�������܂�����A���m�F��U�����킹�Ă��Q�����������B
�P�O�E�W�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��7���@�ؑ��͂�݁FRe�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2
�q���搶
�݂Ȃ���
�ȉ��A�I�C�����g�~�X�g�̍���T�q����̂g�o�ł��B
��낵�����肢���܂��B
http://jade-initiative.net/bodywork.html
------------------------------
Jade Initiative ����T�q
jade-initiative.net

Jade Initiative ��14�N�̃h�C�c�ݏZ�o�������ăh�C�c�Ɠ��{�̕����𗬂̂��߂ɍv�����鍁��T�q�̃T�C�g�ł��B
------------------------------
�ؑ��͂��
���ڎ�2
2016�N10��7���@�q���N�F�l�̉Ȋw��T�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�i10��30���j�̂��U���@�@���ڎ�2
�g�S�ϗe�Z�@������̊F�l
�䕗���߂��邽�тɗ������Ȃ�܂��ˁB
�g�S�ϗe�Z�@������ł����b�ɂȂ��Ă��܂��q���ł��B
�������ɋ��s�ŊJ�×\��̃Z�b�V�����u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�̂��U���ł��B
��N�x���A�ؑ��͂�݂���Ǝ��𒆐S�ɁA�l�̉Ȋw��T�������J�Â��Ă��܂��B���N�x�́A�u���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[�̌𗬁v�Ƃ����e�[�}�ŁA��̐g�̋Z�@�̗��_�Ǝ��Z�̗��ʂɂ킽��Z�b�V��������悢�����܂����B
���m�Ɛ��m�A���p�ƕ\���A���ꂼ��܂������Ⴄ�g�̕����͂ǂ̂悤�Ȑړ_����������̂ł��傤���B�ϔO�_�I�Ȕ�r���ׂ肪���ȓI�}�������z���A�g�̋Z�@�ɒʒꂷ����̂�͍����邱�Ƃ͉\�ł��傤���B��̐g�̕������Q���҂݂̂Ȃ���ɂ��̌����Ă��������āA�����ݏo����悢�Ǝv���܂��B
�I�C�����g�~�[�����w�����������̂́A�ؑ�����ɂ��Љ���������I�C�����g�~�X�g�̍���T�q����A���Ɍ���S������͎̂��ł��B���Ɍ��ƃI�C�����g�~�[���ꂼ��ɂ��āA�ȒP�ȗ��j�Ɨ��_�̉���ƁA���Z�w������ё̌����������ƍl���Ă��܂��B�X�P�W���[���Ƃ��ẮA�O����Q���ԂɌ��A�㔼��Q���Ԃ��I�C�����g�~�[�A�Ō�ɑ������_�̎��Ԃ��Ƃ肽���Ǝv���܂��B
�����ȂǏڍׂ͎��̒ʂ�ł��B
���� : 2016�N10��30���i���j�@13 :00�`18:00 �i�J��12:30�j
�ꏊ : �b���Ј�掛�X�R�e�[�W
�@�@�@�i���s�s�������掛���a��10�j
�A�N�Z�X�Fhttp://www.cottage-keibunsha.com/access.html
�t���C���[��Y�t�������܂��B�l���c���̓s����A���o�Ȃ̏ꍇ�͑��߂ɂ��m�点����������Ώ�����܂��B
�q���N�q
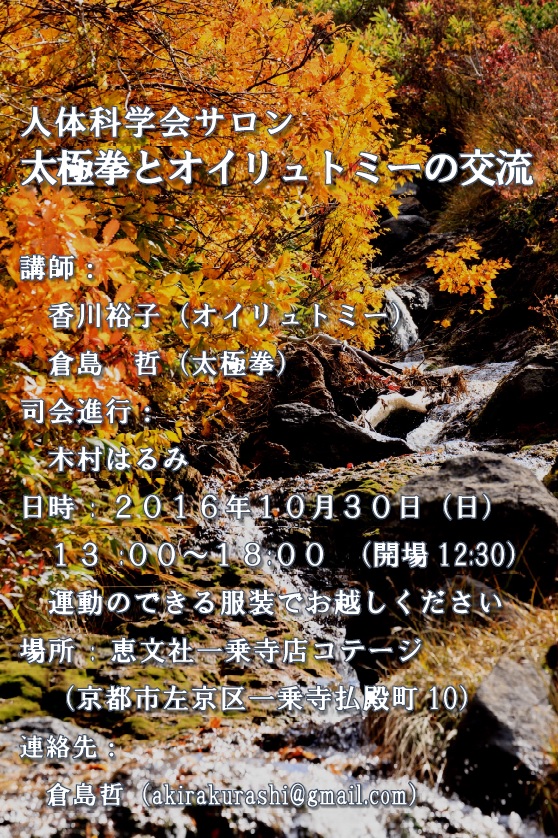
���ڎ�2
2016�N10��5���@���c����FRe�F10��14��(��)���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v�@�@���ڎ�2
���V����l
��ϋ����[���Â��̈ē��A���肪�Ƃ��������܂��B
�S�̂���F����́A���Ђ��Q�����������B
���̓��i10��14���j�̖�́A�͑��\����2�K��18������20���܂ŁA�����팤������J�Â��܂��B
�u�_���K���v�A�|���������\�ł���I
�P�O�E�T�@���c����q
���ڎ�2
2016�N10��5���@���V����F10��14��(��)���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v�@�@���ڎ�2
���c�搶�A�g�S�ϗe�Z�@������݂̂Ȃ���
�����b�ɂȂ��Ă���܂��B
���J��w�̓��V����ł��B6���̌�����Łu����F��̐S�쌤���Ɛg�S�ϗe�̌��v��
���Ĕ��\�����Ă��������܂����B
���̓x�A����F��֘A�̂��m�点������A���A�������Ă��������܂����B
���N(2017�N)1��22��(��)�ɁA���J��w���E�������������Z���^�[�w�p�u����u�،�
�̐��E�\�w�،��o�x�Ɠ���}���_���\�v���J�Â���܂��B������w�쐶�̉Ȋw������
�Ƃ̋��ÂŁA����V��搶�����Ăт��ċ��s�z�[��(���s�w�������o�Ă���)�ŊJ�Â�
��܂��B���V���R�[�f�B�l�[�^�[���Ƃ߂����Ă��������Ă���܂��B
�ȉ��A���̊֘A���N�`���[�ł��B
���J������u����F��Ƃ͉��҂��H�v
�E�����F10��14��(��) 13:15�`14:45
�E�ꏊ�F���J��w�[���w�ɃA�N�e�B�r�e�B�z�[��
�E�u�t�F���V����
�E��ʗ������}�A���ꖳ��
http://rcwbc.ryukoku.ac.jp/activity/meeting
�F��Ɋւ��鏉���I�Șb(�F��̐��U)������\��ł��B
�����̂����ɂȂ�܂����A�������S������܂�����A�ǂ������u�ɂ��z���������B
��낵�����肢�\���グ�܂��B
*******************************
���J��w
���E�������������Z���^�[(���ی�������)���m������
���V����(Taisuke KARASAWA)
*******************************

���ڎ�2
2016�N10��3���@���c����F�����V��10��3���t�L���u���V�A�ł̔��s�ƌÎ��L�v�@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�����V��10��3���t�L���u���V�A�ł̔��s�ƌÎ��L�v�������肵�܂��B
����ǂ�������K���ł��B
�P�O�E�R�@���c����q
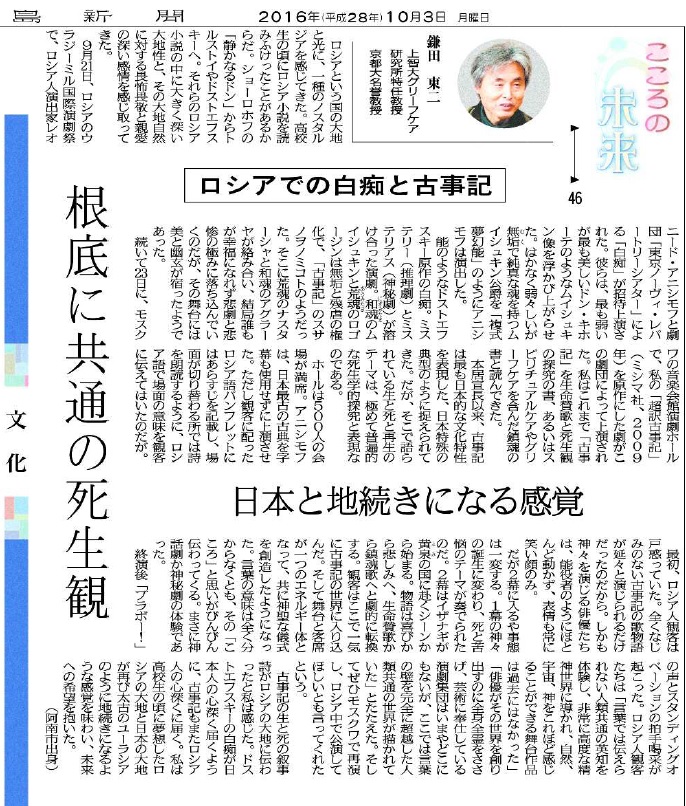
���ڎ�2
2016�N10��2���@���c����F���R�C�����R�V�U�@�@���ڎ�2
2016�N10��2��
�����͓��j���B�����B30�x���Ă���Ǝv������A���s��32�x�̐^�ē��ɂȂ����B
�Ƃ͂����A�H�̎c�����B�ȂɁA���܂����̂��B
15��20���A���R�C�����o���B
�o��O�ɁA�����͎ւɏo��悤�ȋC�������B
�ƁA�o�������r�[�A���[�Ɏւ�����ł����B
�������������B

�ւ̎��[
1���[�g���ȏ�͂���B��ő��a�ɗ����āA�얳����ɕ��Ə�����B
��X�_�Зy�q�B
���R�����グ��B

�{���̔�b�R
���₩�Ȕ�b�R�̎R�e�B
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B�_���ցB
�܂��R���͊������Ă��Ȃ��B
�����܂������B
�ʂ���݂�����B
�����Ƃɂ���낿���ƁA�ւ��B
�q���̎ցB
���x�́A10�Z���`���邩�Ȃ����B
����䂢�B
���ł��A�q���͂���䂢�̂��B

�{���̐X�̋��N
�X�̋��N�͂܂��������Ă��Ȃ��B
�����ԔG��Ă���B

�{���̐X�̗d���N
�X�̗d���N�́A�h���C�B
��������B
���݂��̂��̂��������Ȃ̂����B

�{���̉���
����̌������͐���ԁB
�����A�i���͂�̌������́H

�i���͂�̓�
�_�s���������E�E�E

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
���グ�郂�A�C�N�́A�z�C��炵�ς炸�B

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l
�X�����n���l�̑O�X�p���Ƌً}�~�Ϗo���Ԑ��ς�炸�B
�����ˁA���̎p���Ɛ��_�B
�����A�����V����ǂ�ł��āA���]���́u���҂ɉ�����v�̃R�����ɓ��V�{�q���̋L�����o�Ă����B
Wikipedia�ɂ́A���V�{�q����̋L���͂����o�Ă���B
------------------------------
���V �{�q�i�������� ����A1967�N3��16�� - �j�́A���{�̃C���X�g���|���C�^�[�A�����ƁA���{�ƁB
�ٕ����A���z�A���ЁA�j�{�Ȃǂ��e�[�}�ɁA���{�e�n�E���E�e���𗷂��A�k���ȉ�͂������C���X�g�E���|���^�[�W���������B
�_�ސ쌧�o�g�B���{�@��{���w���N�w�ȑ��ƁB��w���ƌ�A�ҏW�҂��u�]�������o�ŎЂɍ��i�����A��ʊ�Ƃ�OL�ɂȂ�B��w�̉��t�̊��c����G���̕\���C���X�g�𗊂܂ꂽ���Ƃ����������ɁA1992�N����C���X�g�̎d��������悤�ɂȂ�B1997�N����A�G���w�{�ƃR���s���[�^�x�ŁA�ҏW�ҏ��c�N�v�̘A�ځu����ɗ����āv�̃C���X�g���|��S������B�������ɑ����̎d�����n�߂�B1998�N�A�u����ɗ����āv�̕ҏW�S����������ɘO���ɂƌ����B�����̋�����Ƃ��s���Ă������A2011�N�ɗ����B
�{�c��ȁA����G�s�Ɓu�G���^���m���t���|���v���������Ă���B
����
�w�Z���Z�C�̏��� �C���X�g���|�u�{�v�̂���d����x���Y���[�@2006�N5���@ISBN 4901998161
�w���E�j�{�I�s�x����o�ŎЁ@2007�N1���@ISBN 4759251332
�w���₶�����\��Ŋ뜜�풆�N�j���}�Ӂx�ɂ�o�� 2008�N11�� ISBN 4931344224
�w�g�̂̂����Ȃ�x�@�����V���o�ŁA2010 - ��27��u�k�ЃG�b�Z�C���
�w�����@�O�C�̓Ƃ킽���x��g���X�@2012�N2���@ISBN 9784000258364
�w�Y���܂܂ɓ��ɒ����x �����V���o�Ł@2016�N8��
����
�w�V�q���̌��z�p �Q���̃R�X�����W�[�xINAX�o�� 1993�N09��
�w�J�i�f�B�A���T�}�[�EKYOKO�x�i�������߂����ő}�G��S���j ���_�� 1994�N1��
�w�������邫������ �ۂ��_����x�i�������ꂪ���ő}�G��S���j���k�� 1994�N4��
�w�������֘^ �u���̏o���l�X�v���猩���A�W�A �x�i�ē����삪���ŃC���X�g��S���j���w�� 1998�N5���i�̂����t���Ɂj
�w����ނ�܂����̂������X�x�i�������߂����ő}�G��S���j ���_�� 1998�N6��
�w�A�W�A�H�n���I�s�x(����T���E�ҁj���ԏ��X 1999�N10��
�w����ɗ����āx�i���c�N�v�����ŃC���X�g��S���j�����Ё@2001�N12�� - ��3��Q�X�i�[�܁u�{�̖{�v��������
�w�u�{�v�ɗ����āx�i���c�N�v�����ŃC���X�g��S���j�V���Ё@2006�N2��
�w�Ӌ��̗��̓]�E�ɂ�����x�i����G�s���A����Ƃ̑Βk�����^�j�{�̎G���� 2008�N6��
�w�������֘^�x�i�ē����삪���ŃC���X�g��S���j���Y�t�H 2009�N3
�O�������N
���V�{�q�@���I�G���L - �u���O
��M�嗤�E���V�{�q
------------------------------
���V�{�q����́A25�N�ȏ�O�A���u�t�����Ă������A���{�@��{�ŌႪ���������Ƃ̂���w���������B
�u���{�ϗ��v�z�j�v���������̌Ⴊ���Ƃ̍ŏI���A���d�̊��ɁA�z�Ƃ�����֑}���̉Ԃ������Ă������B
��ɂ���ɂ��A����ɂ��̂悤�Ȗ��Ȑ^�������Ă��ꂽ�̂́A���̎�����̎��������B
�����u���Ă��ꂽ�̂����V�{�q�������B���U�Ɉ�x�����A������̖Y����Ȃ��z���o�Ȃ�B
���q�ɏZ��ł����ޏ��̊����͂Ȃ��Ȃ��s�����j�[�N�ŁA�����납�����B
�t�[�e���̌�Ƃ͂ǂ������Ă�Ƃ��낪����悤�ȁA���ɐ�����Ĝf�r���悤�ȕ�����������B
���ɐ�����āA���E���̓j�E���������āA����C���X�g����I�s�G�b�Z�C�w���E�j�{�I�s�x�������āA���f�B�A�ɒ��ڂ��ꂽ�B
���V����́A�Ⴊ�t�͂����Ă���w����o��x�i�p�쌹�`�n�݂̓`������o��G���j�̕\����S�����Ă��ꂽ�B
�N�₩�Ȑ�G�f�U�C���B
���̍��A�Ⴊ�ւ�������{�@��{�̊w���ŁA���f�B�A�Ŋ��Ă����\�i���A�o�l�̖x�{�T���N�ƃG�b�Z�C�C�X�g�̓��V�{�q����B
���E�𗷂��A��t�ɓ��ďZ�݂��A�����{��k�Ќ�́A�������ɕY���������Ƃ����B
�������ɂ͍s���������A������B
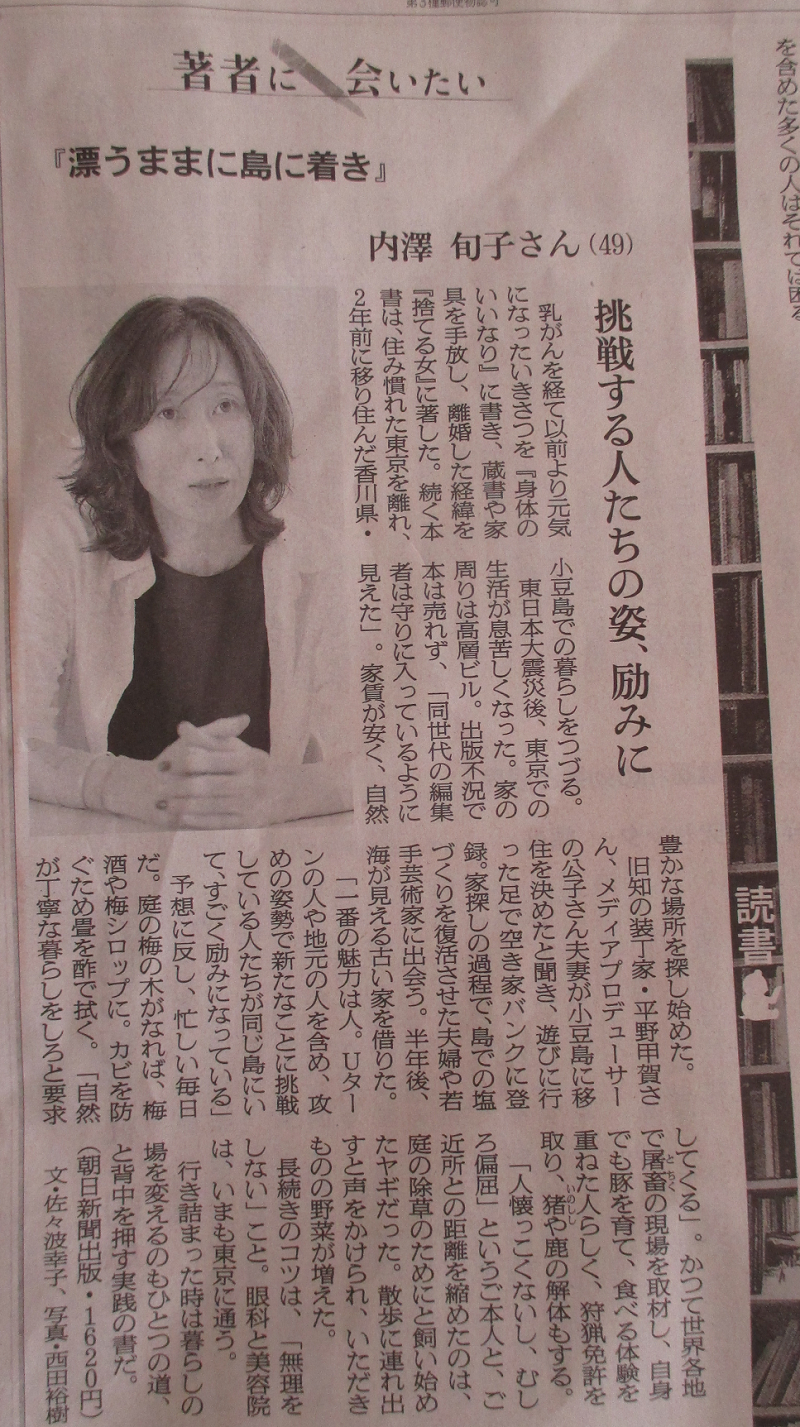
2016�N10��2�������V�������L��
����́A�B��̓��̒��m���C�m���̋L�����ڂɕt�����B
�����č����A�������ɗ��ꒅ�������V�{�q����̋L�����ڂɕt���B
�^�C�~���O���悷����B
�������B
���̖����B
�����疢���������Ă���B
�����猻�݂̖�肪�����Ă���B
��Ԃ̖��́A�u�T�C�Y���v�B
���͂ǂ̂悤�Ɂu�g�̏�ɍ������������v���ł��邩�H
�u�g�̒��m�炸�̐������v�����Ă����j���Q�����A�u�g�̒��v��m���āA�u�g�̒��v��ق��āA�܂����Ɓu�g�̏�v�ɉ��������������ł��邩�ǂ����B
���ꂪ����A������Ă���B
�u�v���I�f�b�Z�C�v�O����̑�d����Y����́A�u1���x��̃g�b�v�����i�[�v�Ɠ��̐����������Ă����B
�����āA������v�������h�L�������g����O����ɋL�^���A�̂����B
�f���������u�v���I�f�b�Z�C�v�Ƃ��āB
������̈�u�������p���ŁA���̗쐫�ƕ������@�艺���˂B
���u���v�炿�̉��Ԃ�����킢�B
����ǂ��A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ł���ł́`�B
�u�g�̒��v�m�炸�Ȑ����������ł����B
�t�[�e���̃g�E����́B
���ߑ������Č��グ��B
��ɋz�����܂��B

�{���̞w��
���̐g�̒��m�炸���B
����[�Ȃ��́`�B
���ꂼ��̍D���Ȑ����������ł���ł́`�B
���R�C�����ł��̂��Ƃ��v�������Ƃ�킢�B
�j���Q����y���ɒ�������R���n�Ɏ��B����āB
���肪�Ƃ��������܂��B
�����B

�{���̂����u
�����u�̂��n���l�̑O�Ŕʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B

�{���̐���R
���i�́A�N�p�͉_�Ō����Ȃ��B
�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�ł�Ԃ�12��B
���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��

�{���̏C�w�@
��������̂������B
�C�w�@�̘[�ɒ�������A�^���ÁB
��X�_�ЎQ�q�B���q12�q�B

��X�_�Ђ̐_��
�_���ɏƖ���������B
�H����~�ɂȂ�̂������낤�B
���͉߂��䂭�Ȃ�B

��X�_�Ђ̎Q��
�Q���̌������ɉ�������H
�d���ΉA�������郂�m�́H
�얳�T���{�E�I
���ڎ�2
2016�N10��1���@���c����F���R�C�����R�V�T�@�@���ڎ�2
2016�N10��1��
���̂Ƃ���A���������J���������B�֎�@��̉J�ʂ������B�쉹�ł킩��B
�������J���~�����B
���A����Ԃ��o�Ă��āA���̌�܂��ɕς������A�G�C���b�A���̋@����Ă͂Ȃ炶��15��15���A���R�C�����o���B
��X�_�Зy�q�B
���R�����グ��B
���������B

�{���̔�b�R
���₩�Ȋ����B
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B
�֎�@�ٓV�r�̐��ʂ͖L���ŁA�����Ă���B����T�`�����I�X�Ɖj���ł���B
���Z�~�i�[�n�E�X�̘e�̗т̒��̐��H�̐��������I

���Z�~�i�[�n�E�X�k���̐��H
���������ŁA���ʂ̑������B

���H��̉�
���H��̉���̉��������n���Ă���B
�_���ɓ���B

�ŃL�m�R�H
�H���ˁB���������ɍg���L�m�R���B
�����ǁA����́A�ŃL�m�R�H
�N�₩�Ȕ���Ԃ̃L�m�R�ɂ́A������ƓŁX����������̂��B
�R�����G��Ă��āA�Ƃ���ǂ���A�����܂��ʂ���݂��B

�{���̐X�̋��N
�X�̋��N�������炸�Ԃ��ƔG��Ă���B

�{���̐X�̗d���N
�X�̗d���N���G��Ă͂��邪�A�������A���̔G��͔ނ̓Ɠ��̂ʂ߂�ƂȂ��Č��������Ă���B�|��Ă��Ȃ��B
�����I�@�s���g�I

�{���̉���
����̔������ꂪ����悭������悤�ɂȂ��Ă����B
�z���g�A�H���[�܂��Ă���̂�������B
���̌��ʂ�������悭�Ȃ��Ă����̂ŁB
�^�Ă͗̑��g���ז����ĉ���̔�������������Ȃ��قǂ������̂ɁB
���ł́A�����ԁA�ڎ��ł���B

�i���͂�̓�
�i���̖��G��Ă���B

�i���͂�̎���
�\�ɉ���āA�ؔ��ɃJ�r�̂悤�Ȃ��̂������Ă���̂��m�F�B
����L�����Ă���B�ہH

�{���̐X�̃��A�C�N
���n�̔w�̐�̐X�̃��A�C�N���A�G��Ă͂��邪�A���傤�ǂ悫���������B

�{���̐X�̃��A�C�N
���グ���ɂ́H

�{���̐X�̂��n���l
�X�̂��n���l���O�X�p���A�������A�悩�`�I

�{���̐X�̂��n���l
���ʊ���ǂ����肩�܂��Ƃ�킢�B
�����A�V����ǂ�ł�����A�B��̓���I�^�[�����ċN�Ƃ��Ă����҂́u�����疢��������v�Ƃ����L�����傫���f�ڂ���Ă����B
�B��̓��̓��O�̒��m���̊C�m���Łu������Ё@���̊i�߂���̂�j�v���^�c���Ă����\������Œn��Â���E���玖�ƃv���f���[�T�[�̈����T�u����B
�����T�u����͈��Q���V���l���܂�̈��m�����É��炿�ŁA���s��w�H�w���A����w�@�H�w�����Ȃ��C��������A�g���^�����Ԃɓ����āA���Y�Z�p�G���W�j�A�Ƃ��āu���E�ő��̖��l�����C���v�̐V�Ԏ�̊J���ɏ]������B
�u158���镔���̒��ōł��Z�����A��肪��������Ǝv���Ă����B
�x���͎��R�̒��ɏo���B
�}�E���e���o�C�N�ɏ��A�w�����y���������x�ƉƂɋA���ăr�[�������ށB���̂Ƃ��A���܂��ĕ����Ԃ̂����̌��t�������B
�w�ŁA����ł����́H�x
�������������炢�A�V�Ԃ��߂����ɓc�ɂɍs���B
���O�͂���ł����̂��A�ƁB
�Q�l���ォ��l�Ǝ��R�A�Љ���l���Ă����B
�w�����\�ȎЉ�x��T���Ă����B
���傤�ǂ��̂���A���m����m�����B
����ŊC�m���Ƃ��������̂������Ă����B
���߂ĊC�m�ɗ����Ƃ��A�����ɏZ�ނƒ��������B�v
�����āA�����T�u����́A2007�N12���ɁA�g���^�����E���A2008�N1���ɈڏZ�B
�u�J���[��1�䂪50�b�łł���w���������C���x�̊������ゾ�����B
���ԂƊ�����Ђ�ݗ����A�c�Ƀx���`���[�ƒ�`�����B
�Ж��́u���̊i�߂���̂�j�v�B
��낤�Ƃ����̂͂�����̖��������邱�Ƃ������B
�q���g�́A�C�m�Ƃ����Љ�̏������ɂ������B�v
�������āA��������́A�u����Љ�݂̍���ɋ^�������A�V�����������̊m����ڎw���ē���4�N�ڂőގЁv���A�u�����\�Ȗ��������čs������l�Â���v��ړI�ɉ�Ђ𗧂��グ���̂ł���B
���̌�A2011�N4������́A�C�m���̋���ψ��ɂ��A�C���Ă���B
�u���̊v�̑�\���A�ɂ͎��̂悤�ɂ���B
http://megurinowa.jp/2000/post-11.html
�����Љ�͗h�ꓮ���Ă��܂�
�������͂ǂ�������K���ɕ�炵�Ă�����̂ł��傤��
�Y�݂Ȃ��琶���Ă��邤���ɗl�X�ȏo�������
�P�̍l���Ɏ���܂���
���ƂłȂ��Ă��A�s��łȂ��Ă��A
�n��ɍv���ł���d�������Ȃ���
�n��̕��X�ƂƂ��ɐ������y���݁A
���S���S�Ȃ����������̂�H�ׂȂ���
������Ɖ҂��ŁA�Ƒ��ƍK���ɕ�炷
����Ȑl������������A��ꂫ��������Љ���A
�����ƕ�炵�₷�����̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤��
�S���ɂ��铯���z�������������Ԃ�����
�C�m�̕��X�ƁA�ꏏ�ɍl���s�����Ȃ���
�������͊C�m�ŕ�炵�Ă����܂�
������Џ��̊@��\������@�����T�u��
��̓I�ɂ́A3�̗��O���𗧂ĂāA�u�������B�E�C�m����Ɂw���ꂩ��̐V�����������x���w�Ԋw�Z�Â���v�ȂǂɎ��g��ł���B
�@ �C�m�������ꂩ��̎Љ�̃��f���ƂȂ邽�߂́u�n��Â��莖�Ɓv
�A �Љ�̃��f���Ƃ��Ă̊C�m������w�Ԃ��߂́u���玖�Ɓv
�B �C�m���Ŋw���Ƃ��Љ�S�̂ɓ`���邽�߂́u���f�B�A���Ɓv
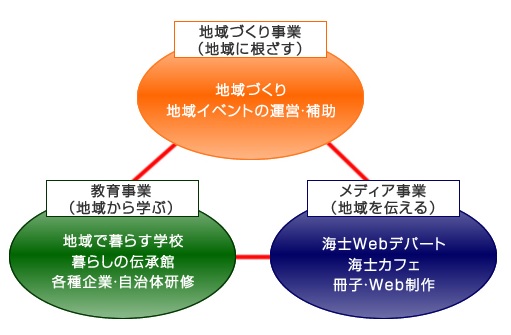
�����āA�����T�u����́A���A�u���ɑ�w�@������v���Ƃ�ڎw���Ă���Ƃ����B
�u�C�mMCA��w�@�v��n�邱�Ƃ��B
����́A�uMBA�v�A�܂�A�u�o�c�w�C�m�iMaster of Business Administration�j�v�̑�w�@�ł͂Ȃ��B
�u�����\�ȃR�~���j�e�B�Â���v���w�Ԃ��߂́uMaster of Com��unity Administration��MCA��w�@�v�B
���₠�`�B
�܂�������`�B
���ꂽ��`�B
�����Ӗ��A�u���Ȋ����ŁA���̋L�����~�߂܂����B
���́A��́A2004�N����2007�N�܂ł��̊C�m���ŁA���s���`�|�p��w�́u�������_�v�Ƃ���2��3���̌��n���ƍs�Ȃ��Ă����̂������B
�C�m���́A���s���`�|�p��w�̓��R���������̌̋����������Ƃ�����A���N�����Ƒ�w����̘A�ւŁA���Ƃ�A�[�e�B�X�g�E���W�f���Xin �C�m������낤�Ƃ��A���̐�ڂƂ��Ď��Ƃ��n�߂��̂������B
�R���C�m����������ɂ�������A�C�m������𗬑��i�ۉے��̐R�x��������ɂ����x��������āA�ł����킹��������A���͂������������肵���̂������B
�ႪHP�́u���[���T���g���^�[23�M�v�i2007�N7��29���L�j�ɂ́A���̂悤�ɁA�R����������̒����̏Љ�L���������Ă���B
http://homepage2.nifty.com/moon21/shinsletter.html
���B��̓��O�̒��m���͊C�m��(���܂��傤)�ƌ����܂����A���̊C�m���́A���s���`�|�p��w�̑n���ғ��R�ڒ��������̏o�g�n�Ȃ�ł���B����Ȃ��Ƃ������āA�C�m���Ƒ�w�����Ƌ��͂Ȃǂ�ʂ��Č𗬂�[�߂Ă��܂��B�킽�����S�����Ă�����Ɓu�������_�E�B��v�����̈�ł��B
�@�C�m���́A���������̉�����40�`60km�̓��{�C�ɕ����ԉB��Q��180���܂�̓��̈�ŁA�L�l���͓��O�R���A����P���̂S���B���O�R���Ƃ͒��m��(�C�m��)�Ɛ��m���i���m�����j�ƒm�v���ł��B��R�B�������Ɋ܂܂��C�m���̐l���͖�2,500�l�B
�@�S�N�O����R�����Y�����ȉ��A������E����c���̋����T�`�R���J�b�g�𑱂��A���������Ƃ��ē������Y�Ƃ��N�Ƃ��A���������ۂ��A�����܂œƗ��ƕ��̓����т��A�u�����܂邲�ƃu�����h���v������j���f���A�@�T�U�G�J���[�A�ACAS�ɂ���K�L�A�B�V�R���A�C�B�A�Ȃǂ̂��̂Â���Ɏ��g�ݑ傫�Ȑ��ʂ��グ����܂��B���̐V�������z�Ƒn���́A�u��ҁv�Ɓu�n���ҁv�Ɓu�悻�ҁv���Ƃ������Ƃł��B
�@�R�����Y��������͐挎�ANHK�o�ł̐����l�V���Łw�������@�����c�邽�߂̂P�O�̐헪�x�Ƃ����{���o���܂����B�����ŁA�R������́A�u�Ō������Ő�[�ցv�A�u����������{��ς���v�Ƒi���A�u�������̌��́w�𗬁x�v�ŁA�u�w��ҁx�w�n���ҁx�w�悻�ҁx������Β��͓����v�Ǝ咣���Ă��܂��B�킽���́A����A�V�c���ꕛ�������炱�̖{�����������ēǂ݂܂������A�����ւ�ʔ����ł��B�o�c�҂Ƃ��Ă̈�������v�Ԃ���̎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂�����A���Ђ���ǂ��������B�܂��A���Ў���ɂ����߂��������B�B��͐�����I��
���ꂪ�A�قƂ��10�N�قǑO�̘b�B
������������̂��A2007�N7��29�������A���̍��A���Ԃ�A�����T�u����́A�C�m���ɈڏZ���錈�S�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H
�����āA2007�N12���Ƀg���^��ގЁB�����āA2008�N1���Ɋ�����Џ��̊�ݗ��B
���̊C�m���́A�Ñ�Ɂu��H���E�C�m�i�݂����ɁE���܁j�Ƃ��āA�m��ꂽ�B
�Ƃ����̂��A���鋞�Ղ���C�m���́u�����A���r�v�������コ��Ă������Ƃ������؊Ȃ����@����Ă���̂��B
�܂�A�ޗǎ��ォ��A�C�Y���̕�ɂƂ��āu��H���v�̈�Ƃ��Ė���m���Ă����Ƃ������ƁB
�܂��A�ޗǎ��ォ��u�����̓��v�Ƃ��āA�������g�̏���⹁A���v�̗�(1221�N)�ɔs�ꂽ���H��c�������ꂽ�B
�w���ƕ���x�ɂ́A���̊C�m���ׂ̗̓��̐��m���ɕ��o��l�������ꂽ���Ƃ��L����Ă���B
���̂��Ƃ́A�{��8��27���t���́u�B��A�[�g�g���C�A���v�ɏ������Ƃ��肾�B
����Ȏ���ɂȂ����̂��B
�����ˁI
�������ˁI
���҂ł���ˁI
����������ˁI
�����v���B
���́A1998�N�Ɏn�߂��uNPO�@�l�������R��w�v���A����ȕ������������ė����グ���n�搶�U���犈���������B
�u���̊v�̂悤�ȁu������Ёv�́u�r�W�l�X�v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��������ǁB
�uNPO�@�l�v�Ƃ��āA�u��c���v�̋��犈�������Ȃ肵���������ė����Ǝv���B
�����āA�{�N�A2016�N������X�e�[�W�A�Z�J���h�X�e�[�W�ɓ˓����Ă���B
����Ȏ����ɁA���̋L����ǂ�ŁA����10�N�A20�N�́u����̊v��䍂�����ꂽ�̂������B

�{���̞w��
�C�����ƁA�w�тɓ����Ă����B
�P�[�u���w���߂��A�l�H�X�L�[��Ղ��߂��A�����u�ցB

�{���̂����u
�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B�����āA�Z���q�B
���i��]�ށB

�{���̐���R

�{���̔��i�ƒ|����
�悭������B
�|�������B
�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�G�ꂽ�ł̏�ŁA�o�N�]3��Ƃł�Ԃ�12��B
�w�����G���B
���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��
�Ō�́A��X�_�ЎQ�q�B
�u����̊v�ł͂Ȃ����A���q12�q�B

�{���̍�X�_�Ђ̐_��
���̐_���Ɏʂ��胂�m�́H
����10�N�A20�N�̗��j�́u����̊v�H
�X�p�C�����j�ρH
����咆���H
����Ƃ��H
�����H
���ڎ�2
2016�N9��29���@���c����F13���I����17���I����@�@���ڎ�2
�q���N�l
�݂Ȃ���
��ϋ����[�����̌@�艺���A���肪�Ƃ��������܂��B
17���I���̍����́A�q�����w�E����Ă���ʂ�ŁA���a���ɕ����e���h���m�����܂��B
����́A14���I�㔼�ɁA��k���̗������܂������ɓ쒩�n�̐�����i�`�����j�������u�\�y���\�v���m���������Ƃɂ��Ȃ���܂��B
���̑O�̌�����Řb���܂������A�킽���́A�\���u�����̕����v�u���a���̉B���ꂽ�C�����v�ƌ����Ă��܂��B���ł��A�喼�����̐Q���~�����Ƃ��ł���ʒu�ɂ����̂��\�y�t���\�y�t�����y�t�ł����B
���āA17���I���̂�����́A�Ȋw�Z�p�̐��E�I���W�ƘA�����Ă������Ƃł��B
��̓I�ɂ́A�퓬����A�S�C���C�̔����Ɨ��z�ł��B
���͂�u�����̍���v�̂悤�ɁA�u�₠�₠�A��͕��Ƃ̉��������v�Ɩ����������ăp�t�H�[�}���X�I�ɐ키���ƂȂǁA���肦�Ȃ����ԂƂȂ�܂����B
�ǂ�قǂ̐퓬������A��ʂɁA����������悭�A���₭�����ł��邩�A�����Ɨʂ𑈂��悤�ɂȂ�܂����B
�ȗ��A�����E���|�I�ȗv�f�́A�푈�̑���̉ۑ肩�痣���悤�ɂȂ�܂��B
�����āA�u���̕����v�̈�Ɉʒu�t�����A�u���m���v�Ȃ���̂����܂�Ă��܂��B
���āA�킽������莋�������̂́A������A13�ȋI���ł��B
������u�����S����聁�������v�ƌĂԂ��Ƃ��ł��܂��B
�������k���ɋN�����������S�������{�ƃ��[���b�p�����h���ɂ��铌��������B���������Ƃ̕����j�I�E���E�j�I�Ӗ����ǂ��l���邩�A�����Ă��̌�̕ω����ǂ����邩�A�Ƃ������ł��B
���{�ŁA�@�؎v�z��������@�n�̋��������A���e�B�����̂́A���́u�ÏP���v�̌�ł��B
13���I���{�Ɛ��E�͑傫���]�����A�����āA17���I�ɂȂ��ꍞ��ł����܂��B
�����āA�Ȋw�Z�p�̎���ƂȂ��āA�u�g�S�ϗe�Z�@�v���}�C�i�[�ȗ̈�ɉB����Ă����킯�ł��B
�X�E�Q�X�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��29���@�q���N�F17���I���ɂ悹���@�@���ڎ�2
���c�搶�A�F�l
��T�P����̂������肪�Ƃ��������܂��B
�u17���I���v�͂ƂĂ������[���ł��ˁB
���{�ł́A�퍑���オ��i�����āA�͂��߂ĕ��@�̗��h���m������B����́A���@���킢�Ƃ����ړI�̂��߂ɂȂ�Ƃ��Ԃɍ��킹�邽�߂̋Z�@����ω����āA���@�̏C�����ꎩ�̂̎��ȖړI�����邱�ƂƂ��ė����ł���ł��傤�B
�����ł������悤�Ȏ������܂��B���Ɍ���n����������͖����̕����Ƃ��āA�����̍����̂Ȃ��Ŏ�������x���o�����܂��B�������A�����ɐ������ڂ�ƁA�ނ͈��ނ��Ĕ����k���������A���p���������ēƎ��̗��h�����܂��B
���̂悤�ɁA���p�̗��h��ł����Ă�Ƃ������Ƃ́A�헐�̐�����i�����āA��r�I���a�ŗ]�T�̂��鎞��ɂȂ��Ă͂��߂ĉ\�ɂȂ�̂�������܂���B�����āA�헐�ƕ��a�̗����ɁA�Б����˂����o���̂���l��������s���B
���̐l�́A��̐��̒���}��鑶�݂ł���Ƃ������܂��B�����̐��ɁA�ނ𑋌��Ƃ��Đ헐�̐��̉�������������ł���A�Ƃ��������ł��傤���B���Ƃ��A�C�M���X�ő��Ɍ��������Ă���搶���A�����̓c�ɂŕ��p���ǂ�قǖ��ɗ��������̂��Ƃ��ɂ���������܂��B
���{�␢�E�e�n�̐g�S�ϗe�Z�@�����āA��w�Ƃ����Â��ȏ�ł���\���鎄�B���A�����悤�Ȃ��̂�������܂���ˁB��������ƁA���B���������h��ł����Ă邱�Ƃ��ł���̂����H
�O�̂��̂���̐l�ɏЉ�邱�Ƃ��A�O�̂��̂𐅂ł����߂Ă���Ƃ���������Ă��炤���ƂƂ��đ������Ȃ�A��͂�܂�Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A�O�̂��̂�V���ɕҏW���đ̌n�����āA���̐l�Ɍ����ĉ����V�������̂�n�����邱�ƂƂ��đ�����ƁA����͗��h��ł����Ă邱�Ƃɓ������͂��ł��B�ǂ�Ȓ������\�ł��A�����I�ɂ͓Ǝ��̗��h��n�����邱�Ƃł���A�{�{��������삪������̂Ɠ������Ƃ����Ă���̂��ƍl����ƁA�ʔ����ł��ˁB
�q���N�q
���ڎ�2
2016�N9��28���@���c����F2016�N10��29���i�y�j�ܖ؊��V�u�����u�߁v�̗́A���ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
2016�N10��29���i�y�j15�����A�ܖ؊��V���̍u����ƓC�k���s�Ȃ��܂��B
�_��́A���u�߁v�̗́`�����������ʂ����߂Ɂ��ł��B
���Ђ��̋@��ɂ��Q�����������B
�C�k�́A�{�g�S�ϗe�Z�@������̕��S�����҂̓����i����Ƃ킽�������߂܂��B
------------------------------
�ܖ؊��V�u�����u�߁v�̗�
�������������߂ɕK�v�ȗ͂ƒm�b�ɂ��āA��Ƃ̌ܖ؊��V����Ɏf���܂��B�C�k�ł́A�������R��w�w���E�����i�Ɩ��_�������E���c���A���ꂼ��̎��_����ܖ���ɖ₢�����܂��B�i���\�����ݕ��@�ɂ����ӂ��������B�j
2016�N10��29���i�y�j
15���`18���i�J��14��00���j
��q��w10���ٍu��
���ÁF��q��w�O���[�t�P�A������
�@�@�@�@NPO�@�l�������R��w
------------------------------
�u�߁v�̗́`�������ʂ����߂�
�@���L��t
��ꕔ ���ʍu��
�ܖ؊��V�u�w�߁x�̗́`�������ʂ����߂Ɂv
��� �C�k ���J�E�ΓJ��t
�C�k�u�������ʂ��͂ƒm�b�v
�ܖ؊��V �����i ���c����
��u���F
���2500�~�A�w��1000�~�ANPO�@�l�������R��w���2000�~�ANPO�@�l�������R��w�w������E��q��w�O���[�t�P�A�������l�ޗ{���u����u���E���H�@���w�����Ȋw��500�~�A��q��w�O���[�t�P�A������2016�N�x�H�����J�u����u��2000�~
�\���E�⍇��F
��q��w�O���[�t�P�A������
��102-8554�����s���c��I���䒬7-1
TEL 03�i3238�j3776
FAX 03�i3238�j4661
E-mail grief20161029-ofc@sophia.ac.jp
------------------------------
�ܖ؊��V�i��Ɓj
�P�X�R�Q�N�A�������ɐ��܂��B���A�k���N�����g���B����c��w���w�����V�A���w�Ȓ��ށB�f�U�U�N�A�w������X�N����A���x�ŏ�������V�l�܁A�w�����߂��n������x�ő�T�U�؏܁A�w�t�̖�x�ŋg��p�����w�܂���B�f�O�Q�N�x��T�O��e�r���܁A�f�P�O�N�A�m�g�j���������܁A��U�S���o�ŕ����ܓ��ʏ܂���܁B�����ȊO�ɂ����L����]�����𑱂���B��\��Ɂw���ɐ�����āx�w���̕�x�w�����߂̖�x�w�@�@�x�w���̉����x�w��͂̈�H�x�w�s�`�q�h�j�h�x�w�e�a�x�i�S�U���j�ȂǁA�ߒ��Ɂw���~�̖�x�Ȃǂ�����B
�����i�@1948�N�A�����s���܂�B������w��w�@�l���Ȋw�����Ȕ��m�ے��P�ʎ擾�ފw�B�@���w�ҁB������w���_�����E��q��w��w�@���H�@���w�����ȉȒ��E�O���[�t�P�A�����������BNPO�@�l�������R��w�w���B�����́w���Ɛ_���Ɠ��{�l�x�w���{�l�̎����ς�ǂށx�w����ꂽ���ː��u���S�v�_�x�w���_���E�̂䂭���x�ق��B
���c����@1951�N�A����������s���܂�B���{�@��{��w�@���w�����Ȕ��m�ے��C���B�@���N�w�E�����w�B��q��w�O���[�t�P�A���������C�����E������w�q�������E���s��w���_�����BNPO�@�l�������R��w���㗝�����B�����́w�@���Ɨ쐫�x�w�_�ƕ��̏o�������x�w�������̎v�z�x�ق��B
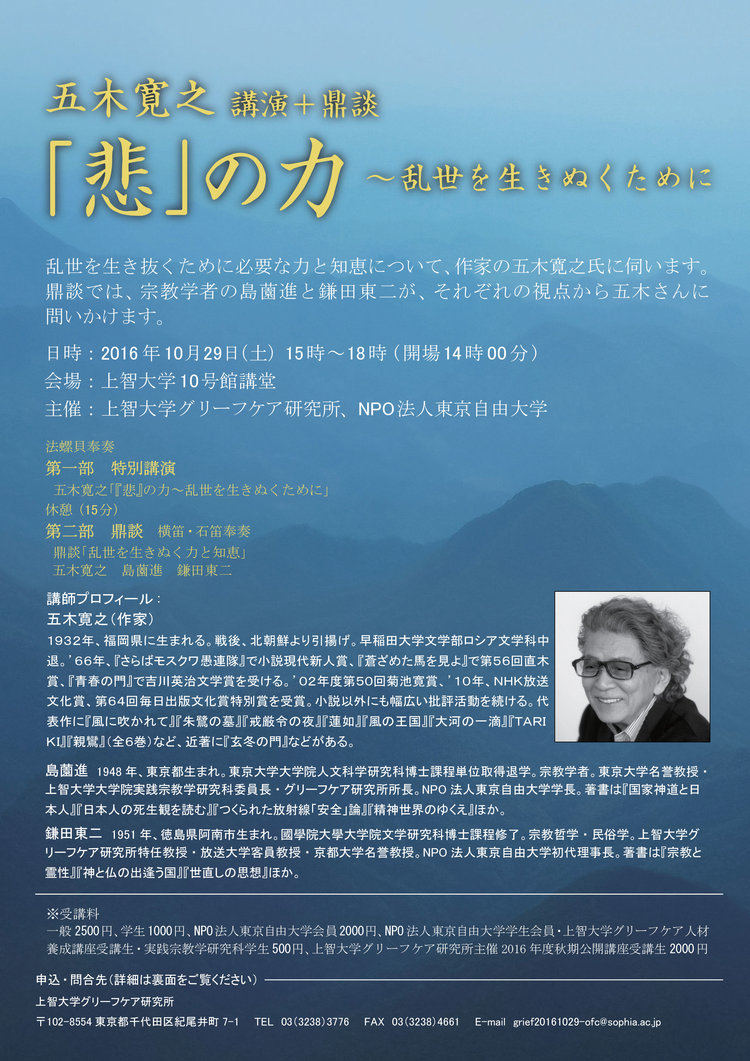
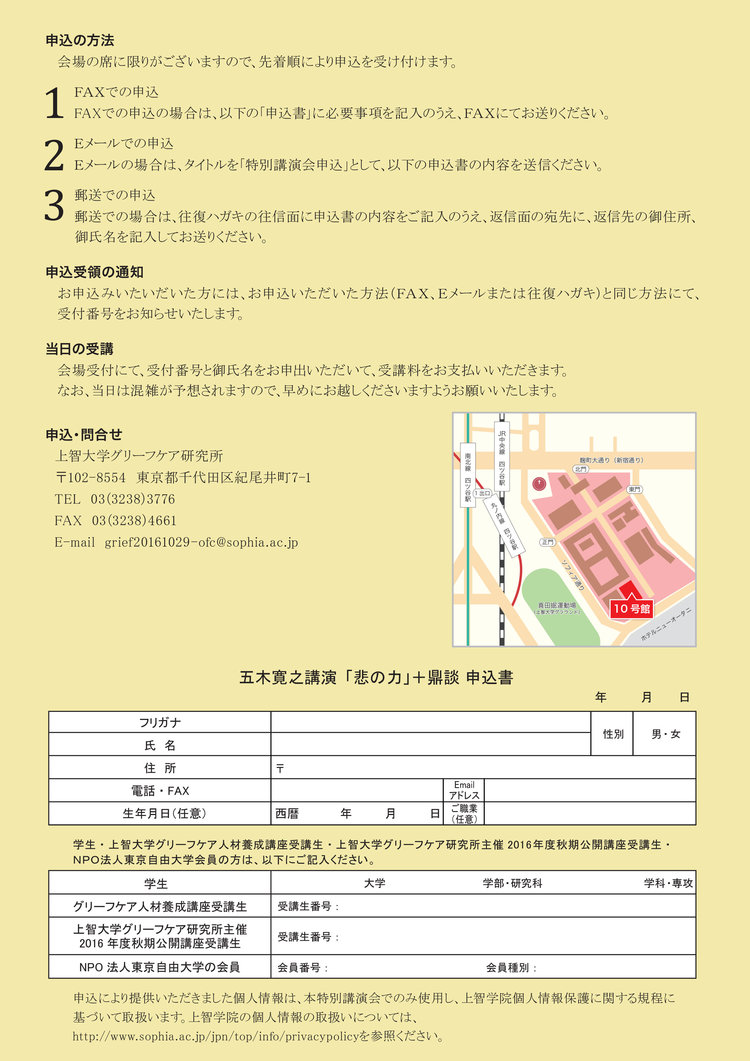
�X�E�Q�W�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��27���@���c����F��51��g�S�ϗe�Z�@��������@�@���ڎ�2
�q���N�l
�݂Ȃ���
����̑�51��g�S�ϗe�Z�@������A���肪�Ƃ��������܂����B
�L�v�ȋc�_���o�����Ǝv���܂��B
�ȉ��A���������܂܂ɁA�u��51��g�S�ϗe�Z�@������v�̕����܂��B
��51��g�S�ϗe�Z�@������
�����F2016�N9��26���i���j13���`17��30��
�ꏊ�F��q��w���T�e���C�g�L�����p�X���O���[�t�P�A�������i�T�N���t�@�~���A����2�K�A����}�~�c�w����������k��4���j
���\�@���c����i��q��w�O���[�t�P�A�����������E�@���N�w�j�u���[���V�A���Ȃ��g�S�ϗe�����̉ߋ��Ɩ����`�����ƃ��V�A���ђʂ�����́v
���\�A�q���N�i���w�@��w�����E�Љ�w�j�u����Љ�ɂ�����g�S�ϗe���`���Ɍ��̍L����ɂ��Ă̎Љ�w�I�l�@�v
�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����j
�e60�����\�{60�����c
A�F���c����̔��\
�킽���̕��́A�قځA�ȉ��̏��Řb�����܂����B
�P�A�����Ƃ̊ւ��i1990�N3������10����K��B���V���|�W�E���Q���j
�@�@���V�A�Ƃ̊ւ��i1990�N8���A�����Y��Y��c���ɂ������{�F����������̎��@�ŁA���\�A�̉F���֘A�{�݁y�F����s�m�̊X�E�o�C�R�k�[���̃��P�b�g�\���[�YTM10���ł��グ��n�z�����ĉ��B2008�N�E���W�I�X�g�b�N��w�ōu�`�A����̃E���W�[�~���K��Ȃ�3��j
�Q�A�����ƃ��V�A�ɂ����鐭���Ə@���i�g�S�ϗe�Ƃ��̋Z�@�𐢂ɑi�����@���ƃI�E���^�����������ň����N�������g��j
�R�A���V�A/���[���b�p�Ɠ��{���Ȃ������Ƃ��Ẵ����S�����ƃ����S���R�`13���I�����S���̓������h���̋R�n��
�S�A���z�E�����S���E���N������{�ɂ����炳�ꂽ�u�L�v����b�R�̐_�������̏o���
�T�A���V�A�ɂ����铌���m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�ɂ��w���s�x�i�h�X�g�G�t�X�L�[�j�Ɓw�Î��L�x����
�U�A�X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���Ɛ�����́w���p�ԓ`�x
�V�A���[���V�A�����Ԗ�������
�W�A�܂Ƃ�
�������A�⑫�ƃR�����g�����Ă����܂��B
�P�A�\�A�F����n�o�C�R�k�[�����w�⑫
TBS�̋L�҂ł������H�R�L������i1942�`�A�����s���`�|�p��w�����j���A�F����s�m�P�������Ă���Œ��ɁA�킽�������u���{�F����������v�̈ψ��̃����o�[�͎��@�ɍs���܂����B
����4������A�H�R����́A1990�N12��2���Ƀ\���[�Y�s�l11���ɓ��悵�A�\�A�̉F���X�e�[�V�����E�~�[���ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ�܂��B
���̎��̃\���[�YTM10���́A�\�A�̃o�C�R�k�[���F����n���ł��グ���̂ł����A�����Ń��[�~���Ɖ�A�ޏ���LP�w�V���̃h�A�x�̋ƊE�p���C�i�[�m�[�c�������܂����B
�H�R����́A���E�ŏ��߂ĉF���ɍs�����W���[�i���X�g��TBS�̉F�����h���ƂȂ�܂����B
���̕ӂ̂��Ƃ́ATBS�F���v���W�F�N�g�w���{�l���F���ցx�ŕ�������܂������A�ł��グ���̎������͑�ύ������ڂ��W�߁A36%�������Ƃ̂��Ƃł��B
�H�R����́A�\���[�YTM-11��������O���ɏ�������A�����p�Łu����A�{�Ԃł���?�v�Ƒ�ꐺ�����ƌ����܂��B
�H�R����́A����O�́A��ꐺ�́u�F���͍��ׂƂ��Ă��܂��v�Ɣ����悤�ƍl���Ă����悤�ł����A�F���͍��ׂƂ͂��Ă��Ȃ��������������ƂƁA�\�A�F����s�ǐ��Z���^�[�i�킽�������@�������Ƃ�����܂��j�ƌ�M���ɁA��������̊��荞�݂̌Ăт����Ɂu����A�{�Ԃł���?�v�Ɣėp�����Ƃ̂��Ƃł��B
��ŁA����́u�����Ƃ������l�炵����ꐺ�������v�ƐU��Ԃ����悤�ł��B
�Ƃ�����A�y���X�g���C�J�ƃO���X�m�`�������r��Ă��鋌�\�A�����B�\�A���J��̃A�m�~�[��Ԃ̒��ŁA�G�z�o�̏ؐl�ⓝ�ꋳ���I�E���^���������荞�݁A�V�@������ϗ��s�����悤�ł��B
�Q�A�u�L�v���
�L�����[���V�A�I�ȍL�����������J�����ł��邱�Ƃ̈Ӗ��ƈӋ`������ɒNjy����]�n������܂��B
�@ �X�T�m���`�卑��_���u�������E���|��E�V�ًՁv�̏o�_�ŎO��̐_��������Ă��邱�ƁB���ł��A�u���|��v�̖�ɂ͖L�����Ă����͂��B�Ȃ��Ȃ�A�ŏ��Ɂu�L�̖�v��������̂̓X�T�m��������B
�A �o�_�n�̑啨��_���u�O�h���v�ƂȂ��āA���l�̃Z���_�^���q���́u�z�g�v��˂��Ƃ�����_�ȍs�ׂ��������Ƃ��w�Î��L�x�ɋL����Ă��邪�A���́u�O�h���v�́u�L�̖�v���H
�B �w�R�鍑���y�L�x�ɁA�ʈ˕P�����g�̏���ɘȂ�ł������A�u�O�h���v������ė��āA��������̕ӂɒu���Ă�����D�P���A���ΐ_�Ђ̐_�E��Εʗ��_�Ƃ���B���́u�O�h���v�́u�L�̖�v�ł͂Ȃ����H�@�Ƃ����̂��A���̐_�̕��_�́A������Ђ̐_�A�܂�A��b�R�̐_�Ƃ���邩��B�����āA��b�R�̐_�́u�L��p�_�v�Ɓw�Î��L�x�ɋL����Ă���B
�C ��א_�Ђ́u���Ȃ�v�́A�ʏ�A�u���v����u���Ȃ�v�ƂȂ��ĂƂ���邪�A�鎭���T����́A���ꂪ���X�͉��̏o��u���Ȃ�v�ł������Ƃ̐����o���Ă���B���́u���Ȃ�v�́A�L�̖�ł͂Ȃ����H�@��ׂ́A�V�����n�������`�����d�����_�ЂŁA��ΐ_�Ђ��J������Ύ��Ƃ͍����W�ɂ��邱�Ƃ��A�w�`���{�n���x�ɋL����Ă���B
�D �w�R�鍑���y�L�x�ɏo�Ă����ב�Ђ̑c�ƂȂ�`�ɘC��́A��Ŗ݂��ˁA���ꂪ�����ɂȂ��Ĕ��ōs�����ƋL����Ă��āA����˂�l�ł���A�L�̖�������̂ł͂Ȃ����H
�ȂǂȂǕ���B
�R�A�u�q���L�v���
������q���N����̃R�����g�ŁA�w�|�敨��x�ɏo�Ă��邩����P�̖�������b�Ɂu���̎q���L�v������ė���ۑ肪�^����Ă��邪�A���́u�q���L�v�ɂ͂ǂ̂悤�ȈӖ����������̂��Ƃ������B
�u�q���L�v�͈��Y�̂����ɂ��Ȃ�܂����A�_�����M����p���{�i�A���e�i�ł���A��͑�����ł��B
���́u�q���L�v���A�C�̂Ȃ��������S���̃V���[�}�������Ɂu�����v��406�������Ă��邱�Ƃ̏ے��I�������I�Ӗ��ƈӋ`�Ɨ́B
�S�A�w�Î��L�x�̓��{���ꐫ�Ɛ��E�i�F���j����
�w�Î��L�x�͓���ŕ��ՁB
���̃_�C�i�~�Y�������X�N���w�Î��L�x�������o�Ă���ɐ��͓I�ɑi���Ă��������Ɖ��߂Ďv���܂����B
B�F�q���N����̔��\�u����Љ�ɂ�����g�S�ϗe���`���Ɍ��̍L����ɂ��Ă̎Љ�w�I�l�@�v

�������\����q���N��
�q������̔��\�͑傫��2���\���ŁA
��ꕔ�́A���Ɍ��̗��j�Ɠ����ɂ��ĕ����I�E���_�I����
��́A�C�M���X�E�v�}���`�F�X�^�[�̑��Ɍ�������C�����̎��ጤ��
�ɕ�����Ă��܂����B
�����[�������̂́A
��ꕔ�́u�����Ɍ��v�����܂�Ă���17���I���B���{�ł͍]�˖��ˑ̐��m���ƕ������|�����h�̊m���̖��
�ƁA
��̃}���`�F�X�^�[��C�����̎����6�|���h���i�������đ��Ɍ����w�ԂƂ������Ƃ̈Ӗ��t���Ɣ����j
�ł����B
���j������ƁA����㐢�̒���i1600�|1680���j���ꑰ�ɑ�X�`������Ă������@�Ɂw����o�x�ɂ��铹�Ƃ̗{���p�����킹�āA�u���_���ς���V���Ȍ��@�v��n�n�����̂�17���I�̂��Ƃ��ƌ����܂��B
�܂��A����ɓ`�����������Ɍ��̋Z�@�́A�ʌp�����w�I���V���x�i1560�N�A�����1561�N�j�́u���o���v�сi���傤���傤�悤�ւ�j�v�Ɏ��^����Ă��錝�@�ł���u�v���c�����O�\�v�Ƃ��Ȃ�ȕ������ގ����Ă���ƌ����܂��B
���̐ʌp���́u�`���v��ɐ���������ŁA�ނ����킵���w�I���V���x�́A���̑啔�����A�킢�̎���܂��āA�헪�E�P���E�s�R�E����Ȃǂ�_�������̂ł����A�������A�u�O�\�v�́A����ɒ��ږ𗧂��Ȃ����A�u������g�����߂̐g�̂̊�b��n�邽�߂ɖ𗧂Z�@�v�ł���Ƃ��ďЉ��Ă���ƌ����܂��B
�ʌp���̌����u���Ŗ��ɗ����핐�p�v�Ƃ́A�������A�|��Ⓛ���ⓡ�v�Ȃǂ̕����p�������p�ł��B
���A���@�́A�����������핐�p�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǒႢ����I���l���������Ȃ������̂ŁA�u�r�������͕���a�炸�v�ƋL����Ă���ƌ����܂��B
����ɂ�������炸�A���@�́A�u�葫���������A���̂������v��u�Α��I�ȕ��핐�p�v�̂��߂̐g�̂̊�b���u�Όȁi�Ύ��j�I�ȏC���v�ɂ���č����̂Ƃ���܂��B
�������āA�u���핐�p�Ƃ����ړI�ɑ����i�Ƃ��Ă̏C���v�Ɓu���̎�i�̎��ȖړI���Ƃ��Ă̌��N�̑��v�̗��`�I�u�g�S�ϗe�Z�@�v�Ƃ��āu�����Ɍ��v���`�����ꗈ���悤�ł��B
�킽���́A�ْ��w������\�g�S�ϗe�Z�@�̎v�z�x�i�y�ЁA2016�N4���j�̒��ŁA17���I�Ɋ��������ƂŁu��V�ꗬ���@�v�̑n�n�҂̋{�{�����i1584-1645�j�̂��Ƃ����グ�܂����B
�킽���̏Z�ދ��s�s�������掛�ɁA���R�A��36��̒��̑�8��̉Z���R�R���t�߂ɒK�J�R�s���@�Ƃ����u�^���@�C�����v��W�Ԃ��鎛�@������܂��B
�����ɂ́A�{�{�������C�s�����ƌ�����ꂪ����A�����ŕ����́u��͐_���Ԃ��A�_���ɜ��ނ��Ƃ͂��Ȃ��v�i�u���_�͋M���A���_�܂��v�j�Ƃ��������ƌ����Ă��܂��B
�{�{�����́A���i20�N�i1643�j�A�F�{���F�{�s�̋���R�ɂ���u��ޓ��v�Łw�ܗ֏��x�������܂��B
���̋{�{�����ŔӔN�̎����̌��t�Ƃ����u�Սs���v��21�����́u�����P�v�͎��̒ʂ�ł��B
��A���X�̓���w�����Ȃ�
��A�g�Ɋy���݂��I�܂�
��A���Ɉˌ͂̐S�Ȃ�
��A�g��v�А���[���v��
��A�ꐶ�̊ԗ~�S�v�͂�
��A�䎖�ɉ��Č��������
��A�P���ɑ���i�ސS�Ȃ�
��A���Â�̓��ɂ��ʂ��߂��܂�
��A�������ɍ��ݑ��S�Ȃ�
��A����̓��v�Њ��S�Ȃ�
��A�����ɐ���D�ގ��Ȃ�
��A����ɉ��Ė]�ސS�Ȃ�
��A�g�ЂƂɔ��H���D�܂�
��A���X�㕨�Ȃ�Â����������
��A�킪�g�Ɏ��蕨���݂��鎖�Ȃ�
��A����͊i�ʗ]�̓�����Ȃ܂�
��A���ɉ��Ă͎����}�͂��v��
��A�V�g�ɍ��̗p���S�Ȃ�
��A���_�͋M�����_�܂�
��A�g���̂Ă������͎̂Ă�
��A��ɕ��@�̓��𗣂ꂸ
���삪������17���I�A���{��16���I�㔼����17���I�ɂ����āA�퍑�E�헐�̐����������{�{�����ɂ́A��̌��z���_���`���Ȃ��悤�Ɍ����܂��B
�Ȃɂ���A�u���_�͋M���A���_�܂��v�u�g���̂Ă��A�����͎̂Ă��v�����b�g�[�Ƃ���A�������A�ɂ߂Č����I�ŃX�g�C�b�N�ȋ����҂ł�����B
�u���X�̓��v�ɔw�����A���Ȃ̉��y�ɒ^�炸�A���݁E�h�݁E�i�݁E�����E�]�݁i�~�j�E�����������A�`���邱�ƂȂ��A�R�R�Ƃ킪�g�𗥂��A�����̂ɂ��ˑ������A�����������Ǝ�����Y�ꂸ�A�������@�ƂƂ��Ă̏C�s��ӂ�Ȃ��B���̂悤�ȍ����̕��@�Ƃ̃��A���Y���Ɨϗ��������Ă���̂��{�{�����ł��B
�w�Սs���x�̒��ŁA�u���_�͋M���A���_�܂��v�Ƃ�����19���̌��t�ɂ́A�{�{�����̍�����`������܂��B
�m���ɐ_���͋M���B�������_���𗊂����Ő��i�w�͂�ӂ�����ɂ��ď����ɕ����Ė��𗎂Ƃ��B���n�Ƃ��āA��������M�Ƃ��Ă̑��͖{��ɈӖ��Ɨ͂͂��邪�A���ꂪ�����Ɏ��͏C�s�̉ʂĂɂ��鐶���������鏟�������E����킯�łȂ��B���������āA���͐_���ɗ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ƃ����킯�ł��B
���̋{�{����������N���҂���ɕ����Ƃő喼�ƂȂ��������@��i1571-1646�j�ł��B
�����@��́A���쏫�R�Ƃ̕��@�w����Ƃ��ĕ��|�Ғ��ō��ʂɏA���܂��B
�����āA�u�Í����o�̒B�l�v�u���p�ҔV�P�v�u��(�����ΏM�֏@��)�ɂ��������v�u���p�Í��ƕ�[�v�u���p���o�v�Ƃ��ƕ]����A�B��喼�ɍ̂藧�Ă�ꂽ���@�Ƃł��B
�{�{������������������̋������āA�u���T��v�i���T��@�j�v�����������Ƃ���܂��B
�咘�w���@�Ɠ`���x�Ŗ����@��́A�u�l�����낷���́A�l�����邬�Ȃ�ׂ��v�Ɓu�E�l���v����l���������u���l���v�ւ̓]��������܂��B
����́A�u��l�̈������낵�Ė��l���������v���Ƃ��Ӗ����܂��B
�����@��́A�u�l�����낷���A�p���l���������邬��Ƃ́A�v�ꗐ�ꂽ�鐢�ɂ́A�̂Ȃ��ґ����������B���ꂽ�鐢�����߂�ׂɁA�E�l����p��āA���Ɏ��܂鎞�́A�E�l���������l���Ȃ炸��v�Əq�ׂĂ��܂��B
�����āA�����ɂ�����u�E�l���v���畽�a���ɂ�����u���l���v�ւ̓����������ƌ����܂��B
�{�{�����́A�����@��ɂ��Ȃ�R�S�������Ă����悤�ł��B
�{�{�����́A�w�ܗ֏��x�u�n�̊��v�̒��ŁA
���ɁA�悱���܂ɂȂ����������ӏ�
���ɁA���̒b�B���鏊
��O�ɁA���|�ɂ��͂鏊
��l�ɁA���E�̓���m�鎖
��܂ɁA�����̑������킫�܂�鎖
��Z�ɁA�����ڗ����d�o��鎖
�掵�ɁA�ڂɌ����ʏ������ƂĂ��鎖
�攪�ɁA��Â��Ȃ鎖�ɂ��C��t���鎖
���ɁA���ɂ��T�ʎ��������鎖
�ƋL���Ă��܂��B
����́A���@�ƁE�C�s�҂̐S�\���Ƃ��Ă���������O�̏����ŁA���قȌ����͈������܂���B
���S���������A����܂��Ɏ����ɑΏ����A���|���E�̌|�ɐG��ē������߁A�������Q���ʍׂ����Ƃ���ɂ܂Ŗڂ�z��A���ʂȂ��ƁA���ɗ����Ȃ����Ƃ͂��Ȃ��Ƃ����A�O��I�Ȏ�����`�B
���̂ǂ��ɂ����ۂ�����������܂���B
�����܂ł���ۋ�̂̎��H��������݂̂ŁA���ɁA���V������قǗ��V�ŏ펯�I�ȌP���ł���ƌ����܂��B
���̂悤�ȁu���p���v�������グ���{�{�����Ɛʌp�������ɂ́A���ʂ��郊�A���Y���Ǝ��p��`������悤�Ɏv���܂��B
�����17���I���ɂ킽���͑�ϊS������܂����B
�����āA�����ł́A���傤�ǂ��̍��A�������A�����琴�ɕϑJ���Ă����܂��B
���̂�����A���A�W�A���������Ƃ��āA��ϋ����̂���Ƃ���ł��B
�Ƃ���ŁA���e��ł́u���V�A�A�J�f�~�[�v�̖��́A��ϋ����[�������ł��ˁB

�A�肪���̋��s�E�l��勴
�X�E�Q�V�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��27���@���c����F���X�N���w�Î��L�x�����̔����@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̏��D�̒����b�q����ȉ��̕������
�����̂ŁA�]�����܂��B
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
���X�N���Łu�Î��L�v���㉉���ĎQ��܂������A�ϋq�̕��X���A�X�^���f�B���O�Ɣ�
��ŁA���B���}���ĉ������܂���!!
���V�A�̉����l�̕��X��A�W���[�i���X�g�̕����̌𗬉�ł́A�u�{���̌|�p������
�Ă���ėL��B�A�o���M�����h�ɑ����Ă��鍡�̃��V�A�̉����́A���Ȃ��ׂ��Ƌ�
�����܂����B�v�u���̍�i�ɁA���t�͕K�v����܂���B�[��������L��B�v�u�A
�j�V���t���̉��o�́A���ɖ����ɓ��B���Ă���B�v���X�A��R�̗l�X�Ȏ^������
�����B
���c�������ɂ�������������Ǝv���ƁA�{���Ɏc�O�ł����I
�A�j�V���t����́A��R�̃C���^�r���[�̈˗����Ă�������Ⴂ�܂����I
�܂��߁X�A������Ă��b���o���܂�����K���ł��I
����Ƃ��A�ǂ����X�������肢�v���܂��ӂ����߂�!!
�����m�[���C�E���p�[�g���[�V�A�^�[ �����b�q
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�X�E�Q�V�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��27���@���c����F������w�����엝��������̈ē��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
������w�̈����엝�����i�A�����J��Z�������E��r�����w���j����A�ȉ��̈ē�������Ă��܂����̂ŁA���m�点���܂��B
�ȑO�A�f�j�X�E�o���N�X����ƂR���ԍs�������ɂ������Ƃ�����܂����A�A�����J��Z���̃T�o�C�o���Z�p�́u�g�S�ϗe�Z�@�v�Ƃ��Ă���ϗL�Ӌ`���Ǝv���Ă��܂��B
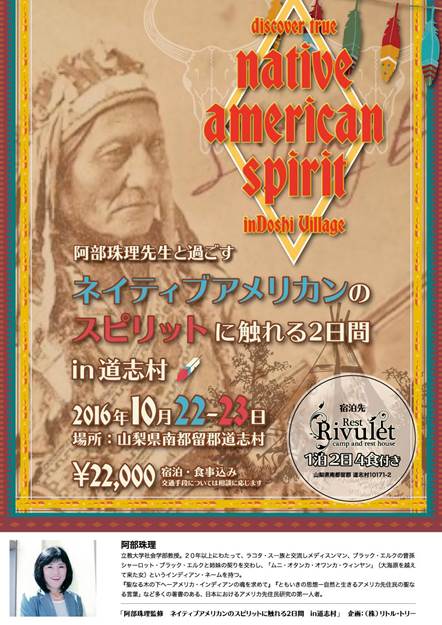

�X�E�Q�V�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��26���@���c����F�����̔��\�����ł��@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�s�\���ł����A�����̔��\�����������肵�܂��B
��낵�����肢���܂��B
�I����ɁA�����̂悤�ɁA�k��1���̋������u�k�̉v���������ō��e����s�Ȃ��܂��B
�X�E�Q�T�@���c����q
�����c����u���[���V�A���Ȃ��g�S�ϗe�����̉ߋ��Ɩ����`�����ƃ��V�A���ђʂ�����́v �idocx 1.37MB�j
���������s85�u�x�m�J���Ɠ������S���̖L�Ǝq���L�v �ipdf 556KB�j
�������V��16.10.1�u���V�A�ɂ�����w���s�x�Ɓw�Î��L�x�v���e �idocx 38.8KB�j
���ڎ�2
2016�N9��25���@���c����F���R�C�����R�V�S�@�@���ڎ�2
2016�N9��25��
�����{�P�Ƃ������̂���x���o���������Ƃ��Ȃ��B
���V�A�ɍs���Ă��A���V�A����A���Ă��Ă��A�����{�P�͂Ȃ��B
�����A�{�P�Ă邩��B
�q���̍�����B
�����Ɛ̂���B
���Ԃ̊ϔO������Ă�悤�Ɏv���B
12���I������̂悤�Ɏv���Ă��邩��B
�ی��E�����̗��i1156�`59�N�j�⌹���̍���i1185�N�j������̂��ƂƎv���Ă��邩��B
��C������������q�����s�҂�����A����܂Ŋ������Ă��l�Ǝv���Ă��邵�A�����Θb�ł���Ǝv���Ă��邩��B
�Ȃ̂ŁA��{�I�ɁA���܂���u�����{�P�v���Ă�悤�Ȃ��B
�䂦�ɁA������u�����{�P�v�͂Ȃ��B
�u�Y��悤�Ƃ��Ă��A�v���o���Ȃ��v���Ƃɖ����ɂȂ��ė�������B
���āA�Ƃ����킯�ŁA���V�A����A���Ă��Ă����Ɏ��Ƃ����A�����O�\�O�����ԎD���ƐԖ厛�i�����@�j�����Q�肵�A�����Ė{���A���悢��{���A���R�C��������킢�I
15���߂��A�����ɂ��A�J���~��n�߂��B
���A�ȁ`�ɁA���܂����Ƃ͂Ȃ��B
15��15���A���R�C�����o���B
��X�_�Зy�q�B
���R�����グ��B

�{���̔�b�R
������ƁA�������Ȃ��Ă����悤�ȁB
�t���ς������ԗ����Ă����悤�ȁB
���s�ł́A����1�T�ԁA�J�����������Ƃ��B
���̂��߂��A�������ɁA�֎�@�ٓV�r�����ʂ��������B
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B
���Z�~�i�[�n�E�X�e�̗т̒��̐��H���A���\���ʂ������A������肸���Ԃꂪ�����B

���H
���H������āA�n�ʂɗ��ꍞ��ł���B

���o�鐅
���H��̐��ʂ�������葽���B

���H��̉�
�X�ɓ���ƁA�����ۂ��͂��邪�A�ʂ���݂Ȃǂ͂Ȃ��B
���A�X�̋��N�͂����ԂC�����Ղ肾�����B

�{���̐X�̋��N
�����������藎�������Ȋ����B
�X�̗d���N���A���傢�ƔG�ꂽ�����B

�{���̐X�̗d���N
��������ʂ�����̂��A�t���ς������Ă����̂��A�������������n�߂��B

�{���̉���
�J�����܂�A�������~���Ă���B
���A�X�̒��́A�̖X�̎P�ɕ����Ă���̂ŁA���̂܂܉J�����n�ʂɓ͂����Ƃ͂Ȃ��B
�X�̒��ł͂��Ȃ�J�h��ł�����̂Ȃ̂��B
�i���͂��`�����ށB

�i���͂�̓�
���̃i���͂�̕\�炪�������𐁂��Ă���B
�����A�|���̂��Ǝv���Ȃ���A����2�N�ȏ�o���Ă���B

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
�X�̃��A�C�N�������͔G��Ă���B���̊Ԃ̉J�ƍ����̉J�ƂŁB
�����V�^�^���������A�C�B
���n���l�́E�E�E

�{���̐X�̂��n���l
���n���l�́A��n�̕�F�B
���̑�n������Ԋ������̂��A���Z���̍��ɓǂ��V�A�����ł������B
�p�[���E�o�b�N�́w��n�x�𒆊w�O�N�̎��ɓǂݒ^��A���̌�A���V�A�̑�͏����̂悤�Ȓ��ҏ�����ǂ������B
�V���[���z�t�́w�Â��Ȃ�h���x����g���X�g�C�ƃh�X�g�G�t�X�L�[�ցB
�����̃��V�A�����̒��ɁA�傫�ȑ�n������������Ă����B
��n���R�ɑ���ؕ|�،h�Ɛe���̐[��������B
���̑O�A���V�A�ɍs���āA����ȃn�C�e�B�[���̍��̃��V�A���o��䍂��Ă����B
�u�Y��悤�Ƃ��Ă��A�v���o���Ȃ��v���V�A��n���o���B
���̃��V�A�ŁA�Ⴊ����́w����@�Î��L�x���㉉���ꂽ�̂��B
�w�Î��L�x���]�̂Ǝ����ς̒T���̏��A���邢�́A�X�s���`���A���P�A��O���[�t�P�A���܂����̏��Ɠǂ�ł����B
����͂ƂĂ�������{�I�ȕ������^�̂悤�Ɏv���Ă���B
�����A�����Ō���Ă��鐶�Ǝ��ƍĐ��̃e�[�}�́A���ՓI���B
500�l�̉�ꂪ���Ȃ������B
���{�ŌÂƂ����ÓT�I�e�L�X�g���������g�p�����ɏ㉉�����B
�������A�ϋq�ɔz�������V�A��̃p���t���b�g�ɂ͂��炷�����L�ڂ��Ă��邵�A�������ɁA��ʂ̐�ւ��̂Ƃ���ŁA����A�i�E���X�̃}�C�N�Ŏ���N�ǂ���悤�Ƀ��V�A�ꂻ�̃V�[���̈Ӗ����ϋq�ɓ`�����B
���̌������ςāA�ŏ��A���V�A�l�ϋq�͌˘f�����B
�ނ�ɂ܂���������݂̂Ȃ��������Ƃ����̕��ꂪ���X�Ɖ̂��邾��������B
�������A�_�X��������o�D�����͔\���҂̂悤�ɂقƂ�Ǔ����Ȃ��B
�\�����ɏ���̂݁B
�����A2���ɓ����A���Ԃ͈�ς���B
1���̐_�X�̒a���̎��ɁA���̃e�[�}���t�ł�ꂽ����B
2���́A�C�U�i�M������̍��ɕ����V�[������n�܂����B
���̐[�݂Ƀ_�C�r���O�������A�_�X�̒a���̕���́A�A�e�[���A��т���߂��݂ցA�����]�̂�������̂ցA���I�ɓ]������B
���V�A�l�ϋq�́A�����ň�C�ɁA�w�Î��L�x�̐��E�ɐ��荞�߂��B
�����āA����Ƌq�Ȃ���̃G�l���M�[�̂ƂȂ��ċ��ɐ_���ȋV����n�������B
�w����@�Î��L�x�̌��t�̈Ӗ��͂܂������킩��Ȃ��ɂ�������炸�A���́u������v�Ɓu����v���r���r�������Ă���B
�����Ƃ��B
����Ȋ����B
�܂��ɁA�_�b���E�_�錀�E�_�鎍���̑̌��B
�I����́u�u���{�[�I�v�̊|�������N�������B
�X�^���f�B���O�I�x�[�V�����̔��芅�т��B
���V�A�l�ϋq�����́A
�u���t�ł͓`�����Ȃ��l�ދ��ʂ̉b�q��̌����A���ɍ��x�Ȑ��_���E�ɓ�����A���R�A�F���A�_������قNJ����邱�Ƃ��ł��镑���i�͉ߋ��ɂ͂Ȃ������v
�u�o�D�����̐��E��n��o���̂ɑS�g�S�������A�|�p�ɕ�d���Ă��鉉���W�c�����܂�ǂ��ɂ��Ȃ��B�v
�u�����ɁA���t�̕ǂ����S�ɒ��z�����l�ދ��ʂ̐��E���`����Ă���B�v
�ƌ��X�Ɍ�����B
�����āA�u���Ђ܂����X�N���ōĉ����Ăق����B���V�A���Ō������Ăق����v�ƌ������B
���ꂵ���ł͂Ȃ����I
���肪�����ł͂Ȃ����I
��͕K�������Ȃ�Ɗm�M���Ă������A�{���ɂ����Ȃ����̂��B
�w�Î��L�x�̐��Ǝ��̏������̐����]�̂����V�A�̑�n�ɓ`������̂��B
�h�X�g�G�t�X�L�[�́w���s�x�����{�l�́u������v�ɓ͂��悤�ɁB
�w�Î��L�x���A���V�A�l�́u������v�Ɓu����v�ɐ[���͂��̂��B
����Ȃ��Ƃ�䍂��Ă����B
�X�͂��ׂĂ��z������ł����B
���肪�����B
�X��B
���グ��B
�w�т��B

�{���̞w��
�z�����܂��̂ł͂Ȃ��A�z�����ނ̂��B
�ǂ������ǂ����B
����Ȃ����ƁB
�����u�̂��n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B

�{���̂����u
�����āA�����u�߁A

�{���̐���R
����R�߁A

�{���̔��i�ƒ|����
���i�߂āA�Z���q�B
�}���A�l�H�X�L�[��Ղɖ߂��āA�o�N�]3��B�V�n�l�ցB��n�ցB
���ꂩ��A�ł�Ԃ�12��B
����̃P�[�u���w�ŁA�������߂�B
�䏊�̂�����Ɍ��̋��˂��Ă���B

�{���̕�����
���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��
�X���Ă���ԂɁA��������J�͎~��ł���B
�����āA�Ō�ɍ�X�_�ЎQ�q�B
���q12�q�B
�����āA�_���ɁE�E�E

�{���̍�X�_�Ђ̐_��
��X�_�Ђ̐_���Ɏʂ������̂́A���V�A�̑�n�H
���{�̑�n�H
�����ŌJ��L�����閳���̐��Ǝ��H
�j�āI
���ڎ�2
2016�N9��25���@���c����FRe�F��51��g�S�ϗe�Z�@������̑q�����W�����@�@���ڎ�2
�q���N�l
�����̃��W�����A���肪�Ƃ��������܂��B
��ϋ����[���g�S�ϗe�Z�@�̎���ƍl�@���Ǝv���܂��B
��낵�����肢���܂��B
�킽���̃��W�����́A�s���`�q�b�^�[�Ȃ̂ŁA�Ջ@���ςł܂��肽���v���܂��B
�������̂قǂ��B
�X�E�Q�T�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��25���@���c����F9��23���i���j���X�N���ł́w�Î��L�x�����̕i�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�F�㐢���y������j�@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�{���A��قǁA���X�N���ɂ��铌���m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̔o�D�Œʖ�҂ł�����㐢���y�����ϗL����������͂��܂����̂ŁA�]�����܂��B
�킽���́A�w�Î��L�x�̕���̋�̓I����͓�����{���̂��̂ł����Ă��A�����Ō���Ă���e�[�}�Ɩ{���͐������ՁE�F�����ՁE���E���Ր�������Ǝ咣���Ă��܂����̂ŁA���V�A�̊ϋq�̊F����Ƌ��ɂ��́u����v�����L�ł����悤�ȋC�����đ�ϊ������v���܂��B
�A�j�V���t����Ə㐢����͂��߁A�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�݂̂Ȃ���ɐS���̌h�ӂƊ��ӂ�\���グ�܂��B
�ȉ��A�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̏㐢���y����́w�Î��L�x������
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
���}���A�Î��L�����̕ł��B
���͂قږ��Ȃł����B�����ł͎����͎g�p�����A�z�z�������V�A��p���t���b�g�ɂ��炷�����L�ڂ��A�������A��ʂ̐�ւ��̂Ƃ���Œʖ�̉���搶������A�i�E���X�̃}�C�N�Ŏ���N�ǂ���悤�ɂ��̃V�[���̈Ӗ����ϋq�ɓ`����`�ŏ㉉���܂����B
���̃��V�A���w����̃��V�A�l�������̊��z�����Ɍ������̗l�q��`���܂��ƁA�P���́A���V�A�l�ɂ͑S������݂̂Ȃ��������Ƃ��������f�B�[�A�́A���A�����ĂقƂ�Ǔ����Ȃ��o�D�����ɑ����˘f�����悤�ł��B�ł����A�q�ȑS�̂���̂ƂȂ��āA���̏��߂đ̌����鐢�E�����Ƃ��������A������낤�ƏW�����ĊςĂ��܂����B���lj����킩��Ȃ��܂܈ꖋ���I�����A�x�e�ɓ���܂������A���̋x�e���P���Ŋς����́A�̌��������̂����ꂼ�ꂪ���������鎞�ԂɂȂ����悤�ŁA�Q��������ɂ�����ӎ��̒������ł��������ł��B�����ĂQ���A�C�U�i�M������̍��փC�U�i�~�ɉ�ɍs���V�[������n�܂�܂����A���������ł͈�C�ɕ���ŌJ��L��������{�_�b�̐��E�ɓ��荞�݁A����A�q�Ȃ���̃G�l���M�[�̂ƂȂ��Ĉꏏ�ɐ_���ȋV���ɎQ�����A���t�͕�����Ȃ��̂ɂ��ׂĐS�ŗ�������������A�s�v�c�Ȃ�������ɐS�n�悢�_��̌������������ł��B�I����̓u���{�[�̊|����������A�X�^���f�B���O�I�x�[�V�����Ŕ��芅�т��܂����B
�����ɑn���I�𗬉����A�����m�[���C����o�D���P�O�l�A���V�A������o�D�≉�o�Ƃ̂ق��ɁA�W���[�i���X�g�A�S���w�ҁA����҂ȂǂQ�O���قǂŊ��z�̃V�F�A�A��X�̑n�������ɂ��Ă̈ӌ������Ȃǂ�3���Ԃقǂ���܂����B���V�A�l�����̋��ʂ����ӌ��Ƃ��ẮA���t�ł͓`�����Ȃ��l�ދ��ʂ̉b�q��̌����A���ɍ��x�Ȑ��_���E�ɓ�����A���R�A�F���A�_������قNJ����邱�Ƃ��ł��镑���i�͉ߋ��ɂ͂Ȃ������ł��낤�B�o�D�����̐��E��n��o���̂ɑS�g�S�������A�|�p�ɕ�d���Ă��鉉���W�c�����܂�ǂ��ɂ��Ȃ��B���t�̕ǂ����S�ɒ��z�����l�ދ��ʂ̐��E��`���Ă���B40�N�O�ɃA�j�V���t�����߂Ċ��g���������V�A�̌��c�ŋ��ɉ������������Ă������D�́A�����ڎw���Ă����l�̐S�A���A���_�ɂ܂Łu���@�������鉉���v���A40�N�����Ă��ɓ��{�̔o�D�����ɂ���Ď������������Ă���܂����B�ǂ̂悤�ɂ��āA���̂悤�Ȑ��E�����グ���̂��A�����Ɏ���܂œ����ŃA�j�V���t���Ƌ��ɂǂ̂悤�Ȋ��������Ă����̂��Ȃǂ̎��^�Ɍ��c�̔o�D�������������܂������A�Ƃɂ���3���Ԃ̌𗬉���V�A������̎^���̗��ŁA��X���{���Ɋ���������ł����B�܂��A���X�N���ōĉ������ė~�����A���V�A���Ō��������ė~�����Ƃ̐������������܂����B
���݂܂���A���}���Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��A�����܂����B
���������̒����Ȃ̂ł����A�A�j�V���t���ŏ��ɓ��{�ŗ����グ�����c�̖��O�́A���c���A�y���W���@�[�j�G�E�A�[�g�E�V�A�^�[�A�X�^�W�I�E�\���c�F�ł��B
�Y�t���܂����ʐ^�́A�������s�������X�N�����ۉ��y��فE�����z�[���y�����A�Î��L�m�Â̗l�q�A�n���I�𗬉�A�I����Ɋϋq����̃��b�Z�[�W�������ꂽ�|�X�^�[�A�Î��L�I����̊ϋq�ł��B

�������s�������X�N�����ۉ��y��فE�����z�[���y����

�Î��L�m�Â̗l�q

�n���I�𗬉�
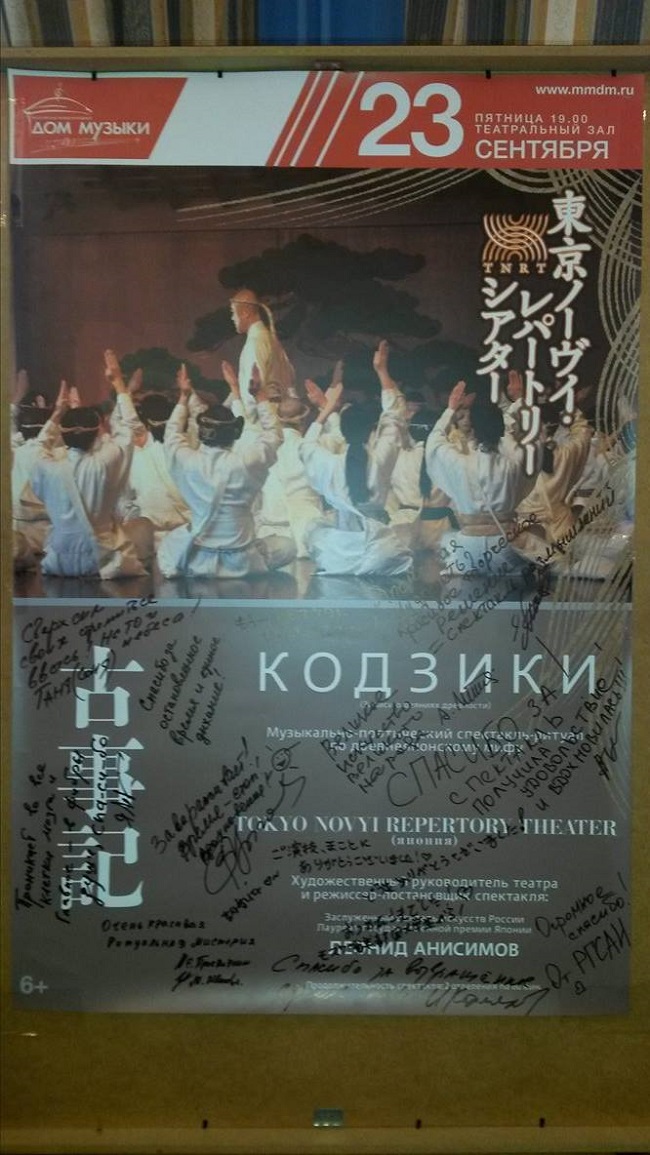
�I����Ɋϋq����̃��b�Z�[�W�������ꂽ�|�X�^�[

�Î��L�I����̊ϋq
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�X�E�Q�T�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��25���@�q���N�F��51��g�S�ϗe�Z�@������̑q�����W�����@�@���ڎ�2
���c�搶�A�F�l
�����̔��\���W�����������肵�܂��B
�x���Ȃ�܂��Ă��݂܂���B
�����͂ǂ�����낵�����肢�������܂��B
�q���N�q
���q���N�u����Љ�ɂ�����g�S�ϗe���`���Ɍ��̍L����ɂ��Ă̎Љ�w�I�l�@�v �ipdf 355KB�j
���ڎ�2
2016�N9��25���@���c����F2016�H�O���[�t�P�A���J�u���u�߂��݂������́v�i9��27���`12��13���܂ŘA��8��j�@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
�t�́u�O���[�t�P�A���J�u���v�Ɉ��������āA9��27���i�j���12��13���܂ŁA�A��8��ŁA2016�N�H�́u�����O���[�t�P�A���J�u���`�߂��݂������́v���s�Ȃ��܂��B
���s�������܂�����A���Ђ��Q�����������B
�X�E�Q�T�@���c����q
��2016�H�O���[�t�P�A���J�u���u�߂��݂������́v �ipdf 829KB�j

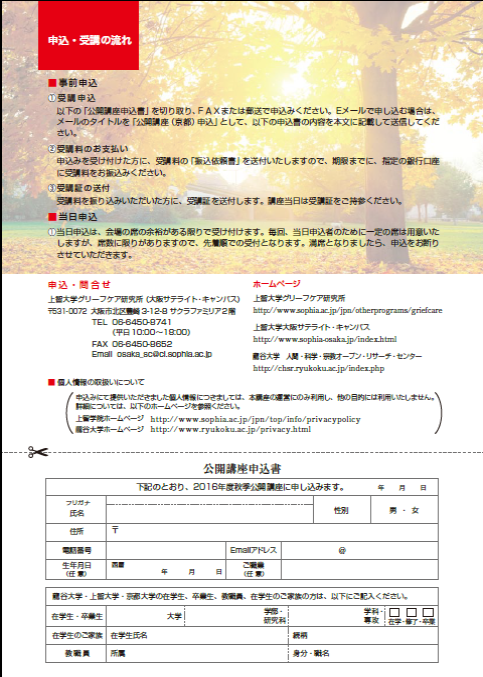
���ڎ�2
2016�N9��24���@���c����F�����O�\�O�����ԎD���E�I�O�䎛�Ɖ����@�i�Ԗ厛�j�@�@���ڎ�2
2016�N9��24��
�ӂƎv�������āA�����O�\�O�����ԎD���E�I�O�䎛���Q�q�����B
�����̐������̂́A�I�O��R�����썑�@�Ƃ����B�u�~���ω��@�v�̑��{�R�ł���B
���́A9��23���i���j19������ق�2���ԁA���X�N�����y��ى����z�[���ɂāu�Î��L�v�������������̂����A9��24���i�y�j�ߑO9��30������12��40���܂ŁA��q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ŁA�S���̏H�w���́u�@���w�v�̏���̎��Ƃ��������̂ŁA�x�u�ɂ��邱�Ƃ��ł����A���������A���Ă���ق��Ȃ������B���R�̂��Ƃ����A�����{���D��ł���B
�Ƃ����킯�ŁA�����͒�����2�R�}�̎��Ƃ��݂��������āA�I����Ă���AJR���w�ɍs���A�V�����œ��}���낵��13���ɏ�芷����JR�a�̎R�s�w�܂ōs���A�����ł���ɋI���{����V�s���̃��[�J�����ɏ�芷���āA�I�O�䎛�w�ɍ~�藧�����B
����܂ŁA�I�O�䎛�ɂ͎Q�q�������Ƃ��Ȃ������̂��B
�l���H�͑�w3�N���̎���88�Ԃ��ׂĉ�������A�����O�\�O���͕����I�ɂ����Q�q���Ă��Ȃ��B
����܂ʼn�����̂́A
��ԎD���̐ݓn���i�����10��ȏ�j
�O�ԎD���̕��͎��i2��j
���ԎD���̒��J���i5��j
��ԎD���̋������i20��ȏ�j
�\��ԎD���̏��펛�i1��j
�\�l�ԎD���̎O�䎛�i4��j
�\�ܔԎD���̊ω����i2��j
�\�Z�ԎD���̐������i8��j
�\���ԎD���̘Z�g�������i2��j
�\���ԎD���̒��@���i�Z�p���A5��j
���ԎD���̌������i3��j
�ԎD���̐������i2��j
�O�Z�D���̕��i�|�����A1��j
�O��ԎD���̒������i2��j
�O��ԎD���̊ω������i3��j
�O�O�ԎD���̉،����i2��j
�ł���B
���̓�ԎD�����܂����Q��ł��Ă��Ȃ��Ƃ����̂́A�\����Ȃ��v���ł������B
�̂ŁA�h������ω���ꏄ������Ă����˂A�Ǝv���������B
��q��w�l�b�J�L�����p�X�ł̌���i�H�w���j�̎��Ƃ́u���n�̔�r�@���w�v�ł��A�l���H����O�\�O���̂��Ƃ���{���\���鐹�n��ꏄ��̈�Ƃ��Ď��グ�˂Ȃ�Ȃ�����B
�a�̎R�s�ɂ͐�������Ȃ����炢�A���Ԃ�40��ȏ�͗��Ă���Ǝv���̂����A����ł��a�̎R�s���ɂ���I�O�䎛�ɂ͈�x���������Ƃ͂Ȃ������B
���̑O�̍���42�����͉��x���ԂŒʂ肩�������ɂ�������炸�B
�Ƃ����킯�ŁA�܂��́A�ό��}�b�v���m�F�B

�a�̎R�s�ό��n�}
���\�A�I�O�䎛�Ƙa�̂̉Y��ʒÓ��_�Ђ��ċ߂��`�B
�ʒÓ��_�ЂⓌ�Ƌ{�ɂ�2�x�قǗ��Ă�̂����B
�����āA�I�O�䎛�̗R�����L�����Ŕ�ǂށB
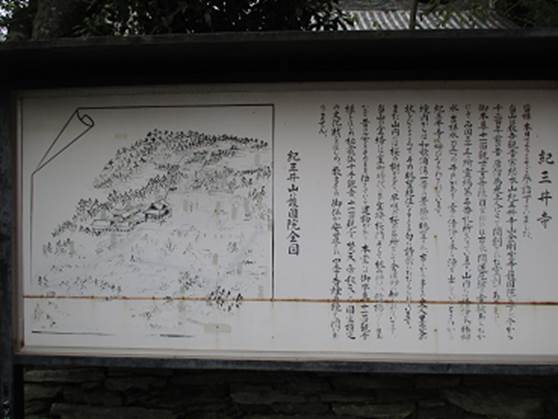
�����O�\�O�����ԎD���I�O�䎛�̊Ŕ�
�n���́A���`�ł́A��T���N�i770�N�j�A�����R�̎R��������������Ă���̂��A���̑m�E����l���ڌ����A���̌�����K�ˁA�����ŋ��F�̐��ω������������Ƃ����B�����ŁA����l�͏\��ʊω��������A���F�̐��ω�����ٓ����Ƃ��Ĕ[�߁A�镧�Ƃ��Ĉ��u�����Ƃ����̂��n�܂�ł���Ƃ����B
���̖����R�ɂ́A���A�k�����A�g�ː���3������Ƃ���A�����ŋI�O��R�̎O�Ƃ������Ƃ����B
���Ƃ��ƁA���́u�����R�v�Ƃ����̂��A�Ñ㍋���E�������̂䂩��̓y�n�ŁA�ɂ߂ďd�v�ȈӖ��������Ă����B�������A���ł���B���R�̂悤�ɁA�����ɂ͎��Ђ����܂��ׂ����Đ��܂��͂��ł���B�ł��Ȃ��̂������������炢�B
�Ƃ����킯�ŁA�܂��͉������Ă����A���߂���ցB

�I�O�䎛�����R��
���A�y�j���̌ߌゾ�Ƃ����̂ɁA�l�e�͂܂�B
�����̑O�̂��X���V���b�^�[���܂��Ă���B
�ǂ������̂��H
�l�e�����Ȃ�����̂ł́H
�����O�\�O���̑��ԎD���Ƃ��ẮA�Q�q�҂����ȉ߂��͂��Ȃ����H
�ƁA�S�z�ɂȂ�B

�I�O�䎛�R��
�Ƃ�����A�܂��́A�Q�q�B
�K�i���e�Ɍ䓰����������B
�܂��́A�u����ω��v���B

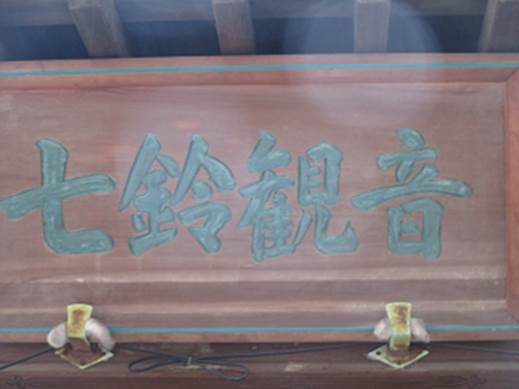
�܂��́A���̓o����́u����ω��v���ŁA�ʎ�S�o�ꊪ�t��A�@���L��t�B
�����āA���������Q�q�B
�E��ɂ́A�������q���J���Ă���䓰���B

�����Ē����K�i�ɒ���B������Ƃ����B

������
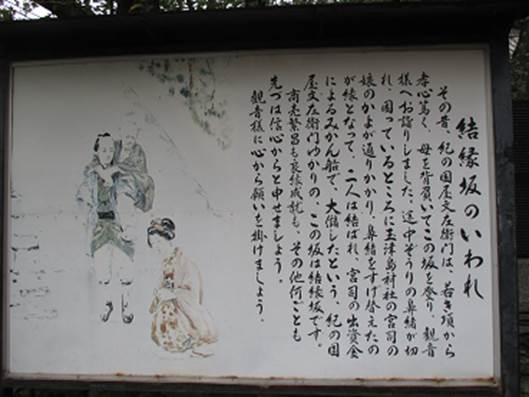
������̗R�������Ŕ�
���̌�����̗R�����Ȃ��Ȃ��B
�M�S�[���e�F�s�̋I�ɍ����卶�q��́A���w�����Ă��̍���悭����Ă��Q�肵�Ă����B
������A�Q�q�r���ő����̕@�����ꂽ�B
���̎��A�ʒÓ��_�Ђ̋{�i�̖��̂��悳���R�ʂ肩�����āA�ꂽ�@����t���ւ��Ă��ꂽ�B
���ꂪ���ŁA2�l�͌������A�ʒÓ��_�Ђ̋{�i�̎���������ɂ݂���D���]�˂ɏo���đ�ׂ������A����z���Ă������Ƃ����̂ł���B
�����ŁA���́u������v�́A�u�lj����A�v�Ɓu�����ɐ��v�̌��ʂ���ƗL����Ă���Ƃ��B
�ȁ`��ف`�ǁB
�����āA����ɔg�ؕs�����B

�g�ؕs����

�g�ؕs����
������Ɂu2016�N�@����g�@���@�i���Α叫�R�A�C�j300�N�v�̛�B
�g�@�́A1716�N�ɓ��얋�{�̑�8�㐪�Α㏫�R�ɏA�C���A1745�N�܂ŁA�݈ʂ�30�N�ɋy���N�Ƃ���铿�쏫�R�ł���B

����g�@�����Α叫�R�A�C300�N�̛�

�I�O�䎛�O��


�����m�Ԃ̋��
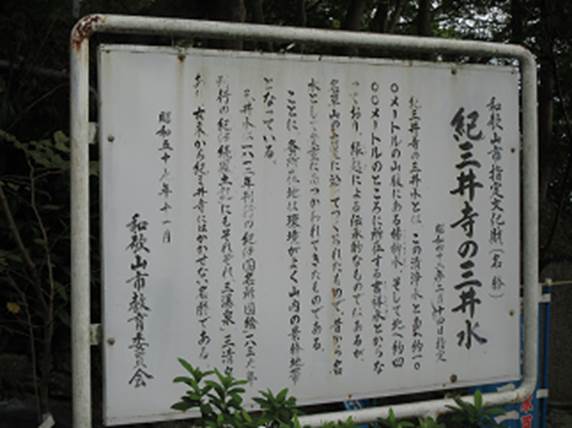
�I�O�䎛�̎O�䐅�̐�������

���V����A����@��

�g�����t

�g�����t��
�����K�i��o���ƁA�Z�p�����B

�Z�p��
�Ȃ��Ȃ��A���i������B

�{���Q��
�悤����ƌ������ɖ{���������Ă���B
���̍��苫������̂悫���]���J���Ă���B
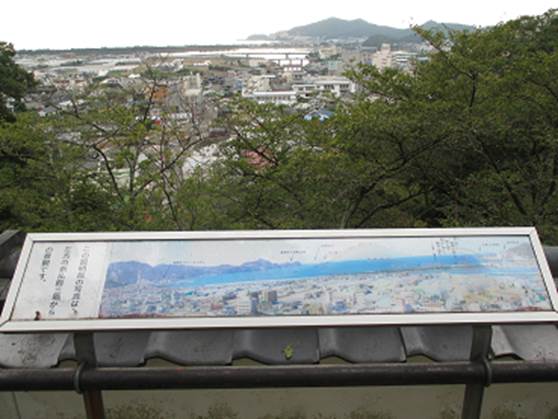
�a�̂̉Y�̒��]

�n�}�Ŕ�
��i���ȁB

�a�̂̉Y
�a�̎R�s���܂�̓���F������̘a�̂̉Y�̒n�͌��\�C�ɓ����Ă����悤�B
���̋I�O�䎛�̋����ɂ́A��킪�B
������A����F��D�݂���킢�B

�I�O�䎛�̑��
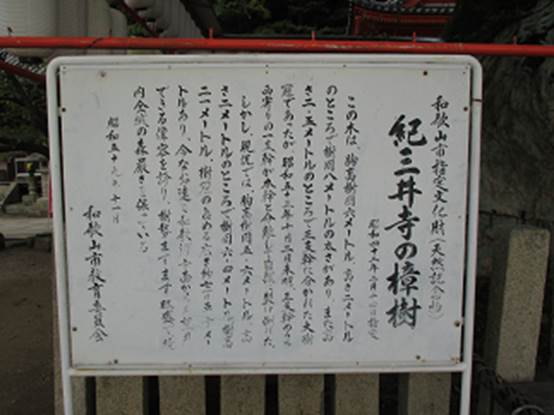
�����̐�����

��t��

�{���Ƒ���

�I�O�䎛�{��


�{���ŁA�ʎ�S�o�ꊪ�t��A�ΓJ�E���J�E�@���L�̎O��̐_���t�B
�т邳�܂ł�B

�o��ḑ��ґ�

�o��ḑ��ґ�
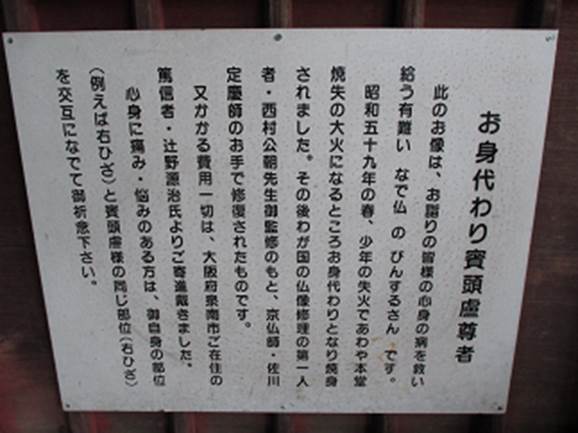
�o��ḑ��҂ɂ��Ă̐�������

�d�v�������̑���
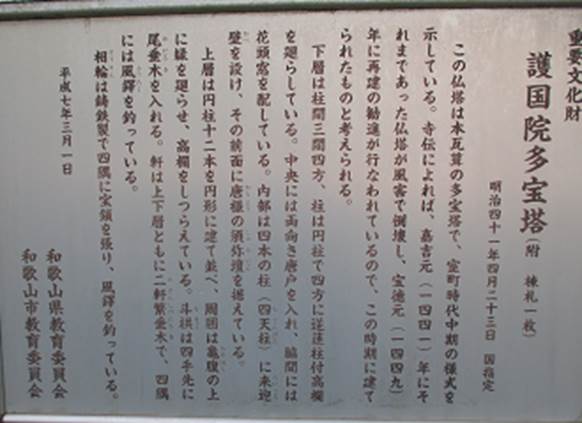
��������


���a

�ؑ��̑���������ؗ����Ƃ��ē��{�ő�̊ω���F��
���a�ɂ́A�ؑ��̗������Ƃ��ē��{�ő�̑���\��ʊϐ�����F�������u����Ă����B
�����ł��A�ʎ�S�o�ꊪ�t��Ɩ@���L��t�B�����ɖ苿���B�G�R�[���Ȃ���B

�a�̂̉Y�̊C
��������a�̂̉Y���ēx�]�ށB
�[�z�̉e���C�ʂɗ����Ă���B
��i���ȁB

�a�̂̉Y�̊C
�a�̂̉Y�̊C�̎c�Ƃ�]���ɏĂ��t���A�e�����F�l�̊h���Z�E�̂��������@�ɋ}���B
�����@�ɂ��A�a�̎R������l�Ԃ̏\��ʊϐ�����F�����u����Ă���B
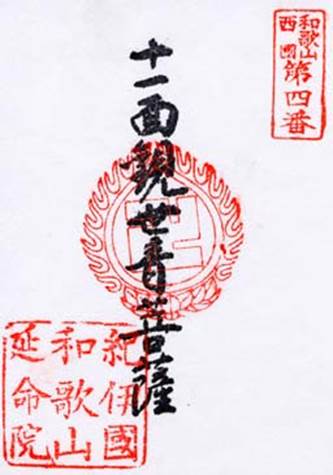
���

�^���@�����h�����@�i�ʏ́F�Ԗ厛�A�a�̎R�s�鏠��6-9-1�j
�ՏƎR�����@�������́A�ʏ́u�Ԗ厛�v�ƌĂ�Đe���܂�Ă���s���̖����B
���̉����@�͂��Ƃ��Ƃ͓��O�{�̐_�{���Ƃ��đn�����ꂽ�Ƃ��������R���������Ă���B
�]�ˎ��㏉���̌��a2�N�i1616�N�j�A�~�M��l�̎��A���ݒn�̑鏠���Ɉڂ����Ƃ����B
�����@�̋q�a�ƍg�k�h��̐Ԗ�́A����2�N�i1805�N�j�ɋI�B�ˎ�ώ��݉@�d�ςɂ���i���ꂽ�B
�{���ɂ́A�u��������t�v�Ƃ��Ă��O�@��t�������u���Ă���B
���̑��́A�~�M��l�̖������ɂ�葢��ꂽ�Ƃ����B
�����ɁA����n�����A�q��E���q�n�����A���䗅���������āA�ߗׂ̐l�тƂ̕�炵�̒��̐M�ɗn�����݁A�g�ݍ��܂�Ă���B
�{���̖{���́A�����E�̑���@���ł���B
���̃x���K���F�́u�Ԗ�v�Ǝ���ŕ������ł߂��������u�a�̎R���ӂ邳�ƌ��z�i�Ϗ܁v����܂��Ă���B
�m���ɁA�m���ɁA�f�G�Ȋ������B

�Ԗ厛

��n����


�{��

�{�����̂���

�{�����̂���

�H�̂��ފ݂̂���

�{�����̂���

����F��Ƃ̂���

����Ƃ̂���
���̉����@�́A����F��̐��Ƃ̕�ł��邱�Ƃł��m���Ă���B

�����ɁA����F��̕������[�߂�Ă���B

����F��̕������[�߂�ꂽ����B
���̂���Q�̈�p�ɓ���F��̕������[�߂��Ă���B
���̑O�ŁA�ʎ�S�o�ꊪ�t��A�@���L��t�B
����ŁA�����͎v���c�����Ƃ͂Ȃ��B
�h���Z�E�Ɉ��A���ċA�낤�Ǝv�������A���ɔ\���ςɍs���Ă���Ƃ��B
�悫�����킢�\�A����I


�u�a�̎R���ӂ邳�ƌ��z�i�Ϗ܁v����܉����@����
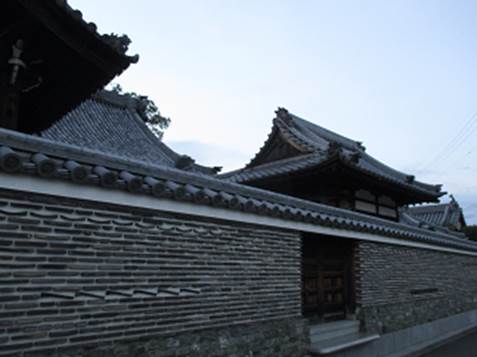
�u�a�̎R���ӂ邳�ƌ��z�i�Ϗ܁v����܉����@����
���̖{�����C���v�H�Ȃ���1995�N5���A�킽���͂��̖{���̗��c���ɎQ�A���߂Ă�������̂������B
���x���A������ɂ͔��߂Ă����������B
�h������A�������肪�Ƃ��B
���ɁA�ŐV���w�u���X�s���`���A���w��7���@�X�s���`���A���e�B�Ə@���x�iBNP�A2016�N8�����j��u���Ă����܂��B
�ƁA�������āA�����@�O����JR�a�̎R�s�w�s���̃o�X�ɏ���āA���s�ɖ߂����̂������B
��������킢�\�`�B
���ڎ�2
2016�N9��24���@���c����FRe�F���X�N���Î��L�����@�@���ڎ�2
�ؑ��͂�݂���
���肪�Ƃ��������܂��B
�{���̓s���ŁA�Ԃɍ����悤�ɋA�����������ł��̂ŁA���S�z�Ȃ��悤�ɁB
���ƌ����Ă��A�{���D��ł��̂ŁB
�X�E�Q�S�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��24���@�ؑ��͂�݁F���X�N���Î��L�����@�@���ڎ�2
���c����@�搶
���������l�ł����B
���j�I�ȃ��X�N���ł̌Î��L�̏㉉��U����Ă̂��A���A
�����Ȃ���A�ǂ݂܂����B
�ȉ��A�m�[���B��FaceBook�ɑ�D�]�E�听���̂�������܂����B
���c�搶�̖ڂŌ������������Ȃ��������ƁA
�c�O�ł���������܂���B
�i���̂��߂Ƀ��X�N���܂ōs���ꂽ�̂ł��傤�B���M�ɏ���āA�A�B�j
�����N�������̂��A�S�z���Ă���܂��B
���d���͖����ɍς܂��ꂽ�̂ł��傤���B
https://www.facebook.com/tokyonovyi/photos/a.216028121767151.46600.186698851366745/1076283329074955/?type=3
9.24
�ؑ��͂��
���ڎ�2
2016�N9��24���@�I�����a�F�]���i���{�搶�j�@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
���{�搶��育�ē��̂��������ŁA���{�搶��PC�s���̂��߁A
����Ƀ��[���̈ꕔ��\��t���ē]�������Ă��������܂��B
���c�搶�A�ǂ������������������B
�I�����a�@�q
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�S�g�ϗe�Z�@������
�����o�[�̊F�l
�ߓ��A�W�J�M��NHK���������A���\���グ�����{�ł������܂��B
�������̕ύX������܂������Ƃ����A���\���グ�邱�Ƃ��x��Ă���܂��B
�\�������܂���B�\�肳��Ă����̂�9��18���ł������A
�p�������s�b�N�����̂��߁A�������ύX���������܂����B
�W�J�M�̕����́A
�{��9��24���i�y�j���j�ANHK BS�P 22�F00�|22:50
�h�L�������^���[WAVE�u�W�J�M �����g���h���`�A�����J �t�����_�̓����`�v�ł������܂��B
���A�����x��܂������Ƃ�[�����l�ѐ\���グ�܂��B
���Q�l�ɂȂ�K�r�ł������܂��B
���̃��[���́A�I���搶�ɂ����k�������Ă��������A���������������Ă���܂��B
��낵�����肢�\���グ�܂��B
���{ �_�q
���ڎ�2
2016�N9��24���@���c����F9��26���i���j��51��g�S�ϗe�Z�@������ē��i���\�ҕύX�̂��m�点���܂݂܂��j�@�@���ڎ�2
�݂Ȃ���
���T�̌��j����9��26���ɁA�u��51��g�S�ϗe�Z�@������v���AJR�~�c�w���}�~�c�w����������4�`7���̏�q��w���T�e���C�g�L�����p�X�ōs�Ȃ����Ƃ��ē����Ă���܂����B
��51��g�S�ϗe�Z�@������
�����F2016�N9��26���i���j13���`17��30��
�ꏊ�F��q��w���T�e���C�g�L�����p�X���O���[�t�P�A�������i�T�N���t�@�~���A����2�K�A����}�~�c�w����������k��4���j
���\�@�A���^���W�����[�i���s��w��w�@�l�ԁE���w�����Ȕ��m�ے��E�����l�ފw�j�u���㒆���ɂ����鎀�̑̌��v���O�����̔w�i�Ɛg�S�ϗe�ƌ���V���[�}�j�Y���v�i����j
���\�A�q���N�i���w�@��w�����E�Љ�w�j�u����Љ�ɂ�����g�S�ϗe���`���Ɍ��̍L����ɂ��Ă̎Љ�w�I�l�@�v�i����j
�i��F���c����i��q��w�O���[�t�P�A���������C�����j
�e60�����\�{60�����c
������́A�\��ʂ�s���܂����A���\�҂���l�ύX�ɂȂ�܂��̂ŁA���m�点���܂��B
���\�\��҂̃A���^���W�����[������̂��߁u�g�S�ϗe�v���A�c�O�Ȃ��瓮���Ȃ����Ï�Ԃɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�s���`�q�b�^�[�Ƃ��Ă킽�������\�����Ă��������܂��B
�킽���̔��\�^�C�g���́A�u���[���V�A���Ȃ��g�S�ϗe�����̉ߋ��Ɩ����`�����ƃ��V�A���ђʂ�����́v�Ƃ��܂��B
���\���e�́A
�@�����Ƃ̊ւ��i1990�N����10��قǖK��B��ɋC���V���|�W�E���Q���j�ƃ��V�A�Ƃ̊ւ��i1990�N8�����\�A�̉F���֘A�{�݁y�F����s�m�̊X�E�o�C�R�k�[���̃��P�b�g�ł��グ��n�z���@�A�E���W�I�X�g�b�N�̑�w�ł̍u�`�ƍ���̃E���W�[�~���K��Ȃ�3��j
�A�����ƃ��V�A�ɂ����鐭���Ə@���i�g�S�ϗe�Ƃ��̋Z�@�𐢂ɑi�����@���ƃI�E���^�����������ň����N�������g��j
�B���V�A�`���[���b�p�Ɠ��{���Ȃ������Ƃ��Ẵ����S�����ƃ����S���R�`13���I�����S���̓������h���̋R�n��
�C���z�E�����S���E���N������{�ɂ����炳�ꂽ�u�L�v����b�R�̐_�������̏o���
�D���V�A�ɂ�����w���s�x�i�h�X�g�G�t�X�L�[�j�Ɓw�Î��L�x
�E���[���V�A�����Ԗ�������
�F���̑�
�Ȃǂł��B
��낵�����肢���܂��B
�Ƃ���ŁA
�q���N�l
�����̃��W�������20��������Ď��Q���Ă���������K���ł��B
�܂��A���O�ɗ����Ȃ������o�[������Ǝv���̂ŁAML�ɑ��M���Ă���������ƍK���ł��B
��낵�����肢���܂��B
�X�E�Q�S�@���c����q
���ڎ�2
2016�N9��23���@���c����F���V�A�������@�@���ڎ�2
���V�A�����@2016�N9��19���`23��
-----------------------------
2016�N9��20��
��6���A���V�A�A�E���W�[�~���s�̃z�e���Ŗڊo�߂�B
���V�A���J�|�p�Ƃ̃��V�A�l���o�ƂŁA�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̌|�p�ē߂Ă��郌�I�j�[�h�E�A�j�V���t���ƁA�ނ������铌���m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̌��c������40���Ƌ��ɂ��̒n�ɂ���Ă����B
�A�j�V���t���Ƃ́A����12��18���i���j�ɁA�{�g�S�ϗe�Z�@�������Â̍��ۃV���|�W�E���u������ƃX�^�j�X���t�X�L�[�v���J�Â���B

����2�T�ԁA���V�A�̃E���W�[�~���s�̒��S�ɂ���E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ŁA�����t�F�X�e�B�o�����J�Â���Ă���B�����ŁA�A�j�V���t���̉��o�ɂ��h�X�g�G�t�X�L�[��́u���s�v������9��21���ɏ��Ҍ��������̂ł���B
���̌�A���X�N���Ɉړ����A9��23���ɁA�킽����������w����Î��L�x������ɃA�j�V���t�������o���������m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�́w�Î��L�x���㉉���邱�ƂɂȂ��Ă���B�{���ɗL����Ƃł���B���̂��Ƃ����蓯�s���@�Ƒ����������A�����ɁA���V�A�̏@���{�݂�g�S�ϗe�Z�@�̂���悤��_�E�v�z�A�l�X�̊�����̂ɂ��ڂ������Ă݂����B���ɁA���V�A�����̋���₻���ōs�Ȃ��Ă���T��V���A�l�X�̐M�Ȃǂɒ��ׂĂ݂����B
���s���琬�c��`�`���X�N�����o�R���A���X�N���̓�����200�L���A���V�A�ŃL�G�t�����Ɏ���2�ԖڂɌÂ��ƌ�����Ós�E���W�[�~���ɓ��������B�����͍��9��19���̐[��23���������B�a�̂��߃��X�N������o�X��5���Ԉȏォ�������B��s�@�̃t���C�g������ƁA�����20���ԋ߂��Ԓ��ɂ������ƂɂȂ�B
�����́u���s�v�㉉�O�ɁA�܂��͑��ɓy�n�̐���ɂ����A���邱�Ƃ�����A�A�j�V���t����⌀�c���݂̂Ȃ���ƈꏏ�ɃE���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����̕��ْ�����ɉ������A�E���W�[�~���s�������������B
�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����O�ƁA�N�j���[�M�j���X�J������O�ƁA�{���K��������낷�u�˂̏��3�����Ŗ@���L���t�B�z�e���ł͂������A���̂��߂̒��ŁA�킪�O��̐_��̐ΓJ�E���J�E�@���L���t�������A�߂��̃��V�A�l�h���q�͂����������̉��ɂ͂т����肵�����Ƃ��낤�B
���̃E���W�[�~���Ƃ����X�́A���āA�E���W�[�~�������̎�s�ł��������A���s�Ɏ����Ƃ��낪����Ɗ������B���s�͓ޗǂɎ������{���̌Ós�ł��邪�A���̃E���W�[�~�����A�L�G�t�Ɏ������V�A���̌Ós�ŁA�Ȃ��炩�ȋu�̏�ɂ���B
�X�S�̂��u�˂̏�ɂ���̂ŁA�y�������ߓn�����Ƃ̂ł��钭�]�̂悢�n�_���e���ɂ���B
�����A���w�����Ƃ���ł́A���ɐ��E��Y�ƂȂ��Ă���E�X�y���X�L�[���@�̃o���b�N�C�R���悪�����������B�o���b�N���p���C�R����Ƃ��Ď��߂��L���X�g�����@�Ƃ��Đ��E��ԈႢ�Ȃ��B����قnj����ȂƂ������A�����Ƃ������A�����I�ȃC�R����͌������Ƃ��Ȃ��B�܂��ɁA�C�R���E�}���_���B�o���b�N��䶗����E�ł������B
�s���̎�v�{�݂ɂ��āA�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����̎x�z�l����z���Ă��ꂽ�������ē����A���J�Ȑ��������Ă��ꂽ�B�ޏ��̐����ł́A992�N�ɃE���W�[�~����������n��ꂽ�Ƃ����B�����ɂ́A�傪5����A�����c���Ă���̂��A1164�N�ɑ����Ƃ��������̖�ŁA���̕\�ɃL���X�g�̃C�R���A���ɐ���}���A�̃C�R�����`����Ă���B
�����A13���I�����A�����S���E�^�^�[���R�ɍU������A���N�ɂ��킽�錃�����킢�̌�A�I�ɁA1239�N�A�E���W�[�~��������̓����S���R�ɋ����A���̌�A���V�A�̒��S��s�@�\�́A�L�G�t�A�E���W�[�~���Ɏ�����O�̎�s���X�N���Ɉڂ����B
�����[���̂́A���{�������S���ɐN�U���ꂽ�̂��A1274�N�̕��i�̖���1281�N�̍O���̖���2�x�ŁA�ÌR�͑䕗�ɏP���āA���́u�_���v�ɓ��Ă��đގU�����Ƃ���Ă���_���B���̂ق�40�N�O�Ƀ����S���R�́A�E���W�[�~������������j���A���X�N���ɂ܂Ői�R���Ă����̂��B���̋R�n�R�c�����S���R�̋��Q���ׂ������ւ̊g���̈ӎu�Ƃ��̐퓬�\�͂Ǝ������̐��܂������_�Ԍ���v���������B�u�����v�Ƃ���Ă��鎖�Ԃ����E�j��傫���h��ւ����̂��B13���I���E�v���A�����S�����m�̓��[���V�A�嗤���A����A�n�����A�k���������̂������B������A�����S���R�́B
�Ƃ���ŁA���̉����̖���ӂɂ͓y�ۂ��z������Ă������A�G�J�e���[�i2���i1729�|1796�j�����X�N�����痈�����ɁA�n�Ԃ��ʂ�Ȃ�����Ɖꂽ�Ƃ����B
���̃G�J�e���[�i2���́A���݂͐��E��Y�ƂȂ��Ă���A�E���W�[�~���̍ō��ő�̏@���{�݂ł���E�X�y���X�L�[�吹���i���_���A�Q�吹���j�ɑ��z�̊����A����ɂ��A�o���b�N�l���̑s��E�����ȃC�R���悪��R�`���ꂽ�Ƃ����B���z2~3���~�ɋy�Ԋ��Ƃ��B���̃E�X�y���X�L�[�吹����1158�N����1160�N�ɂ����đ���ꂽ�Ƃ����B���{�ł́A�ی��̗��i1156�N�j�E�����̗��i1159�N�j���N�����Ă���A���~�̌����u���҂̐��v�̓����̍��ł������B
���̃E�X�y���X�L�[�吹���̒��ɃA���h���C�E�{�S�����u�X�L�[�Ȃǂ̑���̈�̂����[����Ă���B�����̃C�R����́A�A���h���C�E���u�����t�i1360�|1430�j���`�����B���{�ł́A������i1363�|1433�j�����Ă��鍠�̂��Ƃł������B���u�����t�Ɛ�����Ƃ́A�قƂ�Ǔ������������A�����̍ō����͎҂̉��ŁA�|�p�E�|�\�Ɋւ�錆�o�����˔\���J�Ԃ������B
���u�����t�́A1405�N���ɏC���m�ƂȂ�A�u�����O�ҁv�i���O�ʈ�́j�Ȃǂ̃C�R�����`�����B���u�����t�́A����܂ŃM���V�����̊��`���l������X���u�l���̊��`�������ɓ]�������B���V�A�l�ɐe���݂₷���C�R�����`���n�߂��ŏ��̐l���Ƃ����B�w�f���\�����X�x�̊ēA���h���C�E�^���R�t�X�L�[�́A1967�N�Ɂw�A�������C�E���u�����t�x�삵�A1969�N�̃J���k���ۉf��Ղ̍��۔�]�Ə܂���܂����B
���u�����t�̏������C�R����̑s�傳�ɂ͋���������B�������B�X�����B�~�Q�����B���t���������B���������A�����B�Ƃ����ق��Ȃ������B�E�X�I
�����āA��A�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ŁA���㕗�ɃA�����W���ꂽ�`�F�[�z�t����́u�����߁v����ł��ό������B�����͂��悢��A�j�V���t���o�A�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�ɂ��u���s�v�㉉�ł���B�ڂ��M�ɂ��Č��͂������B
-----------------------------
2016�N9��21��
��7���N���B�ߑO���́A�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ŁA�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̃��n�[�T�������w�B
�A�j�V���t���吺���グ�Ȃ���A���ɓ]�����̏Ɩ��Ɖ����̃_���o���B�ْ���������B�d���݂�s����ȏƖ����̊m�F�Ƌ@���Ŏ�Ԏ�钆�A�s���s���ƒ���߂���C���B
�m�Â��A3���Ԃ��ׂĂ����n�[�T���ł���]�T�͂Ȃ��̂ŁA��v�ȃV�[���̔����m�ÁB�ő�������Ō����X�^�b�t�B
�A�j�V���t�̑吺����ԁB���V�A��Ɠ��{��Ɖp��̃`�����|���ŁB�݂ȕK���ł��炢���Ă����B
�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�́A2004�N�ɁA���I�j�[�h�E�A�j�V���t�����o�w�����Ă���3�̌��c�A���c���ƃy���W���@�[�j�G�i�u�Ǒ̌��v�̈Ӗ��j�A�[�g�E�V�A�^�[�ƃX�^�W�I�E�\���c�F�i�u���z�v�̈Ӗ��j���������Đݗ����ꂽ�B
�ȗ��A�X���j�X���t�X�L�[�V�X�e����Ǝ��ɉ��߂�����グ���X�^�j�X���t�X�L�[�`�A�j�V���t�����ŁA
�@�S�̉h�{�ɂȂ鉉��
�A�������ɑ����ɍs������
��Nj��������B
�u�������ɑ����ɍs���v�Ƃ́A������ʂ��Ď������g�̋C�Â���F����[�߁A�l�ԓI�������ʂ����Ƃ������Ƃł��邪�A�����ɂ̓X���j�X���t�X�L�[�V�X�e���Ɋ�Â��Ǝ��̐l�Ԋw������B
�X���j�X���t�X�L�[�́A���҂ɁA
�@���ۑ�
�A�ђʍs��
�B����
��3��O��I�Ɉӎ������邱�Ƃ���ɓ˂����Ă����Ƃ����B
�u���ۑ�v�Ƃ́A�������l���ň�ԋ��߂Ă�����́B
�u�ђʍs���v�Ƃ́A���́u���ۑ�v�ɂǂ������Ă��邩���h������s���B
�u���́v�Ƃ́A���́u�ђʍs���v�̒��ł��́u���v���u����Ă���͂��F�����邱�ƁB
���Ƃ��A���c����́u���ۑ�v�́u�y�����������v�A�u�ђʍs���v�͉Ȍ��F�g�S�ϗe�Z�@�������NPO�@�l�������R��w�⋞�s�`�������̐X���i���c��Ȃǂ̊������т����h������u�n�����̟Д��v�A�u���́v�͂��̈��̋�̓I�Ȉʒu��͂��炫����ʁE�e���ȂǂȂǁB
�X�^�j�X���t�X�L�[�́A�o�D�琬�̂��߂ɖ��m�ȃJ���L�������ƃ��\�b�h����������A���̌�̃��V�A�̉�����w�͂�������̂悤�ɃJ���L�����������Ďw�����Ă���Ƃ����B
�@�D�p
�A�Y�ȕ���
�B�b�@�i�����@�E����E���H�C�X�g���[�j���O�j
�C�X�e�[�W�E���[�u�����g
�D�_���X
�E���y
�F�N�w�E�S���w
�G�����j
�H���C�N�p
�I�E�w�i�t�F���V���O�j
�J�A�N���o�b�g
�ȂǁB
�Ƃ���ŁA�{�g�S�ϗe�Z�@������̉�X�ɂƂ��đ�ϋ����[�����Ƃ��A����̃��V�A�K��Ŗ��m�ɂȂ����B���́A�X�^�j�X���t�X�L�[���u�����@�c�L�[�̐_�q�w��h���t�E�V���^�C�i�[�̐l�q�w�ɑ�ϋ����������Ă��Ȃ�ǂ�ł����Ƃ������ƂȂ̂��B���A���Y�������̗��ɐ_���`�v�z�Ɛ_���`�|�p����忂��Ă���Ƃ������Ƃ��B�����ÁX�B
�Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�i�x�]�V���A�����ЁA2015�N�j�ɂ́A1910�N��ɃX�^�j�X���t�X�L�[�����[�K�Əo��A�u�v���[�i�v�Ƃ������[�K�p����g���Ĕo�D�w�������Ă����Ƃ����B
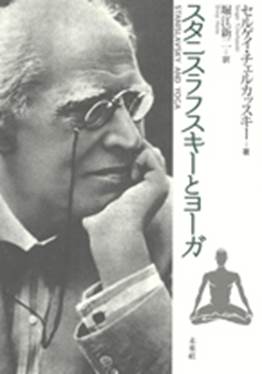
���҂̃Z���Q�C�E�`�F���J�b�X�L�[�iSergei Tcherkasski�j�́A�A�j�V���t���l�A���V�A�A�M���J�|�p�ƂŁA�T���N�g�E�y�e���u���O����������w�����ŁA�o�D�w�Ȏ�C�߂Ă���B���o�ƂŁA�|�p�w���m�ł�����B�{�̒��ҏЉ�ł́A�u���E��40 �ȏ�̉����w�Z�ȂǂŃX�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���Ɋ�Â����[�N�V���b�v���J�ÁA���{�ł�4 ��s�Ȃ��A2015 �N��5 ��ڂ��s�Ȃ���B20 ���I�̃��V�A�̉��o�ҋ���Ɋւ���_���ŏC�m�����A�_���u�X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���̐i���@�\�@�{���X���t�X�L�[�A���[�E�X�g���X�o�[�O�̉��o�E�o�D���犈���v�Ō|�p�w���m�����擾�i2012 �N�j�B���̂ق��ɁA�w�X���C�V�����G�t�@�o�D�A���o�ƁA���t�\�\�킪�t�̎t�x�i2004 �N�j�A�w�X�^�j�X���t�X�L�[�ƃ��[�K�x�i2013 �N�j�A�w�X���[���t�̉������h�x�i2013 �N�j�Ȃǂ̒���������B�v�Ƃ����B
�A�j�V���t�́A���V�A�A�M���J�|�p�ƂŁA�����m�[���C�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̌|�p�ēł��邪�A1993�N�Ƀ��X�N���|�p�������u�ǂ��Łv�ő听���������߁A���̉��o�ɑ����V�A���J�|�p�Ƃ̏̍���^����ꂽ�Ƃ����B���N���{�ɏ��ق���āA�u���A�N���������ł��Ȃ��Ɓv �̋������o�ŕ������|�p�D�G�܂���܂��Ă���B���{�A���V�A�A�A�����J�ȂǍ��ۓI�ɉ���������W�J���Ă���B�����āA�{�N�A�A�j�V���t�́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ւ̓��\�\�V�X�e���̓ǂݕ��Ɨp��99�̓�x�i���m�J�A����n�O�E�㐢���y��A2016�N4���j���o�ł��Ă���B�A�j�V���t�͂܂��A2007�N�ɁA���V�A�`���|�p�𐢊E�ɕ��y�����Ă���v���ɑ��ă��V�A��������Z���t�B�[���E�T���t�X�L�[���_��������^����Ă���B
�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�́A2004�N�ȗ��A�A�j�V���t���o�ɂ��A�`�F�[�z�t��i�u�ǂ��Łv�u�����߁v�u���̉��v�u���[�j����������v�u�O�l�o���v�Ȃǂ����X�Ə㉉���A�����āA�ߏ��卶�q��́u�]����S���v�ɒ���B����ɂ́A2007�N�ɋ{����u��͓S���̖�v�A2008�N�ɃV�F�C�N�X�s�A��u�n�����b�g�v�A2011�N�Ƀh�X�g�G�t�X�L�[��uidiot�`���s���`�v�A2012�N�Ƀu���q�g��u�R�[�J�T�X�̔��n�̗ցv�A2014�N�Ƀx�P�b�g��u�S�h�[��҂��Ȃ���v�Ɓw�Î��L�`�V�ƒn�Ƃ��̂��̉˂����x�A2016�N�ɃM���V���ߌ��u�A���e�B�S�l�[�v�Ɓu���f�B�A�v�Ȃǂ��_������I�ɏ㉉���Ă��Ă���B�����������N�̊������тƉ^�c�̓K������]������āA�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�́A2015�N�ɓ����s���u�F��NPO�@�l�v�Ƃ��ĔF����Ă���B
���̓����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[���A���������āA2011�N�����́u���s�v��2014�N�����́u�Î��L�v���A���V�A���̌Ós�E���W�[�~���Ƒ�O�̌Ós���X�N���ŏ㉉����̂ł���B2004�N�̓����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�����グ������A�u�C���X�s���[�V�����ւ̓��v�i2004�N�j�Ȃǂ̃V���|�W�E���ɖ���̂悤�ɎQ�����Ă�����Ƃ��ẮA���S���ʂ̂��̂�����B
�A�j�V���t�́A�u��v�ł͂Ȃ��A�u����v���͂��炩����Ɣ���B�u����v�́u�S�̉h�{�v�ɂȂ邪�A�������A�u����G���[�V�����v�͗L�Q�ɂ͂��炭�B����Љ�̂悤�ȕ��������ł́A�[���u�S�̉h�{�v�Ƃ��Ắu����v���͂��炩���邱�Ƃ͋H��ŁA�Q�����������퐶���̒��Łu��v�̔g�ɓM��Ă���B���́u��v���[���u����v�A�j�Ă���B���ꂪ�����́u������̖��v�ł���B
���������āA����Љ�ɂ�����^�́u������̃P�A�v�Ƃ́A�u��v�𗣂�āu����v���͂��炩����g�S�ϗe�Z�@���K�v�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B�A�j�V���t�̒���u�X�^�j�X���t�X�L�[�ւ̓��v�Ƃ́A���̂悤�ȁu�S�̉h�{�v�Ƃ��Ắu����v�̐[�݂Ƃ��̂͂��炫�ɓ��B���邱�Ƃł���B�����āA�|�p�Ƃ̎g���Ƃ͂��́u����v���Ăъo�܂����Ƃɂ���Ƃ����B���������u����v�ɑi��������|�p���N���G�C�g���Ă����l�Ԃ��K�v�Ƃ��Ă���ƃA�j�V���t�͎咣����B
21���̖�18������A�j�V���t���o�ɂ��w���s�x���㉉���ꂽ�B�x�e�����݁A3���ԗ]�B�����Ƃ��ア�������Ƃ��������u�h���E�L�z�[�e�v�̂悤�ȁA�u�L���X�g�v�̂悤�ȃ��C�V���L�����̑��݂��яオ�点��B�R���A��X�����A���C�ŁA���^�ȍ��B���C�V���L�����݁B�h�X�g�G�t�X�L�[�͂��́u�������v���͋ɂ܂�Ȃ��l�Ԃ�`�����B���̃��C�V���L���������\�̂悤�ɁA�A�j�V���t�͉��o�����B
�\�̂悤�ȃh�X�g�G�t�X�L�[�́u���s�v�B
�~�X�e���[�i�������j�ƃ~�X�e���A�X�i�_�錀�j���n���������悤�ȉ����B�@�ה����ȐS�����B�x���`�ŐQ�Ă��郀�C�V���L����҂̔w�ォ��A�O���[���ƃi�X�^�[�V���������čŌ�̌��t����Ƃ���Ȃǂ͋S�C���镡�������\�̐��E���霂������B
�r�����S�[�W���Ƙa�����C�V���L���B2�l�X�T�m���̂悤�ȃ��S�[�W���ƃ��C�V���L���́A���C�Ǝc�s�̌����B�܂��ɁA�X�T�m���Ԃ�ł���B
�����ɁA�r���i�X�^�[�V���Ƙa���A�O���[�������ނ̂����A����܂����G���܂���悤�ȍ����̖��ɒN�����u�K���v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ߌ��ƔߎS�̋ɂ݂ɗ�������ł����W���B�����䂦�̔j��̖��H�Ƃ����̂�����ӂꂽ���������A���̃��S�[�W���ƃ��C�V���L�����w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̃h�~�[�g���[�i�~�[�`���j�ƃA���N�Z�C�i�A�����[�V���j�ɂȂ���A���̊Ԃ�����Ɂu���G���܁v�����Ă����C�����i���[�j���j�ƃX�����W���R�t��
�h�X�g�G�t�X�L�[������A�l�Ԃ́u��v�Ɓu����v���a瀂Ɛ[�݂�O�ꂵ�Ė\���Ă݂���l���B�e�͂Ȃ���B
���́u���s�v�㉉���I����āA�X�^���f�B���O�I�x�[�V�������N�������B�A�j�V���t������ɏ�����B���芅�т̒��A���{����͂��E���W�[�~��������܂ł���Ă��������m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̌��c����l�ЂƂ�̎���A�j�V���t����������Ɓ@�����Ă������B
�������I����āA12���߂��܂Ń��V�A�̉����l�����ƍ��e��B���X�N����w�̏����S���w�������w���s�x�����̊��z�Ɠ��{�l�̐S���͂��Č��������A�ʔ��������B���̂��̂��������A�ׂ��Ȃ��Ƃ�c��܂��Ă������{�l�̐S�ƍs���̓�����N���ɕ����яオ�点���B�X�C�X�̃}�[�T�ƃ��o�̃G�s�\�[�h�����グ���Ƃ���ɒ��ڂ��āB�ȁ`��E�E�E�ف`�ǁE�E�E�B
�������Ƀ��X�N����w�S���w�����̐S���w�I����_�͉s���ł������B�钆��24���߂��A�J�~�钆�A�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}���ꂩ��z�e���܂ŗ̎P�������ĕ����ċA�����B
-----------------------------
2016�N9��22��
��6�����N���B�����̓��X�N���Ɉړ����āA�A���̓r�ɒ����B�d���̂��߁A�ő�̖ړI�ł������w�Î��L�x�㉉�ό��ł����A���̑O�ɋA������H�ڂɁB�v�����Ȃ��Ƃ͂����A���������������c�O���ɂł���B
���́u�������v�̕��́u����v���u�v����u�g�S�ϗe�Z�@�v�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A���X�N���ł����Ƃ��s��ő傫�ȃL���X�g���̋���u�X�p�X�t���X�^����v�i�L���X�g�~�ϋ���j�����ɍs���B�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̖��҂ł���A�ʖ�҂ł�����㐢���y����Ɉē����Ă�����āB
�E���W�[�~�����烂�X�N���܂ł̓��}�A�����ă��X�N���s�����w�ƁA���X�A�����Ղ�Ǝ��Ԃ��������̂ŁA�㐢����̃��C�t�q�X�g���[���X�^�j�X���t�X�L�[�̔o�D�p���A�j�V���t�̉��o�_���܂߁A��������Ƙb�����Ƃ��ł��A��ώQ�l�ɂȂ����B�㐢����A�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂��B
�㐢���y����́A1972�N��ʌ����܂��44�B���Z���ƌ�A�Q�l���ɂӂƂ����������ɂ������Ƃ����������ŁA���\�A����̃��X�N���������ۊW��w���ۏ��w���ɓ��w����B���A�O�N�Ԋw�Ԃ����ނ��āA�T���N�g�y�e���u���N���������A�J�f�~�[(���ݕ�����w)�|�p�w���h���}���o�Ȃɓ��w�����B�����ŁA�݂�����A�X�^�j�X���t�X�L�[�E�V�X�e���Ɋ�Â��o�D�p���w�ԁB���ɁA�g�t�X�g�m�[�S�t�̒�q�������������[�E�v���g�L�����Ɋw���1997�N�ɑ��Ƃ��A�A�����o�D�Ƃ��ĕ����e���r�Ȃǂɏo�����Ă��鎞�ɁA2000�N�ɁA�A�j�V���t�Əo������B�A�j�V���t���w�����郏�[�N�V���b�v�ɎQ�����Ĉȍ~�́A�����m�[���C�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̌����ɂ��Q�悵�A�����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̖��ҁE�ʖ�E�}�l�[�W�����g�Ȃǒ��j�I�����o�[�Ƃ��Ċ������Ă���B���N��4���ɁA�A�j�V���t���́w�X�^�j�X���t�X�L�[�ւ̓��x�̖|����o�ŁB�����ʂɊ��Ă���B
���̃X�p�X�t���X�^����́A1812�N�i�|���I���푈�ɏ��������A���L�T���h��1��������݂̒����o���A�f�U�C���R���N�[�������āA�o���オ�����̂�1839�N�B�����A�X�^�[�����ɂ��A1931�N�ɔ��j����A���̐Ւn�ɃX�^�[�����͂��̋����4�{�قǂ̍����̃X�^�[�����̓��������Ă悤�ƌv�悵���Ƃ����B�����A����͎��������A���̌�Ւn�̓v�[���ƂȂ�A1989�N�̃S���o�`���t����ɏ��߂čČ��v�悪�����オ��A1994�N�ɍČ�����B�G���c�B�������1995�N1��20���A��_�W�H��k�Ђ�3����ɒ��H�B�v�[�`�������2000�N8��19���Ɋ����B���������s��ɍs��ꂽ�Ƃ����B
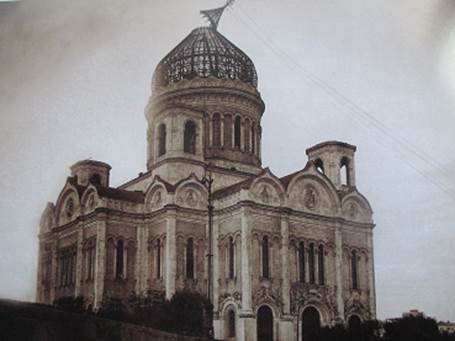
�j���O�̃L���X�g�~�ϋ���
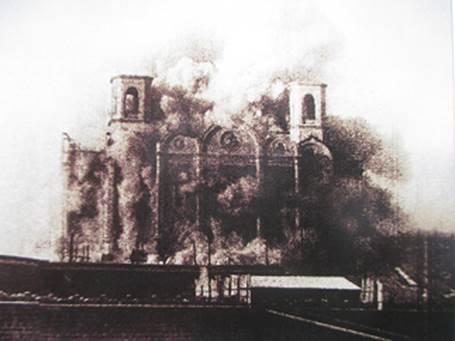
���j�����L���X�g�~�ϋ���

�L���X�g�~�ϋ���̐Ւn�Ɍ��݂��v�悳�ꂽ�X�^�[�����̓����i�E��̎��@���L���X�g�~�ϋ���̑傫���j
�����ɓ����āA���̑s�傳�ɋ������B�E���W�[�~���̃E�X�y���X�L�[�吹���̃C�R����������������A�����̌��z�̓�����Ԃ̑������ɂ͐�������B�����܂ŃC�R����t���X�R��Ŗ��ߐs�����������ȑ��`���p�͂��������Ȃ��B�v�[�`���哝�̂͐l�S�����p��S���Ă���̂��A���V�A������̗��j�I�������Ƃ��ă��V�A���O�̐M�ƐS�̋��菊�Ƃ��Ă��́u�L���X�g�~�ϋ���v���ő���ɗ��p�E���p���Ă���Ǝv����B���܂��ˁA���ɁA���̂����́B��㓌���s�m�������̐l�S�����p�̉��肳���ӂ݂�A���V�A�𑼎R�̐ɂ�����ǂ����ƌ����������Ȃ�B����قǁA���Ɏ��ڂ������A�L���X�g�����V�A������̑����̋ɂ݂����o���Ă���B���̂�������A���������ɋ��ʂ̃v�[�`�������V�A�l���Ɏt�������Ƃ���Ȃ̂��낤���H
�v�[�`���̋���ȓƍٓI���͂ƁA���V�A�l���̃��V�A�����I�L���X�g���̊Ƃ������p���āA�X�^�[���������������Ă悤�Ƃ��Čv������͂邩�ɗy���ɋ��x�ȋ���z�����݂���Ă���B
��1�T�ԂقǑO��9��14���A���V�A�ō����@���̓��V�A�A�M�ō��ٔ����ɃI�E���^�����̃��V�A�����ł̊������֎~����悤�v���������A���\�A��������̃A�m�~�[��Ԃ̒��ŐV�@�������Ȃ藬�s���݂��Ƃ����B�G�z�o�̏ؐl�ⓝ�ꋳ������̈�������Ƃ����B�I�E���^���������������̒��Ń��V�A�Љ�ɓ��荞�݁A���݂܂Ŋ����𑱂��Ă����悤�����A�����ɗ��Ă��悢�抈���֎~�̗v�����o�A9��20������R�����s�Ȃ��Ă���͂����B
�v�[�`���哝�̂́AKGB�o�g�Ƃ������A�l�X���������A�ǂ̂悤�ɂ���Έ���Ɛ����I�ȗ͂��s�g�ł��邩�A���ɂ悭�킩���Ă���悤�Ɍ�����B����̐��E��́A�č��̃z���C�g�n�E�X���M�̏��ƃ��V�A�̃N�����������M�̏��ƒ����̒���C���M�̏��ƃA���u���M�̏���4�ɏ����d�ˍ����Ȃ���A���̎��Ԃ������Ă��Ȃ��Ƃ������A���̒ʂ�ł��낤�B���̈Ӗ��ł��A�z���C�g�n�E�X��ӓ|�ɂȂ��Ă���č��̑����̓��{�̏��Ԃ͌����炯�Ƃ������A��Ƃ���ɂ܂�Ȃ��Ƃ����ׂ����B
����o�ϐ헪�ɂ��u�l�S�����p�v�Ƃ��������I�u�g�S�ϗe�Z�@�v�̌������K�v�ł���B�@���I�Ȑg�S�ϗe�Z�@����łȂ��A�|�p�I�Ȑg�S�ϗe�Z�@���A�����I�Ȑg�S�ϗe�Z�@���A������ƌ��āA���͂��Ă����K�v������B���ׂ����Ƃ͂܂��܂����ڂł���B
���́u�L���X�g�~�ϋ���v�Ȃǂ̕ϑJ�����Ă���ƁA�@���Ɛ������ǂ�قǖ��ڂɊւ�肠���Ă��邩���悭�킩��B
���ǁA���̉āA�������S�����烍�V�A�܂ŗ��𑱂����悤�ȁB��������1���L���߂��B�����S���R�̉����ɂ���
�������A���Ẵ����S���R�̉����́A�R�n�ł������B���̔n������āA�E���W�[�~�������X�N�����L�G�t���苒�����̂��A�����S���R�́B��������I�@�����13���I�ɁB�j�āI
�������āu���ۑ�v���ڂƑ��������Ăł������B
�P�A�����Ə@���Ƃ̊W�̍čl�@
�Q�A�@���ƌ|�p�Ɛ����̎O�������猩��g�S�ϗe�Z�@
�R�A�X�^�j�X���t�X�L�[�̐g�S�ϗe�Z�@�Ɛ�����̐g�S�ϗe�Z�@
�S�A���V�A�̃��A���Y���ƃ~�X�e�B�V�Y��
�T�A�L���X�g�����̐�����̓`���ƃJ�g���b�N�̓`��
�U�A�����S����13���I���E�j

���c���烍�V�A�Ɍ������r���̃��V�A�̎R���݁i�R���ɐႪ�ς����Ă���j

�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����

�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����

���o�ƃA�j�V���t���ƃE���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}���ꕛ�ْ���

�E���W�[�~���s�̃V���{���F�����̖�

�����̖�̗��̃C�R���F����}���A�ƃC�G�X

�����̖�̕\�̃C�R���F�C�G�X�E�L���X�g

�����S���E�^�^�[���l�̃E���W�[�~�������P���̖͌^�i�����̖唎���فj

13���I�Ɏg��ꂽ�V

��




�E�X�y���X�L�[�吹����]��





�E���W�[�~���ŌÂ̖�

�����̑�}�ցH


�E���W�[�~�������ōł��Â��E�X�y���X�L�[�吹���i12���I�n���j

�E�X�y���X�L�[�吹��

�E�X�y���X�L�[�吹���O�̃A���h���C�E���u�����t�̓���

�E���W�[�~���s�̋���

�������

��̃E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}��

�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ϋq��

���C�g�A�b�v���ꂽ�����̖�

�����̖�

�����m�Ò��̓����m�[���B�E���p�[�g���[�V�A�^�[�̖��҂���

�_���o������A�j�V���t�|�p�ēi�E�[�j

���C�V���L�����݂Ə��R

�Ō�̌m��
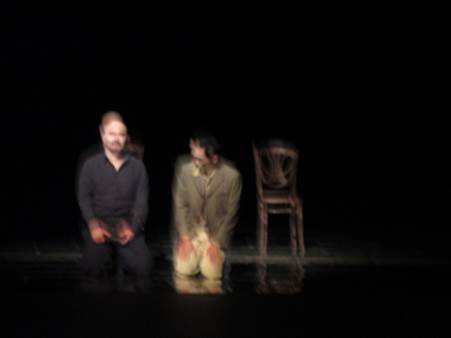
�r�����S�[�W���Ƙa�����C�V���L��
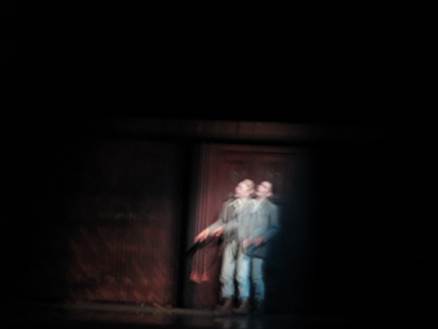
�h��郀�C�V���L����

�x���`�ɐQ�Ă��郀�C�V���L���Ɣw��̃A�O���[��

�x���`�̃��C�V���L���Ɣw��̃i�X�^�[�V��

�E���W�[�~���̃g���j�e�B����

�E�X�y���X�L�[�吹��

�E�X�y���X�L�[�吹��

�E�X�y���X�L�[�吹��



�E�X�y���X�L�[�吹���̃l�R�`����

�E�X�y���X�L�[�吹���̋u���猩���{���K��

�E���W�[�~���̊X�̕��i

�w���s�x�㉉��ɃE���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����3�K�ōs�Ȃ�ꂽ���e��

���e��ł̐����i�㉉���ꂽ����́w���s�x�̈��p�p���f�B�j

���X�N���̃L���X�g�~�ϋ���

�L���X�g�~�ϋ���̓����i����s�̎ʐ^�W���j

�L���X�g�~�ϋ�������̐��ʓV���

�L���X�g�~�ϋ�������̉E���V���

���X�N���N�����������̃E�X�y���X�L�[���@

���X�N���N���������O�̃��X�N����w

���[�j���}���قƂ��̑O�̃h�X�g�G�t�X�L�[�̓����i���̏�ɂ����܂��̂悤�ɔ����~�܂��Ă����j

�Ԃ̍L��ƃN��������

�N���������ƐԂ̍L���

�N�����������ʂ̃��[�j���_

�{���̋��s��掛�̉��ϒn���i�A���Ă��Ĉ�掛�̂��n���l���Q�q�B�z�b�Ƃ���ˁA�ǂ����j
���ڎ�2
2016�N9��22���@�ҐM�s�F�u���̂��ē��@�@���ڎ�2
�F����
�����́BNPO�@�l�������R��w�^�c�ψ����̒ҐM�s�ł��B
���c�搶�̂��������A�u���̂��ē��������Ē����܂��B
���T��24���i�y�j�A������w�����̊nj[���Y����ƍ�Ƃ̛I�M�q��������������A
�����ƒm �u���ƕ���`�A�W�A�ƃA�����J�̕Ӌ����߂����āv���J�Â��܂��B
�g�S�ϗe�Z�@������̊F���܂ɂ́A�����Ɗy����Œ�������e�Ǝv���܂��B
���Z�����Ƃ͑����܂����A�F���܂̂��Q�������҂����Ă���܂��B
--------------
�����ƒm
�u���ƕ���`�A�W�A�ƃA�����J�̕Ӌ����߂����āv
�I�M�q�~�nj[���Y
�����F2016�N9��24���i�y�j14:00�`16:30
�ꏊ�F �������R��w�i���R���u�E�R���e���c���{�j
��u���F ��� 2500�~�A��� 2000�~�A�w�� 1000�~�A�w�����500�~
�Q�����@�F�������R��wHP�̃R���^�N�g��ʁi���L�����N��j��肨�\�����݂��������B
HP�Fhttp://www.t-jiyudaigaku.com/contact/
�u���T�v�F
�l�ނ́A�������Ȃ��畨����ނ��A����̂Ȃ��ŗ������Ă܂����B
���܂ɓ`���_�b�⏖�����A�����|�\�ɂƂ��āA���͂ƂĂ���ȗv�f�ł��B
����́A���j���炱�ڂꂨ�����y�n�̐����E���ނ��A�z���̗����Â��Ă�����Ƃ̛I�M�q����ƁA��]���I�s�ɂ��Ȃ���A�����ꐫ�ƖS���E�ڏZ�̌o����w�i�ɂ������E���w��_���Ă������l�Ŕ�r���w�҂̊nj[���Y��������������A���ꂼ��A�W�A�ƃA�����J�̗��ƕ���ɂ��āA���b���������܂��B
�u�t�����F
�I�M�q�i���傤�̂Ԃ��j
��ƁB1961�N�A���l�s���܂�B������w�@�w�����ƁB1986�N�A�w�������ʂ̍ݓ��؍��l�x�Ńm���t�B�N�V���������W���[�i���܂���܁B�l�Ԃ��͂����ށu���Ɓv�u�����v���邢�́u�ݓ��v�Ƃ��������t���炱�ڂꂨ������́A�Ђ��₩�Ȑ���ǂ������āA�z���̗��𑱂���B�����Ɂw�����m�[�g�x�i�F�����w�܁j�A�w�� ��N��ɓ͂��قǂɁx�A�����Ɂw�Ǖ��̍���l�x�i�n���o�ŕ������J�܁j�B�Ғ��Ɂw���ʂӂ肾���ł�߂Ƃ���@欗Y�W�x�ق������B
�nj[���Y�i�����������낤�j
���l�A������w��w�@���H�w�����ȐV�̈�n����U�f�B�W�^���R���e���c�n�����B
1958�N���܂�B������w�A�n���C��w�A�j���[���L�V�R��w�A���V���g����w�ȂǂŁA�����l�ފw�Ɣ�r���w���w�ԁB�����Ɂw�R�����u�X�̌��x�A�w�T���A�ꂾ���đ��錎�x�A�w�ΐ��̗��x�i�ǔ����w�܁j�A�w�{�͓ǂ߂Ȃ����̂�����S�z����ȁx�B�����Ɂw�쐶�N�w�x�A�w�������E�̃|���g���[�m�x�B���W�uAgend'Ars�v4����́w�����_�x�������Ċ��������B�J���u�C�t�����X�ꌗ���w�A�`�J�[�m���w�Ȃǂ̖|��ł��m����B�ق����������B
--------------
���̑��ɂ��������R��w�ł͂��̏H�A���������
�v���O���������p�ӂ��Ă���܂��B
�ǂ̍u�������C�y�ɂ��Q���ł��܂��̂ŁA���Б������^�т��������B
http://www.t-jiyudaigaku.com/
--------------
10��1���F�����ƒmvol.04�u�v�z�̐X������v�@�u�t�F�������E�������
10��14���F�����[�~vol.01�u��ؑ�فE�܌��M�v�E�䓛�r�F�v�@�u�t�F�������
10��29���F�ܖ؊��V�u���u�߂̗́v�@�u�t�F�ܖ؊��V�@���F��q��w
11��11���F�����[�~vol.02�u��ؑ�فE�܌��M�v�E�䓛�r�F�v�@�u�t�F�������
11��12���F�@�����ĂȂɁHvol.02�u����3.0�v�@�u�t�F���c��Ɓ@���F�ڍ��s����
11��26���F�����ƒmvol.05�u�Ñ�l����̐S���Ǝ��̌����_�v�@�u�t�F�g������
12��9���F�����[�~vol.03�u��ؑ�فE�܌��M�v�E�䓛�r�F�v�@�u�t�F�������
12��10���F�@�����ĂȂɁHvol.03�u�P���g�́y�Đ��z�M�Ɓy����߁z�v�@�u�t�F�߉��^�|
1��13���F���c�[�~vol.01�u���{�̐_�X�Ɛ��n�v�@�u�t�F���c����
1��20���F���c�[�~vol.02�u���{�̐_�X�Ɛ��n�v�@�u�t�F���c����
1��21���F�@�����ĂȂɁHvol.04�u�ڂ��̐��n�Y���L�v�@�u�t�F�ז쐰�b�E�O��q��
2��11���F�@�����ĂȂɁHvol.05�u�R���̒q�d�Ƌ����v�@�u�t�F��{��O�Y
--------------
�������Ō�܂ł��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�G�߂̕ς��ځA�F���܂̂����������F�肵�Ă���܂��B
�ҐM�s �q
���ڎ�2
2016�N9��20���@���c����F���R�C�����A�E���W�[�~��������������@�@���ڎ�2
2016�N9��20��
��6���A���V�A�A�E���W�[�~���s�̃z�e���Ŗڊo�߂�B
���V�A���J�|�p�Ƃ̃��V�A�l���o�ƂŁA�����m�[���B���p�[�g���[�V�A�^�[�̌|�p�ē߂Ă��郌�I�j�[�h�E�A�j�V���t���ƁA�ނ������铌���m�[���B���p�[�g���[�V�A�^�[�̌��c������40���Ƌ��ɂ��̒n�ɂ���Ă����B
�A�j�V���t���Ƃ́A����12��18���i���j�ɁA�{�g�S�ϗe�Z�@�������Â̍��ۃV���|�W�E���u������ƃX�^�j�X���t�X�L�[�v���J�Â���B
����2�T�ԁA���V�A�̃E���W�[�~���s�̒��S�ɂ���E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ŁA�����t�F�X�e�B�o�����J�Â���Ă���B�����ŁA�A�j�V���t���̉��o�ɂ��h�X�g�G�t�X�L�[��́u���s�v������9��21���ɏ��Ҍ��������̂ł���B
���̌�A���X�N���Ɉړ����A9��23���ɁA�킽����������w����Î��L�x������ɃA�j�V���t�������o���������m�[���B�[���p�[�g���[�V�A�^�[�́w�Î��L�x���㉉���邱�ƂɂȂ��Ă���B�{���ɗL����Ƃł���B���̂��Ƃ����蓯�s���@�Ƒ����������A�����ɁA���V�A�̏@���{�݂�g�S�ϗe�Z�@�̂���悤��_�E�v�z�A�l�X�̊�����̂ɂ��ڂ������Ă݂����B���ɁA���V�A�����̋���₻���ōs�Ȃ��Ă���T��V���A�l�X�̐M�Ȃǂɒ��ׂĂ݂����B
���s���琬�c��`�`���X�N�����o�R���A���X�N���̓�����200�L���A���V�A�ŃL�G�t�����Ɏ���2�ԖڂɌÂ��ƌ�����Ós�E���W�[�~���ɓ��������B�����͍��9��19���̐[��23���������B�a�̂��߃��X�N������o�X��5���Ԉȏォ�������B��s�@�̃t���C�g������ƁA�����20���ԋ߂��Ԓ��ɂ������ƂɂȂ�B
�����́u���s�v�㉉�O�ɁA�܂��͑��ɓy�n�̐���ɂ����A���邱�Ƃ�����A�A�j�V���t����⌀�c���݂̂Ȃ���ƈꏏ�ɃE���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����̕��ْ�����ɉ������A�E���W�[�~���s�������������B
�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����O�ƁA�N�j���[�M�j���X�J������O�ƁA�{���K��������낷�u�˂̏��3�����Ŗ@���L���t�B�z�e���ł͂������A���̂��߂̒��ŁA�킪�O��̐_��̐ΓJ�E���J�E�@���L���t�������A�߂��̃��V�A�l�h���q�͂����������̉��ɂ͂т����肵�����Ƃ��낤�B
���̃E���W�[�~���Ƃ����X�́A���āA�E���W�[�~�������̎�s�ł��������A���s�Ɏ����Ƃ��낪����Ɗ������B���s�͓ޗǂɎ������{���̌Ós�ł��邪�A���̃E���W�[�~�����A�L�G�t�Ɏ������V�A���̌Ós�ŁA�Ȃ��炩�ȋu�̏�ɂ���B
�X�S�̂��u�˂̏�ɂ���̂ŁA�y�������ߓn�����Ƃ̂ł��钭�]�̂悢�n�_���e���ɂ���B
�����A���w�����Ƃ���ł́A���ɐ��E��Y�ƂȂ��Ă���E�X�y���X�L�[���@�̃o���b�N�C�R���悪�����������B�o���b�N���p���C�R����Ƃ��Ď��߂��L���X�g�����@�Ƃ��Đ��E��ԈႢ�Ȃ��B����قnj����ȂƂ������A�����Ƃ������A�����I�ȃC�R����͌������Ƃ��Ȃ��B�܂��ɁA�C�R���E�}���_���B�o���b�N��䶗����E�ł������B
�s���̎�v�{�݂ɂ��āA�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����̎x�z�l����z���Ă��ꂽ�������ē����A���J�Ȑ��������Ă��ꂽ�B�ޏ��̐����ł́A992�N�ɃE���W�[�~����������n��ꂽ�Ƃ����B�����ɂ́A�傪5����A�����c���Ă���̂��A1164�N�ɑ����Ƃ��������̖�ŁA���̕\�ɃL���X�g�̃C�R���A���ɐ���}���A�̃C�R�����`����Ă���B
�����A13���I�����A�����S���E�^�^�[���R�ɍU������A���N�ɂ��킽�錃�����킢�̌�A�I�ɁA1239�N�A�E���W�[�~��������̓����S���R�ɋ����A���̌�A���V�A�̒��S��s�@�\�́A�L�G�t�A�E���W�[�~���Ɏ�����O�̎�s���X�N���Ɉڂ����B
�����[���̂́A���{�������S���ɐN�U���ꂽ�̂��A1274�N�̕��i�̖���1281�N�̍O���̖���2�x�ŁA�ÌR�͑䕗�ɏP���āA���́u�_���v�ɓ��Ă��đގU�����Ƃ���Ă���_���B���̂ق�40�N�O�Ƀ����S���R�́A�E���W�[�~������������j���A���X�N���ɂ܂Ői�R���Ă����̂��B���̋R�n�R�c�����S���R�̋��Q���ׂ������ւ̊g���̈ӎu�Ƃ��̐퓬�\�͂Ǝ������̐��܂������_�Ԍ���v���������B�u�����v�Ƃ���Ă��鎖�Ԃ����E�j��傫���h��ւ����̂��B13���I���E�v���A�����S�����m�̓��[���V�A�嗤���A����A�n�����A�k���������̂������B������A�����S���R�́B
�Ƃ���ŁA���̉����̖���ӂɂ͓y�ۂ��z������Ă������A�G�J�e���[�i2���i1729�|1796�j�����X�N�����痈�����ɁA�n�Ԃ��ʂ�Ȃ�����Ɖꂽ�Ƃ����B
���̃G�J�e���[�i2���́A���݂͐��E��Y�ƂȂ��Ă���A�E���W�[�~���̍ō��ő�̏@���{�݂ł���E�X�y���X�L�[�吹���i���_���A�Q�吹���j�ɑ��z�̊����A����ɂ��A�o���b�N�l���̑s��E�����ȃC�R���悪��R�`���ꂽ�Ƃ����B���z2~3���~�ɋy�Ԋ��Ƃ��B���̃E�X�y���X�L�[�吹����1158�N����1160�N�ɂ����đ���ꂽ�Ƃ����B���{�ł́A�ی��̗��i1156�N�j�E�����̗��i1159�N�j���N�����Ă���A���~�̌����u���҂̐��v�̓����̍��ł������B
���̃E�X�y���X�L�[�吹���̒��ɃA���h���C�E�{�S�����u�X�L�[�Ȃǂ̑���̈�̂����[����Ă���B�����̃C�R����́A�A���h���C�E���u�����t�i1360�|1430�j���`�����B���{�ł́A������i1363�|1433�j�����Ă��鍠�̂��Ƃł������B���u�����t�Ɛ�����Ƃ́A�قƂ�Ǔ������������A�����̍ō����͎҂̉��ŁA�|�p�E�|�\�Ɋւ�錆�o�����˔\���J�Ԃ������B
���u�����t�́A1405�N���ɏC���m�ƂȂ�A�u�����O�ҁv�i���O�ʈ�́j�Ȃǂ̃C�R�����`�����B���u�����t�́A����܂ŃM���V�����̊��`���l������X���u�l���̊��`�������ɓ]�������B���V�A�l�ɐe���݂₷���C�R�����`���n�߂��ŏ��̐l���Ƃ����B�w�f���\�����X�x�̊ēA���h���C�E�^���R�t�X�L�[�́A1967�N�Ɂw�A�������C�E���u�����t�x�삵�A1969�N�̃J���k���ۉf��Ղ̍��۔�]�Ə܂���܂����B
���u�����t�̏������C�R����̑s�傳�ɂ͋���������B�������B�X�����B�~�Q�����B���t���������B���������A�����B�Ƃ����ق��Ȃ������B�E�X�I
�����āA��A�E���W�[�~���B���A�J�f�~�[�h���}����ŁA���㕗�ɃA�����W���ꂽ�`�F�[�z�t����́u�����߁v����ł��ό������B�����͂��悢��A�j�V���t���o�A�����m�[���B���p�[�g���[�V�A�^�[�ɂ��u���s�v�㉉�ł���B�ڂ��M�ɂ��Č��͂������B
���ڎ�2
2016�N9��15���@���c����F���R�C�����R�V�R�@�@���ڎ�2
2016�N9��14��
�����͉J�̓V�C�\�������A�܂�B
�������A�����p���p���b�Ɨ������A����ȏ�̖{�~��ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
���s��w���F��قƐl�ԁE���w�����Ȃ̐}���قɗp���ŏo�����A������I���āA15��40���A���R�C�����o���B
��X�_�Зy�q�B
���R�����グ��B

�{���̔�b�R
�R�����ۂ�������B
�����͂����₩�����B
�֎�@�ٓV���ƓV���{�Q�q�B
�_���ɓ���B

�{���̐X�̋��N
�X�̋��N�́A�܂����肪�������A�ނɂ͂悢���~�H

�{���̐X�̗d���N
����A�X�̗d���N�́A�Ă�Ă�B
�|��Ă��A���H��ʊ�ňЌ���ۂ��Ă���B
�����ˁA���̕s���S�E�s���g�B
���X�y�N�g�ɒl����B

�{���̉���
���ꂪ������������Ɨt�������Ă��āA���E���L�������悤�ȁB

�{���̃i���͂�̓�
���n�̔w�̃i���͂ꋐ�̓����A�����͂��������Ă��銴���B

�{���̐X�̃��A�C�N

�{���̐X�̃��A�C�N
�X�̃��A�C�N�́A�X�̗d���N�Ɠ��l�A���ς�炸�́A�j�R�j�R��B
�s���S�{�s���g�B�����ˁA���A�C�N���B
���X�y�N�g�ɒl���܂��I

�{���̐X�̂��n���l

�{���̐X�̂��n���l
���n���l�̑O�X�p���B
�����A�}���ł���悤�ŁB
�����Ă���l�X�������ɏ����ɍs���̐��ŁB
����͕s���g�ł͂Ȃ��A�����S�{�����g�B
�����ˁA���n������B
���̋C�\���A�S�\���A�̍\���B
�o������Ă��܂��I
���X�y�N�g�ɒl���܂��I
���X�y�N�g�ɒl����ƌ����A�P�[������B
��ɉi���̖����˂��t�������{�l�B
�u�Y��悤�Ƃ��Ă��A�v���o���Ȃ��v�Ƃ����i�v����B
���̓�����́A���@������ł͉����������ւ�B
�����Ȍ��łȂ܂ł̋��ȁE���܃��[�v�B
���r�E�X�̗ցA�N���C���̚�̂悤�ȁB
���X����Ȃ̂����A���ꎟ���ł͂Ȃ��B
�َ������A���̂܂ɂ��������ɗZ�����Ă��܂��Ă���B
�u��Ζ����I���ȓ���v
�u�ϔY�����v
�u������@�v
����Ȃ��Ƃ����肤��̂��H
�_���I�ɂ��蓾�Ȃ����Ƃ��݂蓾��Ǝ咣����_���B
�o���ǂ���������B
�i���Z���X�t����ӂƂ����Ԓ˕s��v�́A���B���M�͏�灤�����Ök�Ï闡�ɐ��܂ꂽ�B
���̒��ؐl�����a���͖k�ȏ����s灤�����Ɩk���s���_���Ök���Ƃ̌����ɓ�����Ƃ����B
��͏�����2��s���Ă���B
�C���̃V���|�W�E���ŁB
�����ɂ́A�����̗��{�������āA�����������h�ȃ��}�����@������A���̉A�z���������B
�P�C�X�C��Ƃ����Ƃ��ƌ������B
����Ȉٍ��ً��̒n��10�܂ň�����Ԓ˕s��v�́u�S�̕��i�v�́A�u�Y��悤�Ƃ��Ă��v���o���Ȃ��v�s�v�c�ȋ��Ȃɖ����Ă������̂������̂��낤�B
�����x�@���ł�������ό��i�ȕ��e�́A�s�펞�ɂ͕�V�ŁA��V�S�����h���̏����ɂȂ��Ă����Ƃ����B
�����āA�푈���I����āA�\�A�R�ɘA�s����ČR���ٔ��ɂ������A4�N���V�x���A�ɗ}�����ꂽ�Ƃ��B
����́A�Ԓ˕s��v�ɂƂ��āA�u�Y��悤�Ƃ��Ă��Y����Ȃ����A�������܂��A�v���o�������Ȃ��v�o�����̏W�ς������̂ł͂Ȃ����B
���̂悤�ȋ��Ȃ�}���́A�u�Y��悤�Ƃ��Ă��A�v���o���Ȃ��v�Ƃ�������ɑ������邱�Ƃɂ���āA��̓˔j�����B
�P�[��̘_���́A�M���O�i�t�H�@�s�H�j���扻�̐Ԓ˕s��v���~�ς����B
�P�[��͂�A���͂�́A���X�y�N�g�ɒl���܂��I
�����āA����Ɋ������A�h�ӂ��������Ԓ˕s��v�͂�A���͂���A���X�y�N�g�ɒl���܂��I
�S���h�ӂ�\���܂��B
�A�����H�E�y���g���A�R��B
�ނ̓G�X�g�j�A���܂�B
���\�A�̐����I���͂̒��ŁA�u���Ȃ�Â����v�̃~�j�}�����y�ɍs���������B
����́A�O���S���A���O���̂悤�ȁA�S���ՔO���̂悤�ȁA���ꖽ��̌J��Ԃ������Ζ���ɗ��Ԃ��Ă���悤�ȁA�������]���N���鋆�ɂ̃~�j�}���E�~���[�W�b�N���B
�Ƃ�킯�A�uCantus in Memoriam Benjamin Britten�v�̏��̉��ɂ́A���̔��]�Ǝ����Z����������B
�����I
�����Ȃ��̂Ȃ����̉��B
�A�����H�E�y���g�͂�A���͂���A���X�y�N�g�ɒl���܂��I
�ƁA���X�y�N�g�����̓o�q�́A�������A�w�тɓ����B

�{���̞w��
�`�����ށB
�`�����܂��B
�ė�����B
������B
��Ζ����I���ȓ���B
�ƁA�ڂ̑O�ɁI
�j�āI

�{���̐X�̎��N
�V�V�_�N���I
�V�V�_�N�A���͂���A���R�A�K�R�A���X�y�N�g�ɒl���܂��I
1���قǂ��A�����ƌ��ߍ����Ă����B
���肪�Ƃ��������܂��I
�����u�ցB

�{���̂����u�̂��n���l
���n���l�̑O�ŁA�ʎ�S�o�Ɗe��^���B�����ĘZ���q�B

�{���̂����u
�����u�������i��]�ށB

�{���̐���R

�{���̔��i��
�������A�|�������������B
���肪�Ƃ��������܂��B
�l�H�X�L�[��ՂŃo�N�]3��B�ł�Ԃ�12��B
�t���t���B
���R�B

�{���̐X�̗d���N��2��
�X�͂�������H���[�܂�A�}���ɈÂ��Ȃ��Ă����B
��X�_�ЎQ�q�B
���q12�q�B
�_���ɉf�肵���m�B

�{���̍�X�_�Ђ̐_��
����́H
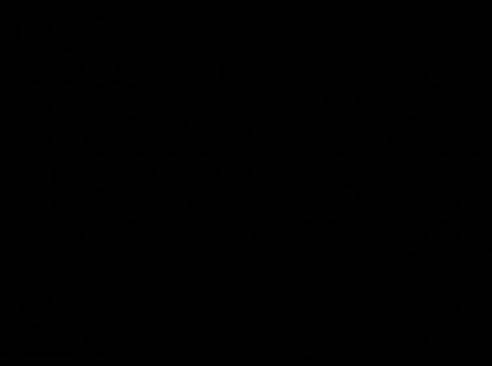
�{���̍�X�_�Ђ̐_��

�{���̍�X�_�Ђ̎Q��
���ł��������B
�j�āI
�u�Y��悤�Ƃ��Ă��A�v���o���Ȃ��v���m������I
���ڎ�2
�g�n�l�d�@�ڎ�2�@�@���O��